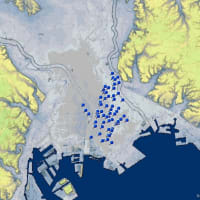先週の土曜日(11/2)グリーンパレスにて開催された、
「江戸川区の歴史を学ぼう」考古学ゼミナールPart1~縄文時代」
に出かけてきました。
江戸川区の歴史を学ぼう
考古学ゼミナールPart1 縄文時代
講師:お茶の水女子大学教授・鷹野光行先生
日時:平成25年11月2日(土曜日)午後3時~4時30分
会場:グリーンパレス
主催:江戸川区歴史民俗史話会
後援:江戸川区教育委員会
→http://www.city.edogawa.tokyo.jp/eventcalendar/kozakoen/251019history/index.html

「江戸川区の歴史を学ぼう・考古学ゼミナールPart1」の
第2回はお茶の水女子大学教授・鷹野光行先生の「縄文時代」です。
講義資料を参照引用しながら概要をアップします。
〇縄文時代とは
「日本列島の歴史の中で、
旧石器時代→縄文時代→弥生時代→古墳時代・・・
と、二番目に古い時代であり、列島の大部分で土器が
作られ使われ始めてから稲作による主要な食糧生産方式を
手に入れるまでの時代。」
〇考古学について
「広義の歴史学の一分野で、発掘を行うことを本領とし、人類が
残した物質的資料、つまり遺跡・遺物の解釈を通じて、人類の
過去の生活ないし文化の変遷を明らかにする科学」
※引用:『世界考古学事典』1979 関野雄
〇旧石器時代から縄文時代になって何が変わったのか
・弓矢が伝わる
ヤジリが出てくる。
旧石器時代:有舌尖頭器 幅2~3cm、9cm×3cmで厚さ1cmなど
縄文時代:石鏃 長さ1~3cm、2g以下
・土器造りが伝わる
大陸から、おそらく北回りで、あるいは日本海を渡って直接に
これらが何をもたらしたか→食糧の範囲の拡大

小林達雄氏、「縄文人の生活カレンダー」
※引用:江戸川区の歴史を学ぼう 考古学Part1縄文時代
※土器その他についての解釈は、いくつかの説があるとのこと。
「考古学について」では、考古学者、喜田貞吉氏の
「ものが出なければ、ものが言えない」という
言葉の紹介がありました。
何もないところからは何も語れず
すべては科学的検証の積み重ねで明らかにしていく学問
とのお話は、端的な言葉とともに印象に残りました。
「旧石器時代から縄文時代になって何が変わったのか」では
食糧範囲の拡大というお話のなかで
狩りでは少し離れたところからでも獲物がしとめられるようになり
土器伝来によって、たとえばドングリなどの木の実は
煮炊きや灰合わせ(アルカリ中和)などの工夫によって
食べられるものが大幅に増えたとのことです。
また、これらの食糧調達を自然のサイクルに合わせていた
とのお話は興味深かったです。