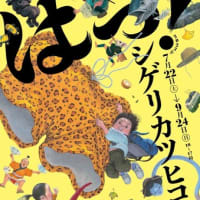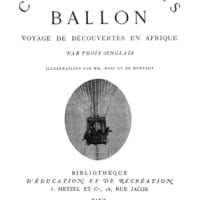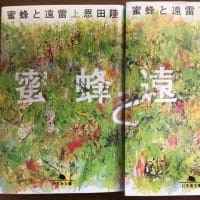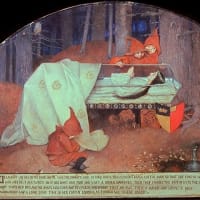NH朝ドラの「花子とアン」。
NH朝ドラの「花子とアン」。
はなは女学校の高等科を卒業して、出版社に勤務するかと思ったら……
「採用すると」言われたのに、すみませんと断って、田舎の甲府に帰ることを決意した。
そして、どうやら地元の小学校の先生として働き始めたようだ。
自分が帰ってくることを心待ちにしていた母親のことを思えば、そうせざるをえなかったのだ。
『赤毛のアン』のなかで、大学に進学するための奨学金を獲得しながら、それを断ってアボンリーに戻り、マリラとともに生活することを選んだアンのように。
「花子とアン」は『赤毛のアン』のオマージュと言ったけど、物語の構成まで、かぶっているわけだ。
 さて、はなの場合は朝ドラなので、泣く場面はあったけれど、わりとさらりと反転した。
さて、はなの場合は朝ドラなので、泣く場面はあったけれど、わりとさらりと反転した。
いっぽう『赤毛のアン』のなかでは、アンの葛藤は読むものの心を強く打つ。
映像は説得力で活字をしのぐと言う人もいるけれど、言葉を紡ぐことで心の動きや、物語の背景を語るほうが、ずっと説得力と力がある。
(朝ドラと、読み継がれてきた優れた物語を比べるのは不公平だけど。)
 『赤毛のアン』のなかで、アンの涙と重苦しい心。
『赤毛のアン』のなかで、アンの涙と重苦しい心。
輝く未来につづく道をあきらめるのは、苦しい選択だ。
だけど「ベッドに入るころには唇には微笑がうかび、心は平和になっていた。アンは自分のすべきことを見てとった。これを避けずに勇敢にそれを迎えて生涯の友としようと決心した。──義務もそれにぶつかるときには友となるのである。」と作者のモンゴメリは書いている。
そしてアンにこんなふうに言わせている。
「…あたしがクィーンを出て来るときには、自分の未来はまっすぐにのびた道のように思えたのよ。いつもさきまで、ずっと見とおせる気がしたの。ところがいま曲がり角にきたのよ。曲がり角をまがった先になにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの。それにはまた、それのすてきによいところがあると思うわ。その道がどんなふうにのびているかわからないけれど、どんな光と影があるのか──どんな景色がひろがっているのか──どんな新しい美しさや曲がり角や、丘や谷が、そのさきにあるのか、それはわからないわ」
それはわからないけれど、自分が何を最優先に考え、どんなことを大事にして生きるのかは、確認できる。
「ええっ、もったいない」と大事な人との関係よりも自分の将来像を優先させたとき、そこにあるのは……。
読者の共感を呼ぶ箇所は、昔も今も変わらない。
 そして、とにもかくにも、アンもはなも地元の学校の先生になったのである。
そして、とにもかくにも、アンもはなも地元の学校の先生になったのである。
はなの曲がり角のさきには、どんな物語があるのだろう。
『赤毛のアン』のファンとしては、朝ドラから目が離せない。