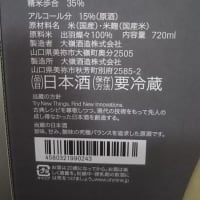皆さん、こんにちは!
プロ研修講師・プロコンサルタント・中小企業診断士のあお先生こと青木公司です。
本日2つめのブログは「中小企業診断士二次試験突破のために変わったところはあるか?」という事についてです。
中小企業診断士二次試験については平成13年からの新制度になってから、平成18年の制度改革などはありますが、大きくは変わっていないというところが言われていました。
しかし、合格者を見ていると明らかに変わってきたところもあると思います。
二次突破のための王道のやり方は踏襲しつつもここに対応しなければ合格できません。
変わってきたところは以下です。
1. 事例1-3について与件文、図表、設問文の文章が長くなっている。
例えば事例1-3については過去、2ページ半程度だったのが3ページ、図表を含めれば4ページにも至るケースが増えています。
さらに設問文も長くなっています。
迅速に正確に情報を把握、収集する能力を上げる必要があります。
さらに複数の設問の制約条件をおさえる必要があります。
2. 迅速な編集力+ダメ押し力が求められている。
解答文字数は必ずしも多くなっていません。よって多く与えられた設問、与件を過去よりより、正確に編集したうえで、作問者が求めている解答の因果の果
を叩き込んで加点要素につまった筋肉解答をする必要があります。
3. トレンドの知識の把握
サブスク・ブランド戦略などについても最新の知識をしっていれば有利になるような作問も見受けられます。
トレンド情報もおさえると有利になる傾向があります。
(読解力と対応力でなくても解答できるものの)
3. 事例4について、圧倒的読解力のスピードと正確性が求められる。
事例4は過去は5ページ程度だったものが、7-9Pにも至る問題になっており、設問文の長さも異様に長い問題が出てきています。
圧倒的読解力のスピードと正確性、そして計算速度が求められます。
4. 徹底的に受験生が苦手なNPVや企業価値計算などファイナンス問題を毎年出したうえで、損益分岐点や限界利益系の問題もバリエーションを変えて出している。
しつこいくらい出ており、どんなパターンで出ても対応力が求められる。
5. 試験として戦略的な対応力が求められている。
どの問題を完璧にとき、どの問題を部分点狙いで行くかなど、戦略的な対応が求められている。
6. 一日、事例1-4まで実力を出し切るスタミナとメンタルが求められている。
ボリュームが多くなり、神経も使う試験になっていて、事例1-4まで頭もメンタルも体力も非常に消耗する試験になってきています。
これに対応する力の工場が重要です。
1-6について、実は本気道場でも対応してきた力が求められるのですが、さらに、上記を踏まえて最強の指導をしていきたいと思います。
わが本気道場にて。
全国各地の大手企業、特許法人や社会保険労務士法人など士業事務所、大手企業労働組合、中小企業の多くのコンサルティング。
全国各地の大手企業の研修講師、経営者向けセミナー講師、講師・プロコン指導、二次合格率43%の中小企業診断士受験講座講師の青木の講師、コンサルティングのお申し込み、お問い合わせは以下青木のメールアドレスまで
↓
masteraochan@yahoo.co.jp