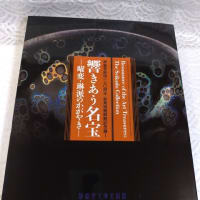【注意事項】
1)本記事は、吉川弘文館刊「永青文庫叢書
細川家文書中世編」を参照しています。
2)現代語訳は純野の“意訳”ですので、訳
し間違いがあるかもしれません。
3)カッコ内は、現代語に直した場合意味が
通じない可能性のある部分に純野が追記した
文言です。
4)現代の歴史書物と異なる表記がある場合
はなるべく原文のままとしました。
09織田信長黒印状 天正二年八月十七日
<本文>
摂州方面に至り、敵が軍働きをしているとの
由承った。(貴殿の働きがあれば)細かいこと
まで相談する必要は無かろうが、(適切に)手
当てすることが肝要である。事実としてうかが
うところによれば、(貴殿が)自ら日の出(現
在の天王寺区玉造?)に陣をとったのは然る
べきこととと存じ上げる。
(なお当方が陣をとる)こちら(河内・長嶋)
の方面のことだが、(伊勢)篠橋(しのはせ)が
(8月12日に)落居してからいよいよ(敵勢を)
押詰め、(伊勢)長嶋の構えに川一本挟んで
追い込んだ。(敵勢は)色々・様々に詫び言を
申上してきたが、火急に(当方への誓約を)
果たすことが然るべしと思うのだが(敵勢から
は)承引がなかった。
(一方)大坂(本願寺)の坊主が(こちら方面
のことを含めた)迷惑を仕出していると聞いて
いる。これにより、我々の身方が(成し遂げよう
としている事が)方々で成り立たない状態であり、
調略等により(うまく)取り計らう必要がある。
そちら方面の事についてはいよいよご油断なく、
明智(光秀)と相談され、(貴殿の)才覚を専一
にして活動頂きたい。近日(当方が)上洛した
時は、(貴殿に)摂(津)・河(内)方面を平定
するようお願いすることにしたい。なおそれ以上
は、時候に従ったのちの手紙でお知らせする。
謹言。
天正二年八月十七日 信長(黒印)
長岡兵部大輔(藤孝)殿
※天正二年=1574年
**純野のつぶやき**
天正二年(1574年)の前回の書状(八月五日)
から十二日後の書状です。史実では、篠橋(しの
はせ)の敵には「長嶋本坊に入り、信長に内応し
て忠節を尽くせ」と命じたことになっていますが、
今回の手紙では「火急に(当方への誓約を)果た
すことが然るべしと思うのだが(敵勢からは)承引
がなかった。」と微妙にニュアンスが違う内容で
長岡藤孝に伝えようとしています。細かく今回の
書状を見てみると、
*敵勢は色々・様々に詫び言を申上してきている。
*ところが信長方が誓約を守らせようとした内容
については承引しない。
という状態のようです。もし信長公が勉強熱心で、
およそ百年前の加賀国一向一揆(15世紀後半)の
ことを研究していたなら、一向宗徒の精神性を把握
して、
➢武器を信長の軍に差し出し二度とこの界隈で反抗
的活動を行わないと誓約するなら降参を許す。
➢かつ、一向宗(=浄土真宗/本願寺)から他の一
般宗教に寝返ったものは降参を許す。
と命じていたのではないかと思います。ただ信仰心
の篤い人々は「武器の貢納はまだしも、棄教するく
らいだったら死んだほうがまし!」と思ったのでしょ
うか、悲惨な結末となってしまいました。
以上
1)本記事は、吉川弘文館刊「永青文庫叢書
細川家文書中世編」を参照しています。
2)現代語訳は純野の“意訳”ですので、訳
し間違いがあるかもしれません。
3)カッコ内は、現代語に直した場合意味が
通じない可能性のある部分に純野が追記した
文言です。
4)現代の歴史書物と異なる表記がある場合
はなるべく原文のままとしました。
09織田信長黒印状 天正二年八月十七日
<本文>
摂州方面に至り、敵が軍働きをしているとの
由承った。(貴殿の働きがあれば)細かいこと
まで相談する必要は無かろうが、(適切に)手
当てすることが肝要である。事実としてうかが
うところによれば、(貴殿が)自ら日の出(現
在の天王寺区玉造?)に陣をとったのは然る
べきこととと存じ上げる。
(なお当方が陣をとる)こちら(河内・長嶋)
の方面のことだが、(伊勢)篠橋(しのはせ)が
(8月12日に)落居してからいよいよ(敵勢を)
押詰め、(伊勢)長嶋の構えに川一本挟んで
追い込んだ。(敵勢は)色々・様々に詫び言を
申上してきたが、火急に(当方への誓約を)
果たすことが然るべしと思うのだが(敵勢から
は)承引がなかった。
(一方)大坂(本願寺)の坊主が(こちら方面
のことを含めた)迷惑を仕出していると聞いて
いる。これにより、我々の身方が(成し遂げよう
としている事が)方々で成り立たない状態であり、
調略等により(うまく)取り計らう必要がある。
そちら方面の事についてはいよいよご油断なく、
明智(光秀)と相談され、(貴殿の)才覚を専一
にして活動頂きたい。近日(当方が)上洛した
時は、(貴殿に)摂(津)・河(内)方面を平定
するようお願いすることにしたい。なおそれ以上
は、時候に従ったのちの手紙でお知らせする。
謹言。
天正二年八月十七日 信長(黒印)
長岡兵部大輔(藤孝)殿
※天正二年=1574年
**純野のつぶやき**
天正二年(1574年)の前回の書状(八月五日)
から十二日後の書状です。史実では、篠橋(しの
はせ)の敵には「長嶋本坊に入り、信長に内応し
て忠節を尽くせ」と命じたことになっていますが、
今回の手紙では「火急に(当方への誓約を)果た
すことが然るべしと思うのだが(敵勢からは)承引
がなかった。」と微妙にニュアンスが違う内容で
長岡藤孝に伝えようとしています。細かく今回の
書状を見てみると、
*敵勢は色々・様々に詫び言を申上してきている。
*ところが信長方が誓約を守らせようとした内容
については承引しない。
という状態のようです。もし信長公が勉強熱心で、
およそ百年前の加賀国一向一揆(15世紀後半)の
ことを研究していたなら、一向宗徒の精神性を把握
して、
➢武器を信長の軍に差し出し二度とこの界隈で反抗
的活動を行わないと誓約するなら降参を許す。
➢かつ、一向宗(=浄土真宗/本願寺)から他の一
般宗教に寝返ったものは降参を許す。
と命じていたのではないかと思います。ただ信仰心
の篤い人々は「武器の貢納はまだしも、棄教するく
らいだったら死んだほうがまし!」と思ったのでしょ
うか、悲惨な結末となってしまいました。
以上