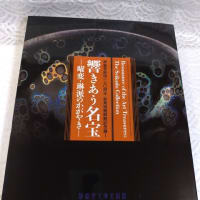戦国時代の単位 長さ・距離
1)上古の長さ
*1咫(あた)=親指と中指を広げた長さ。
約22.5cm?
2)戦国時代の長さ・距離
*1寸(すん)=3.03cm
*1尺(しゃく)=10寸=30.3cm
*1間(けん)=6尺=1.818m
*1段(だん)=6間=10.908m
*1町(ちょう)=10段=109.08m
*1里(り)=36町=3926.88m
【備考】
なお一般の歴史書には書いてありませんが、
全国1里=36町
に統一したのは豊臣秀吉の業績です。それまでは、
平安時代は一里=5町次いで6町
その後一里=30町・36町など
となり戦国期には、
北条氏: 1里=6町
今川氏: 1里=60町
武田氏: 1里=6町と36町を併用
筑紫 : 1里=50町
畿内 : 1里=36町
などバラバラでしたが、
朝鮮の役中に北九州地区に1里塚を築き、
1里=36町と定め、長さの全国統一をスタート
したそうです。(備考は「山川出版社 体系
日本史叢書24 交通史」より引用)
 にほんブログ村
にほんブログ村
1)上古の長さ
*1咫(あた)=親指と中指を広げた長さ。
約22.5cm?
2)戦国時代の長さ・距離
*1寸(すん)=3.03cm
*1尺(しゃく)=10寸=30.3cm
*1間(けん)=6尺=1.818m
*1段(だん)=6間=10.908m
*1町(ちょう)=10段=109.08m
*1里(り)=36町=3926.88m
【備考】
なお一般の歴史書には書いてありませんが、
全国1里=36町
に統一したのは豊臣秀吉の業績です。それまでは、
平安時代は一里=5町次いで6町
その後一里=30町・36町など
となり戦国期には、
北条氏: 1里=6町
今川氏: 1里=60町
武田氏: 1里=6町と36町を併用
筑紫 : 1里=50町
畿内 : 1里=36町
などバラバラでしたが、
朝鮮の役中に北九州地区に1里塚を築き、
1里=36町と定め、長さの全国統一をスタート
したそうです。(備考は「山川出版社 体系
日本史叢書24 交通史」より引用)