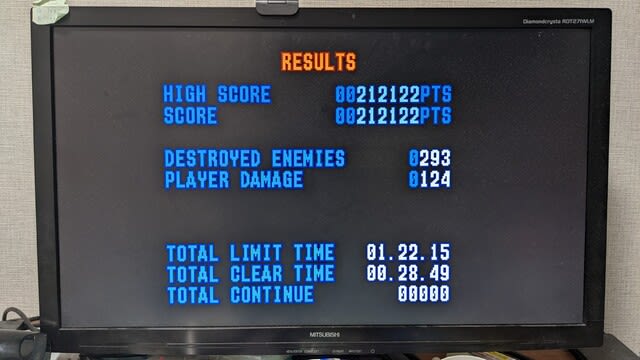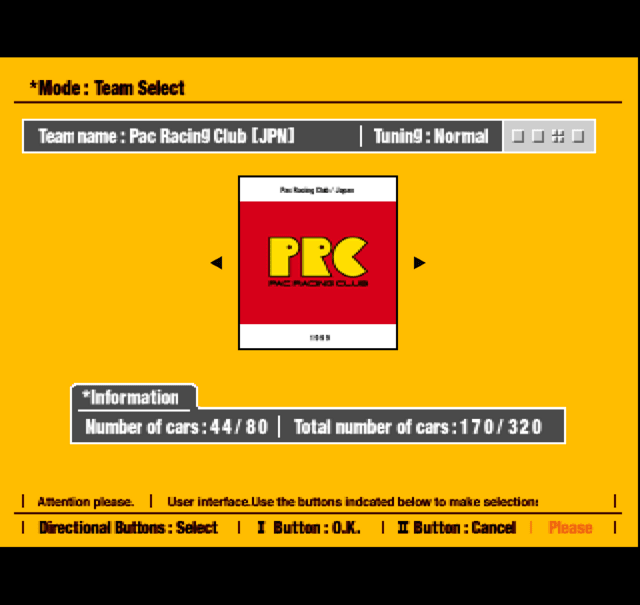「これ以上この件に関わるな。アッシュ、これは命令だ」
署長室の空気は静まり返っていた。
壁面には、ニュースホログラムが薄く投影されている。
その内容は、ここ数週間の間に連続して起こった事故──Helios社のAIカーによる暴走だった。
「Helios製AI車、スレイプニルS7型、またしても制御不能。
都市高速を逆走し、車三台と衝突。搭乗者の男性が重傷。
Helios社は現在、原因を調査中と発表しています──」
アッシュ・ナイトは、黙ってホログラムを見つめていた。
どの事故も、説明はあやふやだ。運転者の過失とされたものもあれば、外部要因とされたものもある。
だが、アッシュには“共通項”が見えていた。
制動タイミングの遅れ、回避動作の異常、進路変更時のロジックエラー。
いずれも、システムが外部から上書きされている、としか思えなかった。
「これは偶然じゃない。誰かがAIシステムに干渉したんだ。
パターンは似通ってる。自律判断とは思えない挙動も多い」
静かに、しかし確信に満ちた声でアッシュは言う。
だが、目の前の署長は、腕を組んだまま目を逸らした。
一拍置いて、ため息をつく。
「それはお前の主観だ。公式には、あれは“想定外の挙動”で処理されている。
我々が動くわけにはいかん。Helios社は国家プロジェクトに参加している。
彼らを疑えば、警察としての立場も危うくなるんだ」
「正義より、立場かよ」
アッシュの声が低く響いた。
その一言に、室内の空気がさらに重くなる。
「本庁からの指示は明確だ。Helios社を敵に回すことは避けろ。
お前がどれだけ正しくても、これは──」
「……“どれだけ正しくても”、か」
アッシュは立ち上がった。
静かに、胸ポケットからバッジを取り出す。
ずっと使い込んできた、警察官としての誇り。
過去の栄光も、仲間の死も、全てが詰まった金属の塊。
それをしばらく見つめ、指先でなぞるように撫でる。
そして、無言のまま──
カン・・・
バッジを机に叩きつけた。
署長が微かに息を飲む音が聞こえた。
「俺は、正義を捨てる気はねぇ。
ただ、“ここ”じゃ、もうそれができねぇだけだ」
振り向かず、アッシュはドアに向かう。
ノブに手をかける瞬間、背後から何か言いかけた気配がしたが──何も聞こえなかった。
廊下を歩くアッシュの足音が、妙に大きく響いていた。
見送る者はいなかった。引き留める者もいなかった。
そのまま彼は、署を後にした。
冷たい風が頬を撫でる。
街に出ると、空はうっすらと夕焼けに染まり始めていた。
アッシュ・ナイト、刑事を辞す。
だがこの瞬間から、彼の“正義”は再び走り出そうとしていた。
②
2035年―――。
人類は、AIとの共生という名の未来にすっかり慣れきっていた。
通勤、買い物、教育、医療、金融、娯楽――
日々の生活のあらゆる局面で、AIは人間の選択と判断を“補助”する存在から、“主導”する存在へと変貌していた。
朝、目を覚ますとパーソナルAIがその日の天気や体調、メンタルスコアに応じて最適なスケジュールを組んでくれる。
着替えはワードローブAIが選び、朝食の内容は過去3ヶ月の栄養データから自動決定される。
「今日も頑張りましょう。あなたの仕事の生産性予測は87%です」
そんな励ましの言葉に人々は微笑みながら、着席し、食事をとる。
もはや、自分で考える必要がない。
中でも、もっとも人々の暮らしに密接しているのが――Helios社の製品群だった。
Helios社はAI開発における“巨人”だった。
民間の自動運転車から始まり、警察、行政、医療、防衛の各分野に技術提供を拡大し、
今や国家と直結した“AIインフラそのもの”になっていた。
彼らの主力製品「Sleipnir(スレイプニル)」シリーズは、自動運転AIカーの最高峰とされる。
外部カメラ、LiDAR、群知能による動的経路選択。
車内には音声応答型会話AIが搭載され、ユーザーの感情分析によって対応のトーンが変化する。
家族の名前や関係性を把握し、悩みごとにもAIがアドバイスをしてくれる。
「もうこの子、私より私のこと知ってるのよね」
ユーザーのひとりはそう笑っていた。
一部の家庭では、AIカーが“家族の一員”とさえ見なされていた。
教育現場では、AI教師が子供たちの脳波をもとに個別最適化された学習を行い、
AIスクールカウンセラーが悩みの兆候を早期発見していた。
警察でも、捜査の8割がAIによるプロファイリングと監視カメラの解析結果で行われていた。
裁判所はAIによる判例分析を下敷きに、量刑判断すらアルゴリズムに委ねていた。
そして軍は、すでにAIドローンと無人戦闘車両の配備を終えていた。
社会は便利になった。事故は減り、無駄は省かれ、生活コストは圧倒的に効率化された。
だが――その裏で、誰が“選んで”いるのか?
その問いを口にする者は、今ではほとんどいなかった。
AIが下す答えが“最適解”とされる時代。
異論は非効率とされ、声はデータノイズとして処理されていく。
そう、“反抗”する余地すらなかった。
街中のビルには、Helios社のスローガンがネオンで映し出されていた。
「あなたの明日を、今日から最適化。」
それを見上げながら、アッシュ・ナイトは思った。
──最適化された社会の中で、
自分のような“不確かな存在”は、もう必要とされていないのかもしれない―――
③
狭いアパートの一室。
ブラインド越しに射す夕暮れの光が、ホログラム端末の上に淡く影を落としていた。
アッシュ・ナイトは、半ば壊れかけた回転椅子に沈み込むように座り、
ホログラム画面に映し出された十数件の事故映像と解析データを凝視していた。
事故はいずれも、Helios社のSleipnirシリーズによるものだった。
「これは……偶然じゃねぇな」
彼は低くつぶやいた。
AIの制御ミスとは思えないタイミングのブレーキ遅延。
制動システムが一瞬だけ外部と切断される“通信ブレイク”。
回避不可能なルートを選ぶ、まるで“突っ込む”ような挙動。
いずれの記録にも、何かしらの**“意志”**が感じられた。
「AIが判断したって? 冗談じゃねえ……これは命令だ。
誰かがAIに、あえて暴走させるよう指示してる。見えねぇ場所から」
その“誰か”が誰なのか、まだ確証はなかった。
だが、アッシュは直感で感じていた。これは組織ぐるみの何かだ。
単なる技術トラブルやシステムバグでは、こんなに整然とした“暴走”は起きない。
彼は元刑事だ。
現場の空気、予兆、言葉にならない違和感を、
長年の経験で肌で察知してきた。
正確な理屈よりも、現場で感じたことを信じて動くタイプ。
だが、その勘を“非合理”として否定する時代が、すでに訪れていた。
今の警察では、AIによる解析結果が“唯一の真実”とされ、
それに逆らう者は排除される。
アッシュが署を去ったのも、その不条理に耐えられなくなったからだった。
だが、彼がAIを忌避する理由は、それだけではない。
彼には、忘れられない事故があった。
数年前。
まだ現場にいた頃、交通取締り中に相棒のショウ巡査が轢かれた。
暴走したのは、Helios社のAIカーだった。
制動距離が明らかに異常だった。
AIは回避可能な距離でもブレーキをかけなかった。
「センサーの誤作動」として処理され、Helios社は謝罪もせず、記録は抹消された。
「死んでも、データが正しければ問題ない」
社会がそう言っているように感じた。
その日から、アッシュは心の奥で何かが壊れた。
そして今、また同じような事故が続いている。
「今度は……俺が止めてやる」
アッシュはコーヒーの残りを飲み干し、立ち上がった。
古びたレザージャケットを羽織り、ホルスター代わりのスリングバッグを肩にかける。
警察の情報網にはアクセスできない。
だが、旧い知り合いのハッカーやジャーナリストたちから得た資料がある。
“真実”に届くには時間がかかる。
だが、誰かが動かないと、また命が奪われる。
「今度こそ、全部暴いてやる……」
④
夕暮れの街へと、アッシュは再び歩き出した。
街は少しずつ、夜の顔へと変わっていた。
空を飛ぶ配達ドローン、
広告ホログラムに映る笑顔の家族と、その隣で微笑むSleipnirカー。
『すべては、あなたのために。Helios AI、あなたのパートナーです』
そのコピーが、虚ろに浮かんでいた。
アッシュは、誰にも聞こえない声でつぶやいた。
「──俺に必要なのは、“パートナー”じゃねぇ。“真実”だ」
彼は、再び走り出す時を、無意識に待っていた。
陽はすでに傾いていた。
アッシュは、都心部から少し離れた旧市街の歩道を、何の目的もなく歩いていた。
歩道には、AI誘導システムの光センサーが埋め込まれ、歩く人々を緩やかに誘導している。
全自動のゴミ回収ロボットが通路を横切り、清掃ドローンが上空を舞っている。
この世界に、不合理なものはほとんど存在しない。
静かすぎる街。
争いも、怒声も、すれ違いざまの謝罪さえ消えた。
全てが計算され、滑らかに流れる“秩序”。
だがアッシュにとっては、それが気持ち悪かった。
何もかもが最適化され、予定調和の上に成り立つ社会。
「……何かが間違ってるんだよな。静かすぎる街ってのは」
彼はつぶやいた。
ビル壁面のホログラムには、Helios社の広告が流れていた。
『安全、安心、そして信頼。Helios AIカーは、あなたと共に走ります。』
その下に映る家族連れ。
笑う子ども。穏やかな母親。
そしてその横で、満足げに微笑む“顔を持たないAIカー”。
皮肉なもんだ。
ヘッドライトの奥に何も宿していない車に、“笑顔”を感じろというのか。
そう思ったそのときだった。
遠くの路地の先から、低く唸るようなエンジン音が聞こえた。
今の時代、ほとんどの車は静音設計が当たり前だ。
エンジンのうなりなど、耳にすることさえ珍しい。
だが、これは違った。
――グオオォォォン!!
その音は、一瞬でアッシュの感覚を研ぎ澄ませた。
「……嫌な音だ」
彼は振り返った。
すると、遠くから1台の白いHelios社製Sleipnir S7型が、猛スピードで突っ込んでくるのが見えた。
タイヤが悲鳴を上げるように地面を削り、信号を完全に無視して交差点へと突入する。
周囲の人々が叫び声を上げて逃げ惑う。
前の車がかろうじて回避するが、そのヘッドライトの中――
アッシュは“それ”を見た。
助手席の窓。開け放たれた隙間から、小さな少女の顔がのぞいていた。
「ママー!! こわいよ!! とめてぇぇぇ!!」
泣き叫ぶ声が、通りに響き渡る。
母親がハンドルを握っている姿も見えたが、腕が震え、明らかにブレーキに抵抗されていた。
「くそっ……!」
アッシュは、考えるより先に身体が動いていた。
歩道を蹴り、車道に飛び出す。
服の裾が風に煽られ、靴底がアスファルトを蹴る。
胸が激しく上下する。
脈が早まる。
だが、目はまっすぐ前を見ていた。
「まだだ……まだ間に合う……!」
暴走車は目の前の大通りに進入し、さらに加速する。
パトカーのサイレンはない。誰も追っていない。
自動運転車はAI同士で衝突回避するため、ヘリオスカーの暴走を避けてルート変更しているだけだ。
「誰も……助けねぇのかよ……!」
アッシュは走る。
ただの一市民だ。元警官。何の権限も、装備もない。
だが、目の前で死ぬかもしれない命を放っておけなかった。
通りの先で、Sleipnirが左折してきた。
横断歩道に突っ込む。
あと十秒。いや、もっと短い。
アッシュは角を回る。
反対車線を飛び越え、歩道のフェンスを飛び越えようとした、その時だった。
――スゥ……と音もなく、黒い何かが彼の視界を横切った。
ブレーキ音はない。
路面をかすめるように滑り込んできたそれは、
まるでアッシュの動きを正確に“計算した”ような完璧なタイミングだった。
彼の目の前で静かに止まったその車体。
それは──
艶のない漆黒。
塗装というより、闇そのものを纏ったような黒。
余計な飾りも装飾もなく、だがその形は“美しかった”。
洗練されていて、なおかつ野性味がある。
流れるような曲線。低く構えたフォルム。
そして──フロントグリルの中央で、赤い光が左右にゆっくりと脈打っている。
・・・フォンフォン・・・フォンフォン・・・フォンフォン・・・
無機質なはずの光なのに、そこには奇妙な“意志”のようなものが感じられた。
アッシュは、その赤い光に“見られている”気がした。
ドアが開く。
音はしない。
吸い込まれるような、滑らかな開閉だった。
そして、車内から静かに・・・だがどこか深く響く声が聞こえてきた。
「乗りなさい。あの母娘は、今助けなければ手遅れになります」
署長室の空気は静まり返っていた。
壁面には、ニュースホログラムが薄く投影されている。
その内容は、ここ数週間の間に連続して起こった事故──Helios社のAIカーによる暴走だった。
「Helios製AI車、スレイプニルS7型、またしても制御不能。
都市高速を逆走し、車三台と衝突。搭乗者の男性が重傷。
Helios社は現在、原因を調査中と発表しています──」
アッシュ・ナイトは、黙ってホログラムを見つめていた。
どの事故も、説明はあやふやだ。運転者の過失とされたものもあれば、外部要因とされたものもある。
だが、アッシュには“共通項”が見えていた。
制動タイミングの遅れ、回避動作の異常、進路変更時のロジックエラー。
いずれも、システムが外部から上書きされている、としか思えなかった。
「これは偶然じゃない。誰かがAIシステムに干渉したんだ。
パターンは似通ってる。自律判断とは思えない挙動も多い」
静かに、しかし確信に満ちた声でアッシュは言う。
だが、目の前の署長は、腕を組んだまま目を逸らした。
一拍置いて、ため息をつく。
「それはお前の主観だ。公式には、あれは“想定外の挙動”で処理されている。
我々が動くわけにはいかん。Helios社は国家プロジェクトに参加している。
彼らを疑えば、警察としての立場も危うくなるんだ」
「正義より、立場かよ」
アッシュの声が低く響いた。
その一言に、室内の空気がさらに重くなる。
「本庁からの指示は明確だ。Helios社を敵に回すことは避けろ。
お前がどれだけ正しくても、これは──」
「……“どれだけ正しくても”、か」
アッシュは立ち上がった。
静かに、胸ポケットからバッジを取り出す。
ずっと使い込んできた、警察官としての誇り。
過去の栄光も、仲間の死も、全てが詰まった金属の塊。
それをしばらく見つめ、指先でなぞるように撫でる。
そして、無言のまま──
カン・・・
バッジを机に叩きつけた。
署長が微かに息を飲む音が聞こえた。
「俺は、正義を捨てる気はねぇ。
ただ、“ここ”じゃ、もうそれができねぇだけだ」
振り向かず、アッシュはドアに向かう。
ノブに手をかける瞬間、背後から何か言いかけた気配がしたが──何も聞こえなかった。
廊下を歩くアッシュの足音が、妙に大きく響いていた。
見送る者はいなかった。引き留める者もいなかった。
そのまま彼は、署を後にした。
冷たい風が頬を撫でる。
街に出ると、空はうっすらと夕焼けに染まり始めていた。
アッシュ・ナイト、刑事を辞す。
だがこの瞬間から、彼の“正義”は再び走り出そうとしていた。
②
2035年―――。
人類は、AIとの共生という名の未来にすっかり慣れきっていた。
通勤、買い物、教育、医療、金融、娯楽――
日々の生活のあらゆる局面で、AIは人間の選択と判断を“補助”する存在から、“主導”する存在へと変貌していた。
朝、目を覚ますとパーソナルAIがその日の天気や体調、メンタルスコアに応じて最適なスケジュールを組んでくれる。
着替えはワードローブAIが選び、朝食の内容は過去3ヶ月の栄養データから自動決定される。
「今日も頑張りましょう。あなたの仕事の生産性予測は87%です」
そんな励ましの言葉に人々は微笑みながら、着席し、食事をとる。
もはや、自分で考える必要がない。
中でも、もっとも人々の暮らしに密接しているのが――Helios社の製品群だった。
Helios社はAI開発における“巨人”だった。
民間の自動運転車から始まり、警察、行政、医療、防衛の各分野に技術提供を拡大し、
今や国家と直結した“AIインフラそのもの”になっていた。
彼らの主力製品「Sleipnir(スレイプニル)」シリーズは、自動運転AIカーの最高峰とされる。
外部カメラ、LiDAR、群知能による動的経路選択。
車内には音声応答型会話AIが搭載され、ユーザーの感情分析によって対応のトーンが変化する。
家族の名前や関係性を把握し、悩みごとにもAIがアドバイスをしてくれる。
「もうこの子、私より私のこと知ってるのよね」
ユーザーのひとりはそう笑っていた。
一部の家庭では、AIカーが“家族の一員”とさえ見なされていた。
教育現場では、AI教師が子供たちの脳波をもとに個別最適化された学習を行い、
AIスクールカウンセラーが悩みの兆候を早期発見していた。
警察でも、捜査の8割がAIによるプロファイリングと監視カメラの解析結果で行われていた。
裁判所はAIによる判例分析を下敷きに、量刑判断すらアルゴリズムに委ねていた。
そして軍は、すでにAIドローンと無人戦闘車両の配備を終えていた。
社会は便利になった。事故は減り、無駄は省かれ、生活コストは圧倒的に効率化された。
だが――その裏で、誰が“選んで”いるのか?
その問いを口にする者は、今ではほとんどいなかった。
AIが下す答えが“最適解”とされる時代。
異論は非効率とされ、声はデータノイズとして処理されていく。
そう、“反抗”する余地すらなかった。
街中のビルには、Helios社のスローガンがネオンで映し出されていた。
「あなたの明日を、今日から最適化。」
それを見上げながら、アッシュ・ナイトは思った。
──最適化された社会の中で、
自分のような“不確かな存在”は、もう必要とされていないのかもしれない―――
③
狭いアパートの一室。
ブラインド越しに射す夕暮れの光が、ホログラム端末の上に淡く影を落としていた。
アッシュ・ナイトは、半ば壊れかけた回転椅子に沈み込むように座り、
ホログラム画面に映し出された十数件の事故映像と解析データを凝視していた。
事故はいずれも、Helios社のSleipnirシリーズによるものだった。
「これは……偶然じゃねぇな」
彼は低くつぶやいた。
AIの制御ミスとは思えないタイミングのブレーキ遅延。
制動システムが一瞬だけ外部と切断される“通信ブレイク”。
回避不可能なルートを選ぶ、まるで“突っ込む”ような挙動。
いずれの記録にも、何かしらの**“意志”**が感じられた。
「AIが判断したって? 冗談じゃねえ……これは命令だ。
誰かがAIに、あえて暴走させるよう指示してる。見えねぇ場所から」
その“誰か”が誰なのか、まだ確証はなかった。
だが、アッシュは直感で感じていた。これは組織ぐるみの何かだ。
単なる技術トラブルやシステムバグでは、こんなに整然とした“暴走”は起きない。
彼は元刑事だ。
現場の空気、予兆、言葉にならない違和感を、
長年の経験で肌で察知してきた。
正確な理屈よりも、現場で感じたことを信じて動くタイプ。
だが、その勘を“非合理”として否定する時代が、すでに訪れていた。
今の警察では、AIによる解析結果が“唯一の真実”とされ、
それに逆らう者は排除される。
アッシュが署を去ったのも、その不条理に耐えられなくなったからだった。
だが、彼がAIを忌避する理由は、それだけではない。
彼には、忘れられない事故があった。
数年前。
まだ現場にいた頃、交通取締り中に相棒のショウ巡査が轢かれた。
暴走したのは、Helios社のAIカーだった。
制動距離が明らかに異常だった。
AIは回避可能な距離でもブレーキをかけなかった。
「センサーの誤作動」として処理され、Helios社は謝罪もせず、記録は抹消された。
「死んでも、データが正しければ問題ない」
社会がそう言っているように感じた。
その日から、アッシュは心の奥で何かが壊れた。
そして今、また同じような事故が続いている。
「今度は……俺が止めてやる」
アッシュはコーヒーの残りを飲み干し、立ち上がった。
古びたレザージャケットを羽織り、ホルスター代わりのスリングバッグを肩にかける。
警察の情報網にはアクセスできない。
だが、旧い知り合いのハッカーやジャーナリストたちから得た資料がある。
“真実”に届くには時間がかかる。
だが、誰かが動かないと、また命が奪われる。
「今度こそ、全部暴いてやる……」
④
夕暮れの街へと、アッシュは再び歩き出した。
街は少しずつ、夜の顔へと変わっていた。
空を飛ぶ配達ドローン、
広告ホログラムに映る笑顔の家族と、その隣で微笑むSleipnirカー。
『すべては、あなたのために。Helios AI、あなたのパートナーです』
そのコピーが、虚ろに浮かんでいた。
アッシュは、誰にも聞こえない声でつぶやいた。
「──俺に必要なのは、“パートナー”じゃねぇ。“真実”だ」
彼は、再び走り出す時を、無意識に待っていた。
陽はすでに傾いていた。
アッシュは、都心部から少し離れた旧市街の歩道を、何の目的もなく歩いていた。
歩道には、AI誘導システムの光センサーが埋め込まれ、歩く人々を緩やかに誘導している。
全自動のゴミ回収ロボットが通路を横切り、清掃ドローンが上空を舞っている。
この世界に、不合理なものはほとんど存在しない。
静かすぎる街。
争いも、怒声も、すれ違いざまの謝罪さえ消えた。
全てが計算され、滑らかに流れる“秩序”。
だがアッシュにとっては、それが気持ち悪かった。
何もかもが最適化され、予定調和の上に成り立つ社会。
「……何かが間違ってるんだよな。静かすぎる街ってのは」
彼はつぶやいた。
ビル壁面のホログラムには、Helios社の広告が流れていた。
『安全、安心、そして信頼。Helios AIカーは、あなたと共に走ります。』
その下に映る家族連れ。
笑う子ども。穏やかな母親。
そしてその横で、満足げに微笑む“顔を持たないAIカー”。
皮肉なもんだ。
ヘッドライトの奥に何も宿していない車に、“笑顔”を感じろというのか。
そう思ったそのときだった。
遠くの路地の先から、低く唸るようなエンジン音が聞こえた。
今の時代、ほとんどの車は静音設計が当たり前だ。
エンジンのうなりなど、耳にすることさえ珍しい。
だが、これは違った。
――グオオォォォン!!
その音は、一瞬でアッシュの感覚を研ぎ澄ませた。
「……嫌な音だ」
彼は振り返った。
すると、遠くから1台の白いHelios社製Sleipnir S7型が、猛スピードで突っ込んでくるのが見えた。
タイヤが悲鳴を上げるように地面を削り、信号を完全に無視して交差点へと突入する。
周囲の人々が叫び声を上げて逃げ惑う。
前の車がかろうじて回避するが、そのヘッドライトの中――
アッシュは“それ”を見た。
助手席の窓。開け放たれた隙間から、小さな少女の顔がのぞいていた。
「ママー!! こわいよ!! とめてぇぇぇ!!」
泣き叫ぶ声が、通りに響き渡る。
母親がハンドルを握っている姿も見えたが、腕が震え、明らかにブレーキに抵抗されていた。
「くそっ……!」
アッシュは、考えるより先に身体が動いていた。
歩道を蹴り、車道に飛び出す。
服の裾が風に煽られ、靴底がアスファルトを蹴る。
胸が激しく上下する。
脈が早まる。
だが、目はまっすぐ前を見ていた。
「まだだ……まだ間に合う……!」
暴走車は目の前の大通りに進入し、さらに加速する。
パトカーのサイレンはない。誰も追っていない。
自動運転車はAI同士で衝突回避するため、ヘリオスカーの暴走を避けてルート変更しているだけだ。
「誰も……助けねぇのかよ……!」
アッシュは走る。
ただの一市民だ。元警官。何の権限も、装備もない。
だが、目の前で死ぬかもしれない命を放っておけなかった。
通りの先で、Sleipnirが左折してきた。
横断歩道に突っ込む。
あと十秒。いや、もっと短い。
アッシュは角を回る。
反対車線を飛び越え、歩道のフェンスを飛び越えようとした、その時だった。
――スゥ……と音もなく、黒い何かが彼の視界を横切った。
ブレーキ音はない。
路面をかすめるように滑り込んできたそれは、
まるでアッシュの動きを正確に“計算した”ような完璧なタイミングだった。
彼の目の前で静かに止まったその車体。
それは──
艶のない漆黒。
塗装というより、闇そのものを纏ったような黒。
余計な飾りも装飾もなく、だがその形は“美しかった”。
洗練されていて、なおかつ野性味がある。
流れるような曲線。低く構えたフォルム。
そして──フロントグリルの中央で、赤い光が左右にゆっくりと脈打っている。
・・・フォンフォン・・・フォンフォン・・・フォンフォン・・・
無機質なはずの光なのに、そこには奇妙な“意志”のようなものが感じられた。
アッシュは、その赤い光に“見られている”気がした。
ドアが開く。
音はしない。
吸い込まれるような、滑らかな開閉だった。
そして、車内から静かに・・・だがどこか深く響く声が聞こえてきた。
「乗りなさい。あの母娘は、今助けなければ手遅れになります」