内田樹氏の「街場の読書論」を読む。
相変わらず、目から鱗がポロポロ落ちて目の前の霧が晴れ、視界が広がってゆく独特の感覚がある。大変心地よい。
内田氏いわく“疾走する文体”なるものがあるという。
“すぐれた作家は一行目から「ぐい」と読者の襟首をつかんで、一気に物語内的世界に拉致し去る「力業」を使”い“一行目でいきなり書き手がもう耳元にいる”という。
内田樹推薦の疾走する文体の決定版はこれである。
撰ばれてあることの
恍惚と不安と
二つわれにあり ヴェルレエヌ
死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織り込まれていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。
ノラもまた考えた。廊下へ出てうしろの扉をぱたんとしめたときに考えた。帰ろうかしら。
太宰治の「晩年」の冒頭部分である。
この部分は小説の「イントロ」としては近代文学史の達成の一つであろうと内田氏は書く。
納得である。
しかし、かくいう内田氏の文体自体がとにかく疾走感がある。
ご本人は謙遜されるかもしれないが、十分太宰とタメを張れると思うのは僕だけだろうか?
その他、お得意のラカン、レヴィナス、マルクス、そして福沢諭吉、はては高橋源一郎、大瀧詠一にいたるまで、まさに古今東西の作家(?)を縦横無尽に読み倒してゆく。
この疾走感と知的興奮を味わいたい方は是非!
相変わらず、目から鱗がポロポロ落ちて目の前の霧が晴れ、視界が広がってゆく独特の感覚がある。大変心地よい。
内田氏いわく“疾走する文体”なるものがあるという。
“すぐれた作家は一行目から「ぐい」と読者の襟首をつかんで、一気に物語内的世界に拉致し去る「力業」を使”い“一行目でいきなり書き手がもう耳元にいる”という。
内田樹推薦の疾走する文体の決定版はこれである。
撰ばれてあることの
恍惚と不安と
二つわれにあり ヴェルレエヌ
死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織り込まれていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。
ノラもまた考えた。廊下へ出てうしろの扉をぱたんとしめたときに考えた。帰ろうかしら。
太宰治の「晩年」の冒頭部分である。
この部分は小説の「イントロ」としては近代文学史の達成の一つであろうと内田氏は書く。
納得である。
しかし、かくいう内田氏の文体自体がとにかく疾走感がある。
ご本人は謙遜されるかもしれないが、十分太宰とタメを張れると思うのは僕だけだろうか?
その他、お得意のラカン、レヴィナス、マルクス、そして福沢諭吉、はては高橋源一郎、大瀧詠一にいたるまで、まさに古今東西の作家(?)を縦横無尽に読み倒してゆく。
この疾走感と知的興奮を味わいたい方は是非!















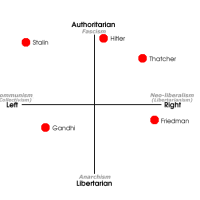
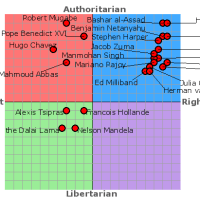
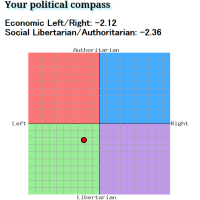
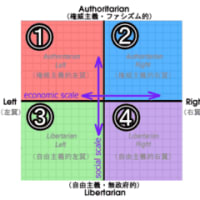






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます