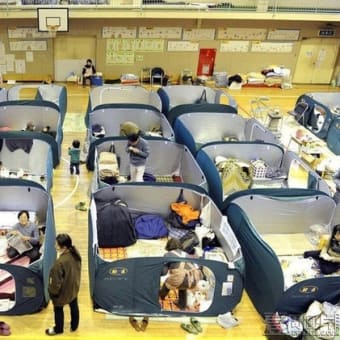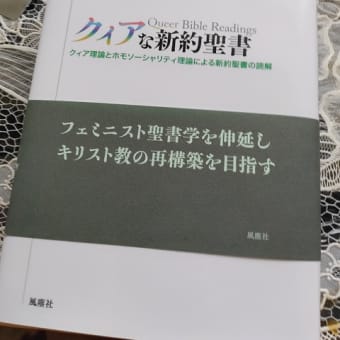経済学者で有名な大塚久雄のエッセイを読んでいた。彼は特にMウェーバーの研究者としても第一人者である。もう半世紀前の記述であるが、現在も同様というか、大塚が心配していたことがより進行してしまったと感じざるを得ない内容である。
少しばかり引用させてもらう。
「我々日本人はかつては『免れて恥なし」という生き方は恥ずべきことだということを知っておりました。法律にさえ引っかかなければ何をしてもよいというような人間は決して尊敬されておらなかったのであります。しかるに今や、その日本人の昔からのモラルさえどこかに消え失せてしまい、はては法論法を上手に駆使さえすれば、何をやってもよいのだと言わんばかりの雰囲気、そういう精神的雰囲気をわれわれはまざまざと経験しているわけです」(大塚久雄『生活の貧しさと心の貧しさ』みすず書房1978年P115)
この精神的雰囲気を「心の貧しさ」と大塚は指摘している。
「心の貧しさ」を日本人にもたらしたのは何だろうか。大塚は経済成長に伴う物質的豊かさが「世俗の論理」として信仰されていることを指摘する。そして、その背後に近代主義。かつ信仰の喪失。
「世俗の論理」は、大塚はウェーバーの責任倫理を介して理解する。簡略化するが、予測をしてその適切な手段を選択すること。目的合理的行為である。この論理が人々の無意識にまで浸透し、現象としては、経済重視、経済成長、効率的、利便性を重視する。今ならコスパ。
で大塚が信仰というのは、ウェーバーの心情倫理に繋がっている。どうも人間には、先の目的合理性には回収できない重要なというか、人間が人間たらしめられる価値意識がある。だから経済なんかよりもっと大切なものがなにがしかある、そういう心情のことで、ウェーバーは心情倫理を優先すべきとした。西欧だからキリスト教とか神とかから生じてくる価値意識なんだろうかとは思う。
で、日本に適応したら、どうなのか。現在の日本というのは、「法律にさえ引っかかなければ何をしてもよい」という空気になっていると思う。僕はこれを非社会性と呼んでいる。この非社会性には上位の価値が控えていて、少し単純化してしまうが、それが経済重視、経済合理性とか、簡単にいえば「金」である。
「法律にさえ引っかかなければ何をしてもよい」は結局儲かればいいということになる。そうすると、それが具体的になんであるのかは簡単に位置付けられないが、誠実さや尊厳という心情倫理になるものを排除する。
「そんなもの金になるか」とでも。日本社会には、そういう人物があたかも論客というかメディアの中心人物になったりだとか、政治家になったりしているように思う。そこには、彼らが気づかぬ「心の貧しさ」がある。
なんか大切なものがあるという感覚、ウェーバーでいえば心情倫理は存在していると思うというか、信じることにする。