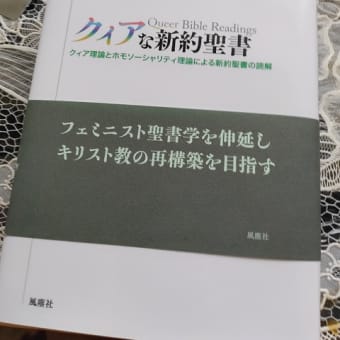最近感じていることだが、世の中が確実なものを求めすぎて、結局のところ、窮屈になっているのではないかと。もう少し、おおらかでいいのではないか、そんなことばかり考えている。
ちょうどテレビで就活を取り上げていた。就活生と企業がマッチングするように、いろいろな手だてがなされているようだ。両者ともに、いい就職を、いい人材確保をと頑張っている。僕自身、大学生の就活とは無関係ではないのだが、あのような時間と労力が本当に必要なのだろうかと疑問に思っている。AIの発達あたりは「あなたに合った職業は・・・です」とでも最適解というやつを出すようになり、それに合わせて行動するようにでもなるのかもしれない。
世の中の役に立つとはいうけれど、僕たちが気づかないところで、役に立っているということがあるはずである。じつは役に立っていないように見えて、僕たち有限な人間が気づかない水準で、役に立つということもあるのではないだろうか。
世の中の役に立たないという見立てから起きた事件として、すぐに思い浮かぶのは3年前の相模原の障害者施設での殺傷事件である。この事件を扱った辺見庸『月』は考えさせられる本であったが、この本については、いつか取り上げたいとも思う。
障害者は役に立たないだろうか。時に次のような話を聞いたことがるのではないかと思う。
口も利けない障害者が亡くなってしまってのち、その遺族が障害者の世話をしているうちに、いつの間にか障害者を中心として家族の意味を理解したり、友人の大切さを知ったといった感想である。悲嘆研究なんかでは、よくあることだと思う。
このような思いを家族や仲間に抱かせたのが亡くなった障害者であるわけだから、役に立たないなんて言えるわけがない。そもそも「役に立つ」という少しばかり功利主義的な匂いのする概念では言い尽くせない意味が含まれている。
次に僕の経験を少しばかり。
もう随分と昔だが、派遣で病院の当直事務をしていたことがある。当然事務なわけだから、事務処理能力や接遇などが問われるわけである。つまり、この仕事で役に立つというのはそういう能力ということになる。
ところが、全然事務処理能力のない人物がいた。Aとしておこう。普通に3件処理できるところが、Aはやっと1件という程度である。ついで業務の理解も薄い。そういう意味では、役に立たない人物である。ただ責める者は少なかった。全部で15人程度のスタッフがシフトで交代しつつ勤務するのだが、1人だけAを見下している者がいただけである。ちなみに彼は大学院生で、先の基準でいえば、役に立つ人間である。Bとしておこう。
僕はリーダー役だったので、シフトを作らなければならない。各自事情があるので、ある程度希望を聞いて、シフトを組むのである。そこで生じた問題はBとは一緒に働きたくないという希望が数人出ることである。業務は結構忙しい。Bはテキパキこなすので、彼と組んだ方が、全体として処理速度は早くなるし、楽なはずなのだが。Aに対しては、B以外は誰も文句をいう者はいない。一緒に働きたくないなどとは言わないのである。
こういう問題は多かれ少なかれ集団であれば生じることではある。気にもせず、シフトを決めていたのだけれど、ある時、気づかされることがあった。
Aと一緒の勤務の時は職場がなんとなくふんわりしていて、心地いいのである。ところがAがいない時にはこの雰囲気はあまり感じられない。先に触れた通り、Aは仕事はできない。そのことはみんな理解している。そうすると、みんなでフォローしているのである。そして、このフォローをしながら対応した結果、ミスも少ないのである。自然発生的に協力関係ができていて、そのことを誰も損得で判断しないどころか、業務全般を見た場合、業務が向上さえしている。
Bが勤務の時は雰囲気が悪いし、自分の仕事だけやってればいいだろうという意識に支配されていたと思う。
Aこそが職場の雰囲気を作り出していたわけだ。彼がいたからこそ、いい職場になっていたのである。彼こそが役に立つ人物であった。当時たまたま僕が気づいたことだが、気づかずにその場に影響を与えていることがあるに違いないということを学ぶことができた。学問的に集団の雰囲気を良くする要因はあげられるかもしれない。しかし、必ず抜け落ちることはある。学問的に取り上げられる要因はいいところ蓋然性に資することだし、人間が意識できる要因にすぎない。ついでに言えば。僕たちは全知全能ではない。
だから集団や社会に何が役に立つのかなんて、必ずわからない部分があり、分かっている要因の意味を変える可能性さえあるわけだ。先のBは仕事はできたが、彼とは仕事をしたくない者が現れるわけだから、役に立つとは何なのか良くわからない部分が生じてくる。
だから就活で一生決まるとか、企業の勝負所だといって、すごい力を入れていることが正しいとは言い難い。もう少し、肩の力を抜いた就活でもいいんじゃないかと思う次第である。