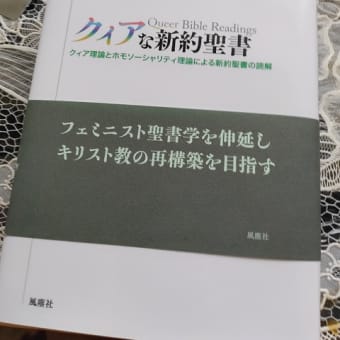『如懿伝』の最後、主人公の皇后・如懿が亡くなるシーンを振り返ってみる。
如懿は宮廷の争いで亡くなっていった多くの人を思い返す。悪事を働いた人でさえ、「生きていたなら・・」と思い返すのである。
愛し合っていた乾隆帝との間の愛情もなくなってしまったことも、自然なことであると言う。男女の愛がなくなることも自然なことであるとは、人間は自然のひとつであることを自覚することだが、そこには哀感が漂う。
常に彼女の傍には芽も出ない枯れた紅梅がある。彼女は長らくこの紅梅の世話をしているが、彼女が亡くなるときに芽は出なかった。ただ時が経って乾隆帝が崩御するとき、その傍で芽を吹いている。
紅梅という自然と人間がなぜか重ねられてしまうのだが、我々の心にある必然的表現であると思う。
如懿は侍女の容珮にお茶を勧める。おそらくは身分の違いから、一緒にお茶を飲むこと自体あり得ないことなのではないかと思うが、如懿はそんなこと気にすることもなく思い出を語る。新しいお茶を取りに行っている間に、如懿は椅子に座ったまま安らかに逝ってしまう。椅子には我が子への遺書が置いてあった。
本当に素晴らしいシーンであった。人が亡くなることが自然のように描かれているからだ。そして、その死の訪れを如懿は知っているかのようであった。容珮との身分を超えた友情を愛(め)で、そして子供への遺書をそこに置いておく。全てが自然に流れている、そういう時間。
人間の死には哀感が伴う。当然のことである。人が死ねば悲しい。それだけだ。ただそれさえも自然である。そんなことが表現されてしまうシーンのように思えた。
前回にもあげたフィリップ・アリエスを拝借させてもらう。
死はそもそも自然であるから、中世、死を安らかに認め、準備をし、その時を穏やかに待ったという。人間は何千年もそのように生き、死んでいったのである。死を恐れるのは当然のように思うが、そうとばかりは言えないことがわかる。
ドラマで描かれる如懿の人生は、その副題「禁紫城に散る宿命の王妃」とされるように、宿命という言葉が持つ意味——望みが叶わない人生での哀しみや苦しみ——を体現するかのようである。
しかしながら、その人生への如懿の受容も死も自然なものとして描かれている。僕には、椅子で眠るような彼女を月が照らしているように思えた。