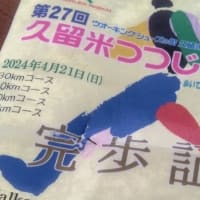1月とは思えない様な陽気が続く。
こんな日はチャリがいい。
折角だ。
どうせ行くなら車では寄り付きにくい、上陽の石橋群に行ってみようか。
上陽町には13もの石橋が点在している。
中でも、星野川添いに連続して続く、「ひ・ふ・み・よ橋」と呼ばれる四つの橋が有名だ。

スマホの目的地を、一番上流の洗玉橋に設定してと。
では出発だ。
後は、スマホの指示通りにペダルを漕ぐだけだ。
キコキコキコ
広川町の県道を漕いでいると、ポケットに入れたスマホから、
《ここから左が近道だよ~~ん》
とのメッセージが。
おや、そうかい。
気が利くねえ。
では、お言葉に従って、左に曲がるとするか。
キコキコキコ
4~5kmも進むと、気のせいだろうか。
だんだんとペダルが重くなってきた。

えーっと、これって・・・
所謂『山越え』っちゅうやつでないかい、スマホ君。
お気は確かですか。

漕げども漕げども、上り坂が終わらぬ。
ゼハー、ゼハー、ヒーーーー💦
こら、スマホッ!!
てめえこの野郎。
ちったあ、頭使えよ!
何でこんな道、教えるんだよ。

どうやらここがピークのようだ。
やっと登り切ったよ。
ブヒャー
えらい目に遭ったぜ。

山から降りてきた場所は、いきなり目的地の一つ寄口橋だ。
だがしかし、である。
冒頭でも書いたように、今回見て回るのは、数ある上陽石橋群の中でも、「ひ・ふ・み・よ橋」と総称して呼ばれる四つの橋なのだ。
名前からして順番がある事は、お分かりいただけるだろう。

寄口橋はなるべく見ないようにして、先ずは最初の目的地、洗玉橋へと急ぐ。

あれかな?

「ひ」 一つ目橋こと洗玉橋だ。
棟梁は有名な肥後の石工橋本勘五郎。
熊本の国指定重要文化財である通潤橋や、東京の万世橋や浅草橋などを手がけた名匠だ。
欄干も往時の姿をそのまま残している。

現在も、県道に架けられた橋の歩道橋として利用されている。


『明治二十六年五月三日竣功』とある。
「竣工」ではなく「竣功」。
現在ではあまり見ないが、当時は神社仏閣や古い橋などは、この字を当てる事もあったようだ。

上流側。
要石部に何やら赤い文字が見える。

説明板によると、
『肥後上益城矢部吹上兄弟橋 、八代種山棟梁 橋本勘五郎、倅 源平、 孫 為八』と、刻まれているとの事。
下流へ移動する。

「ふ」 二つ目橋寄口橋だ。
先程山から降りてきた際、見なかった事にして通り過ぎた橋である。
八女の石工山下佐太郎、上陽の大工小川弥四郎により、大正9年に架けられた。

驚くべきことに、車道として現在も使われる現役の橋なのだ。

現代人である我々は、先人達の技術の確かさに、思いを致さねばならぬ。
何たって、バスだって通れちゃうんだから。
更に下流へ下る。

「み」 三つ目橋こと大瀬(だいぜ)橋。
下流に下ってくる度に、ひとつづつ目が増えてくるのが面白い。
石橋であるのは上流側に架かる橋で、画像向かって右側がそうである。
無論この橋も、現役の車道として活用されている。

この画像を見ればよくわかるかな。
手前が石橋で、奥の方が後に作られた鉄筋コンクリート製である。

大正6年架設。

荻本卯作、川口竹次郎など、建築に携わった大工、石工達の名前が、アーチの頂上に刻まれているとの事。
最後の橋は、

当然「よ」 四ツ目橋となる。
宮ケ原橋。

こちらは道幅も狭く、歩道橋として使われている。
大正11年に豊島虎次郎により建築された。

星野川は、御多分に漏れず、何度も洪水を繰り返してきた河川である。
にもかかわらず、どの橋もびくともしていない。

大事に保存され、地域住民の重要な生活道路として、今も現役で頑張っている。

大したもんである。
季節になれば、これらの石橋のたもとには、蛍が乱舞する姿が見られるらしい。
また行きたい場所が増えてしまった。
では帰るとするか。
言っておくがスマホよ。
下手な口出しは無用だからな。