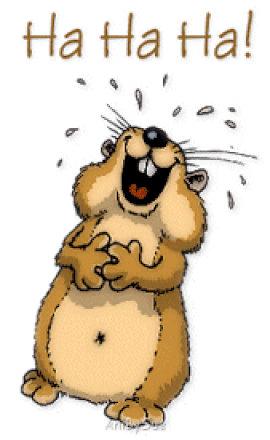~ 今は昔、上野の茂林寺に守鶴という老僧あり ~
『茂林寺の文福茶釜』
(もりんじ の ぶんぶくちゃがま)

大蘇芳年筆
『甲子夜話』
元亀元年(1570)七世月舟禅師の代に茂林寺で千人法会が催された際
大勢の来客を賄う湯釜が必要となりました
その時、守鶴は一夜のうちに、どこからか一つの茶釜を持ってきて
茶堂に備えました。ところが、この茶釜は不思議なことに
いくら湯を汲んでも尽きることがありませんでした。
殊にこの茶釜は八つの功徳があり、中でも福を分け与えるゆへに
守鶴はこの茶釜を「紫金銅分福茶釜」と名付け
この茶釜のお茶を飲むと八つ功徳に授かると言いました。
それからしばらく経ったある日、守鶴は熟睡していて手足に毛が生え
尾が付いた狢(むじな)の正体を現わしてしまいます
実は、守鶴の正体は数千年生き続けた狢だったのです。
これ以上、当寺にはいられないと悟った守鶴は、名残を惜しみ
人々に源平屋島の合戦と釈迦の説法の二場面を再現して見せます
人々が感涙にむせぶ中、守鶴は狢の姿となり飛び去りました。
時は天正十五年(1587)二月二十八日
出典元:ArtWiki