
日本の小惑星探査機「はやぶさ」が今年6月13日に地球に持ち帰ったカプセルの中に含まれていた微粒子を分析した結果小惑星イトカワ由来の物質が含まれていることがほぼ確実になりました。
2005年11月、小惑星探査機「はやぶさ」は小惑星イトカワの地表への着地と地表からのサンプル回収に挑みました。その様子は、当サイトでも生中継しました。世界中の期待が集まる中行われた1回目は降下の途中でセンサーが異常を検知し自動的に着地を中止したものの、姿勢制御不能となり、最終的にイトカワの地表に予定外の着陸を果たしました。再び行われた第2回の着地の際には予定通りの着地を果たしたものの、本来表面の物質を弾き飛ばしてかけらを回収するはずでしたが、弾丸は発射されませんでした。ただし、弾丸は発射されなくても、着地の衝撃で弾き飛ばされたかけらを回収できた可能性がありました。その後長い旅路をへて今年の6月にカプセルを地球まで持ち帰ることに成功しました。
カプセルの中には、1回目の着地時に使用されたB室と、2回目に使用されたA室があり、最初にA室内の分析が行われました。中には微粒子が発見されたものの、数~数十ミクロンと極めて小さいものばかりでした。あまりに小さいため、回収にも時間がかかりましたが、特殊なヘラを使って回収した結果、多数の微粒子が確認され、電子顕微鏡による分析が行われました。

カプセル内からそげ落ちた物質や、打ち上げ前もしくは回収後に混入した地球上の物質が混入している可能性も十分にあったため、スプリング8等の施設での本格的な分析が行われるまでは、イトカワ由来の物質が含まれているかどうかの結論は出ないだろうと思われていました。
電子顕微鏡での詳しい分析の結果、カプセル内に岩石質の微粒子が多数含まれていることが分かり、その数は1500個にも及びました。カンラン石が最も多く、その他輝石、斜長石、硫化物等の鉱物が発見され、その一方で地球上に多い火山岩の成分である玄武岩、安山岩、デイサイト等は含まれていないことがわかりました。また、2005年に「はやぶさ」が赤外線を使って観測した結果、イトカワの地表にはカンラン石や輝石が多く含まれていることが既に判明しており、今回の微粒子の分析結果と一致しています。さらにこれらの鉱物中の鉄の含有率を調べた結果、カンラン石及び輝石中の鉄/(鉄+マグネシウム)の割合はそれぞれ30%、25%前後であり、これも地球のマントルでの割合(何れも5~15%程度)よりも有意に高く、「はやぶさ」の観測結果ともよく一致していました。「はやぶさ」は近赤外線分光器(NIRS)による赤外線スペクトルの観測や、蛍光X線スペクトロメータ(XRS)による蛍光X線(太陽からのX線によって励起された原子から発せられるX線)の観測によって、この値に近い値を得ています(下グラフ)。

一個一個の微粒子がイトカワ由来なのかどうかは詳しく調べないと分かりません。しかし、多くの微粒子を分析することで、イトカワに特徴的な組成であることが判明しました。発見された岩石質の微粒子のほとんどがイトカワ由来であろうという結論に達しました。
今後さらに詳しい分析が行われます。さらに、A室よりも多くのサンプルが含まれていると期待されているB室の分析も始まります。これからの注目は、「イトカワ由来かどうか」から「イトカワはどのような組成か」に移っていきます。小惑星の進化の歴史、さらには太陽系誕生の歴史に迫る画期的成果が期待されます。
2005年11月、小惑星探査機「はやぶさ」は小惑星イトカワの地表への着地と地表からのサンプル回収に挑みました。その様子は、当サイトでも生中継しました。世界中の期待が集まる中行われた1回目は降下の途中でセンサーが異常を検知し自動的に着地を中止したものの、姿勢制御不能となり、最終的にイトカワの地表に予定外の着陸を果たしました。再び行われた第2回の着地の際には予定通りの着地を果たしたものの、本来表面の物質を弾き飛ばしてかけらを回収するはずでしたが、弾丸は発射されませんでした。ただし、弾丸は発射されなくても、着地の衝撃で弾き飛ばされたかけらを回収できた可能性がありました。その後長い旅路をへて今年の6月にカプセルを地球まで持ち帰ることに成功しました。
カプセルの中には、1回目の着地時に使用されたB室と、2回目に使用されたA室があり、最初にA室内の分析が行われました。中には微粒子が発見されたものの、数~数十ミクロンと極めて小さいものばかりでした。あまりに小さいため、回収にも時間がかかりましたが、特殊なヘラを使って回収した結果、多数の微粒子が確認され、電子顕微鏡による分析が行われました。

カプセル内からそげ落ちた物質や、打ち上げ前もしくは回収後に混入した地球上の物質が混入している可能性も十分にあったため、スプリング8等の施設での本格的な分析が行われるまでは、イトカワ由来の物質が含まれているかどうかの結論は出ないだろうと思われていました。
電子顕微鏡での詳しい分析の結果、カプセル内に岩石質の微粒子が多数含まれていることが分かり、その数は1500個にも及びました。カンラン石が最も多く、その他輝石、斜長石、硫化物等の鉱物が発見され、その一方で地球上に多い火山岩の成分である玄武岩、安山岩、デイサイト等は含まれていないことがわかりました。また、2005年に「はやぶさ」が赤外線を使って観測した結果、イトカワの地表にはカンラン石や輝石が多く含まれていることが既に判明しており、今回の微粒子の分析結果と一致しています。さらにこれらの鉱物中の鉄の含有率を調べた結果、カンラン石及び輝石中の鉄/(鉄+マグネシウム)の割合はそれぞれ30%、25%前後であり、これも地球のマントルでの割合(何れも5~15%程度)よりも有意に高く、「はやぶさ」の観測結果ともよく一致していました。「はやぶさ」は近赤外線分光器(NIRS)による赤外線スペクトルの観測や、蛍光X線スペクトロメータ(XRS)による蛍光X線(太陽からのX線によって励起された原子から発せられるX線)の観測によって、この値に近い値を得ています(下グラフ)。

一個一個の微粒子がイトカワ由来なのかどうかは詳しく調べないと分かりません。しかし、多くの微粒子を分析することで、イトカワに特徴的な組成であることが判明しました。発見された岩石質の微粒子のほとんどがイトカワ由来であろうという結論に達しました。
今後さらに詳しい分析が行われます。さらに、A室よりも多くのサンプルが含まれていると期待されているB室の分析も始まります。これからの注目は、「イトカワ由来かどうか」から「イトカワはどのような組成か」に移っていきます。小惑星の進化の歴史、さらには太陽系誕生の歴史に迫る画期的成果が期待されます。











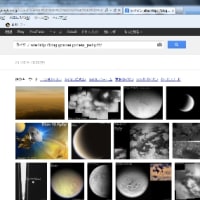
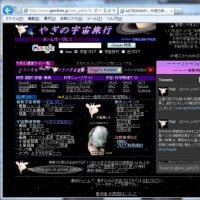


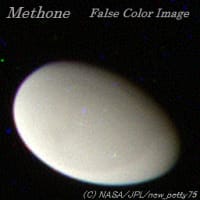
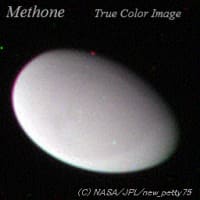



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます