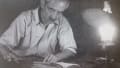新しい年のスタートにあたり、「新しい絃」を読み返してみました。
~1946年(今から70年前)の尾崎喜八の決意を示した自省の言葉~
戦時下のあのような極限状況のなかに自分がおかれたらどうなるか、
果たして後悔しないですむような生き方ができたろうか・・・
「新らしい絃」 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
森と山野と岩石との国に私は生きよう。
そこへ退いて私の絃(いと)を懸けなおし、
その国の荒い夜明けから完璧の夕べへと
広袤(こうぼう)をめぐるすべての音の
あたらしい秩序に私の歌をこころみるのだ。
なぜならば私はもう此処に
私を動かして歌わせる
顔も天空を持たないから。
歌はたましいの深い美しいおののきの調べだ。
それは愛と戦慄と自分の衝動への
抵抗なしには生まれない。
私は逆立つ藪や吹雪の地平に立ち向かおう、
強い爽かな低音を風のように弾きぬこう。
だがもしも早春の光が煦々(くく)として
純な眼よりももっと純にかがやいたら、
私の弓がどの絃を
かろい翼のように打つだろうか。
【自註】
戦災で家を失った私は、妻を連れて一年間、親戚や友人の家から家へ転々と居を変えた。
どこでもみんな親切にしてくれたが、それでももう生れ故郷の東京に住む気はなく、
どこか遠く、純粋な自然に囲まれた土地へのあこがれがいよいよ募った。
ところがちょうどその時、或る未知の旧華族から、
長野県富士見高原の別荘の一と間を提供してもいいという好意に満ちた話が来た。
私の心は嬉しさにふるえ、思いはたちまちあの八ヶ岳の裾野へ飛んだ。
この詩はその喜びと期待から颯爽と泉のように噴き出したものである。
第二聯の「愛と戦慄と自分自身の衝動への抵抗なしには生れ得ない」は、
自分の作詞上の心の用意を音楽家のそれになぞらえて、今後は一字一句
たりとも興に任せて放漫には書くまいという決意を示した自省の言葉である。
ベートーヴェンに学ぶこと、それが詩人私の信条だった。
第四聯の「煦々として」は、「おだやかに柔らかく」という意味で使った。
******************
広袤(こうぼう):
「広」は東西の、「袤」は南北の長さの意、幅と長さ。広さ。面積。

~1946年(今から70年前)の尾崎喜八の決意を示した自省の言葉~
戦時下のあのような極限状況のなかに自分がおかれたらどうなるか、
果たして後悔しないですむような生き方ができたろうか・・・
「新らしい絃」 自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
森と山野と岩石との国に私は生きよう。
そこへ退いて私の絃(いと)を懸けなおし、
その国の荒い夜明けから完璧の夕べへと
広袤(こうぼう)をめぐるすべての音の
あたらしい秩序に私の歌をこころみるのだ。
なぜならば私はもう此処に
私を動かして歌わせる
顔も天空を持たないから。
歌はたましいの深い美しいおののきの調べだ。
それは愛と戦慄と自分の衝動への
抵抗なしには生まれない。
私は逆立つ藪や吹雪の地平に立ち向かおう、
強い爽かな低音を風のように弾きぬこう。
だがもしも早春の光が煦々(くく)として
純な眼よりももっと純にかがやいたら、
私の弓がどの絃を
かろい翼のように打つだろうか。
【自註】
戦災で家を失った私は、妻を連れて一年間、親戚や友人の家から家へ転々と居を変えた。
どこでもみんな親切にしてくれたが、それでももう生れ故郷の東京に住む気はなく、
どこか遠く、純粋な自然に囲まれた土地へのあこがれがいよいよ募った。
ところがちょうどその時、或る未知の旧華族から、
長野県富士見高原の別荘の一と間を提供してもいいという好意に満ちた話が来た。
私の心は嬉しさにふるえ、思いはたちまちあの八ヶ岳の裾野へ飛んだ。
この詩はその喜びと期待から颯爽と泉のように噴き出したものである。
第二聯の「愛と戦慄と自分自身の衝動への抵抗なしには生れ得ない」は、
自分の作詞上の心の用意を音楽家のそれになぞらえて、今後は一字一句
たりとも興に任せて放漫には書くまいという決意を示した自省の言葉である。
ベートーヴェンに学ぶこと、それが詩人私の信条だった。
第四聯の「煦々として」は、「おだやかに柔らかく」という意味で使った。
******************
広袤(こうぼう):
「広」は東西の、「袤」は南北の長さの意、幅と長さ。広さ。面積。