さらに昨日の続き。
枠組みとして、よく言われるように、
学校って社会の縮図じゃない?
学校でも、会社でも、安心と不自由は表裏。
艦長が決めた方向に付き進める乗組員だけが、
大きな戦艦に乗せてもらえる。
たとえ行先に疑問を持っても、
行先を変えることはできない。
テストで知識の有無を測られるより、
もっと世が輝いて見えるような方法で教えて欲しいと思っても、
テストの時間にはテストを受けることになる。
大きな船の一般乗務員にできることは、
乗り心地を良くすることであって、
「違う場所に行きましょう」と提案することではない。
「あっちに行くべきでは?」と言えるのは一握りの上層部。
戦艦が迷ったら撃沈されるから、下々にはその権利はない。
テレビの前でビールを飲んでるオヤジは、
野球の監督に無責任に云々言うことはできるけど、
それを実際に試合中の監督に聞いてもらうことはできない。
無責任な傍観者の意見を全部聞くことは、
試合中の監督にとっては、邪魔でしかない。
じゃあ、教師ではない私が、
なんで学校のアレコレにブツブツ言ってんだ?
邪魔したいわけじゃない。
しんどそうだから。きな臭いから。
そっちでいいの?? と思ってるから。
対案を提示しないなら反対するな、ってのは、
与党が野党には言えても、一般ピープルには当てはまらない。
対案は出せないよ。専門家じゃないもの。逃げてるかなぁ。
だけど「私はそうしたくない」ってのは、確実にある。
戦艦に乗っている以上、艦長に従うのは義務だ。
ならば、違和感を抱えて、しんどくなるくらいなら、
それ以上考えずに割り切って、切り替えて
一定の責任を果たす。成果を出す。
そんな風に生きざるを得ないじゃない。しんどくても。
そういう訓練のために、学校も最適化されている気がして仕方ない。
そこからはみ出す人にも、行き場があればいいのに。
学校だったら、ちゃんと、周りの大人たちが、
はみ出したところも込みで、その子まるごとを受け止めること。
世にとってもその子にとっても、必要なことだと思う。
大きな戦艦の中では、命令に従うことで全体が生きていける。
だけど、そこで「もう無理です!」「撃ちたくありません」って
悲鳴を上げられなくて病気になる人もどんどん増えている。
病んでしまった人もしばらく乗せて行ってくれるのは、
艦載能力に余裕があって、しかも艦長がやさしい会社。
余裕がなければ、生きたまま「イヤなら自分で泳げばいい」って、
海に投げ捨てられたりする。
やさしい会社が、目隠しをした漕ぎ手、
つまり、派遣やバイトを安く雇っていっぱい乗せれば、
安く早く船は動く。
漕げ漕げ早く。他のことは考えるな。
誰も目的地は考えるな。方法だけを考えろ。
船の乗り心地は良くて、有能な人が努力してくれているから、
乗っている限りはとりあえず、沈む心配は少ないんだけど、
たとえば、海には浮き輪で漂っている人もいて。
そんな人は、
どこかの船が通っただけの悪気のない波に沈んでも気づかれない。
船の中に、疲れて外見ながら休んでる人がいたら、
そういう人がおぼれていることにも気づくことがあるかも。
順調な時には、身体ひとつで海を漂ってる人に
「乗りたければ、努力して船に乗ればいいじゃないか」と言ってしまえる。
でも、いつ自分もそうなるか、わかんないんだけどね。
努力して乗り込んだ船が沈むことだって珍しくない。
「関係ない」と思えば、どこまでも人に冷たくなれる。
今、役立つことだけが、世に役立つことじゃないもの。
今の時代に順応している人にとって、むしろ迷惑なことから、
次の時代の新しい芽は生まれてくるもの。
前例や規範に従うことからは、新しいことは始まらないもの。
私は、みんなで一緒に幸せになっていきたいなぁ~と思う。
戦場でそんな寝ぼけたことを言ってると殺されるから、
許される範囲で戦場を暖める。たとえば歌を歌う。
人を誘っても黙殺されるなら、
聞こえないくらいの声で小さくハミング。
ハミングが隣の人や隣の隣の人や、次の世代の人に届いて、
「あ、そういえば、私も歌いたかったんだ」と気づけばいいな。
枠組みとして、よく言われるように、
学校って社会の縮図じゃない?
学校でも、会社でも、安心と不自由は表裏。
艦長が決めた方向に付き進める乗組員だけが、
大きな戦艦に乗せてもらえる。
たとえ行先に疑問を持っても、
行先を変えることはできない。
テストで知識の有無を測られるより、
もっと世が輝いて見えるような方法で教えて欲しいと思っても、
テストの時間にはテストを受けることになる。
大きな船の一般乗務員にできることは、
乗り心地を良くすることであって、
「違う場所に行きましょう」と提案することではない。
「あっちに行くべきでは?」と言えるのは一握りの上層部。
戦艦が迷ったら撃沈されるから、下々にはその権利はない。
テレビの前でビールを飲んでるオヤジは、
野球の監督に無責任に云々言うことはできるけど、
それを実際に試合中の監督に聞いてもらうことはできない。
無責任な傍観者の意見を全部聞くことは、
試合中の監督にとっては、邪魔でしかない。
じゃあ、教師ではない私が、
なんで学校のアレコレにブツブツ言ってんだ?
邪魔したいわけじゃない。
しんどそうだから。きな臭いから。
そっちでいいの?? と思ってるから。
対案を提示しないなら反対するな、ってのは、
与党が野党には言えても、一般ピープルには当てはまらない。
対案は出せないよ。専門家じゃないもの。逃げてるかなぁ。
だけど「私はそうしたくない」ってのは、確実にある。
戦艦に乗っている以上、艦長に従うのは義務だ。
ならば、違和感を抱えて、しんどくなるくらいなら、
それ以上考えずに割り切って、切り替えて
一定の責任を果たす。成果を出す。
そんな風に生きざるを得ないじゃない。しんどくても。
そういう訓練のために、学校も最適化されている気がして仕方ない。
そこからはみ出す人にも、行き場があればいいのに。
学校だったら、ちゃんと、周りの大人たちが、
はみ出したところも込みで、その子まるごとを受け止めること。
世にとってもその子にとっても、必要なことだと思う。
大きな戦艦の中では、命令に従うことで全体が生きていける。
だけど、そこで「もう無理です!」「撃ちたくありません」って
悲鳴を上げられなくて病気になる人もどんどん増えている。
病んでしまった人もしばらく乗せて行ってくれるのは、
艦載能力に余裕があって、しかも艦長がやさしい会社。
余裕がなければ、生きたまま「イヤなら自分で泳げばいい」って、
海に投げ捨てられたりする。
やさしい会社が、目隠しをした漕ぎ手、
つまり、派遣やバイトを安く雇っていっぱい乗せれば、
安く早く船は動く。
漕げ漕げ早く。他のことは考えるな。
誰も目的地は考えるな。方法だけを考えろ。
船の乗り心地は良くて、有能な人が努力してくれているから、
乗っている限りはとりあえず、沈む心配は少ないんだけど、
たとえば、海には浮き輪で漂っている人もいて。
そんな人は、
どこかの船が通っただけの悪気のない波に沈んでも気づかれない。
船の中に、疲れて外見ながら休んでる人がいたら、
そういう人がおぼれていることにも気づくことがあるかも。
順調な時には、身体ひとつで海を漂ってる人に
「乗りたければ、努力して船に乗ればいいじゃないか」と言ってしまえる。
でも、いつ自分もそうなるか、わかんないんだけどね。
努力して乗り込んだ船が沈むことだって珍しくない。
「関係ない」と思えば、どこまでも人に冷たくなれる。
今、役立つことだけが、世に役立つことじゃないもの。
今の時代に順応している人にとって、むしろ迷惑なことから、
次の時代の新しい芽は生まれてくるもの。
前例や規範に従うことからは、新しいことは始まらないもの。
私は、みんなで一緒に幸せになっていきたいなぁ~と思う。
戦場でそんな寝ぼけたことを言ってると殺されるから、
許される範囲で戦場を暖める。たとえば歌を歌う。
人を誘っても黙殺されるなら、
聞こえないくらいの声で小さくハミング。
ハミングが隣の人や隣の隣の人や、次の世代の人に届いて、
「あ、そういえば、私も歌いたかったんだ」と気づけばいいな。












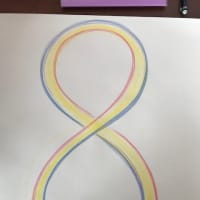







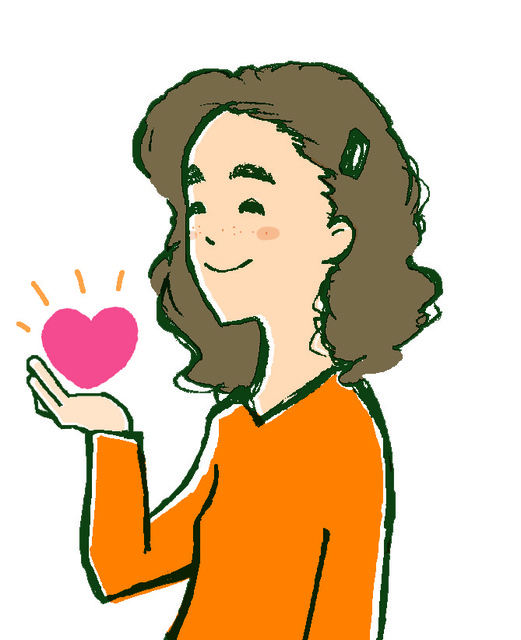

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます