
20代のアパート暮らしの頃から、
生ごみはボカして堆肥にして、
その土でプランターで野菜作ってました。
ただ、近所で売ってるコック付きの生ごみ専用バケツ、
ビジュアル的に黄色とか半透明とかで美しくないし、
残念なことに数年でフタがバキバキに割れるんです。
フタだけでも売ってくれたから、
何度かフタを買い替えたんだけど、
なんかプラを捨てるのは気分が盛り下がるし、
持ち上げたら本体もバキバキ割れるくらい劣化してきた。
ので、今さらながら、
「あのバケツじゃなくてもいいんじゃない?」と思い、
専用バケツを買い変えるのをやめました。
ゴミを減らしたいのに、
ゴミになる事がわかっているものを買いたくない。
ということで、去年あたりから、
家にあったアウトドア用のコンテナを使っています。
黒くて目立たないし、道具でも入ってるみたいで、
庭の隅に積んでてもスッキリ!
改善策の最初は米ぬかを使った段ボールコンポストに挑戦。
肥料としては普通に成功しましたが、
最後にふにゃふにゃになった段ボールが汚くて、
あんまり触りたくない感じではありました。
抵抗のない方は段ボール方式でも大丈夫。
だけど「わざわざ段ボールを使う必要もないんじゃない?」と、
今度は別バージョンに挑戦。手抜き版。
水抜き用に、コンテナ底の4隅に直径7㎜ほどの穴を開け、
そこに毎日の生ごみと、時々ボカシ菌を入れて行くだけ。
穴から勝手に水が抜けるので、水抜きの手間も省けました。
あ、水は液肥として使えるので、
マメに世話する方は液肥もたまる方がいいんでしょうが、
私は放置プレイ気味で、溜まると出す時に臭いから(^^;)、
溜めずにそのまま大地に吸収してもらう作戦です。
この方法が大成功!
臭くもないし、虫も出ないし、水もたまらないし、
しかも、生ごみが発酵して体積が減って行くのか、
(記録してないけど)1か月以上入れ続けても、
全然満タンになりませんでした。
白菜やレタスの大量の外葉、
わさわさしたニンジンの葉っぱなどなど、
大量に入れ続けたのに!
この方法で、十分使い勝手は良くなったし、
肥料づくりとしても成功してたんだけど、
今回は、もう1段階ステップアップ
…になったらおもしろいな、の実験。
最初に土や菌を入れてみたらどうなるんだろ?
菌がいっぱいいそうな腐葉土やミミズのいる土、
精米所でもらってきたヌカ、それにEMボカシ菌。
その3つを最初から混ぜて入れておくことで、
スタンバイしている間に
ボカシ菌をヌカの中で増殖させようという作戦。
スコップも一緒にコンテナに入れておいて、
生ごみを入れたらついでに土をまぶしてフタをする。
そういうサイクルで、どうなるかな~と、
観察してみようと思います。
「嫌気性の菌らしいから密閉しなきゃ」って思ってたんだけど、
バケツのフタが破れてても肥料化したし臭くもなかったから
「あれ? そこまで厳密じゃなくていーんだ!」って。
なら、いったんボカさなくても、底に土入れてたら、
時系列で肥料になってくれるかも?
理想のイメージとしては、
生ごみを投入して2週間くらいで
底から順番に土になっていってくれて、
1か月で満タンになる頃には、
半分くらいはすでに肥料たっぷりの土になってくれる
みたいな感じ。
冬だから気温の関係で、
肥料になるまでに時間がかかるとは思うけど、
最初から生ごみだけ入れてたバージョンと、
底に菌を入れてたバージョンの違いは、
ちょっと観察してみようと思います。
ちょっとずつ手抜きしてきた観察結果として、
あの菌、毎回入れなくても別に臭くならないし、
最初に想定された菌のバランスじゃないかもしれないけど、
空気にさらしたままでも埋めたらちゃんと肥料化します。
絶対に失敗が許されない環境ならいざ知らず、
失敗したら土に埋めちゃえ、という環境なら、
説明通りよりもだいぶん省力化できそうです。
写真載せても美しくないけど、ご参考まで。
この白いのは、土じゃなくて、
半年ほど放置してたら固まってしまったヌカです。



今日の投入分。
大根2本のヘタと葉っぱの黄色くなった所、
皮の青い部分、卵のカラ、みかんの皮などなど。
「小さく刻んで入れましょう」とかいう配慮も、
どーせいつの間にか肥料になってくれるので、
肥料化を急がない時には(っていつもだけど)無視(^^)。
生ごみを出さなくていいのって、ホント楽ちんだし、
暮らしの中に循環系があるのって、
ひとつだけでも、ずいぶん気持ちのいいものです。












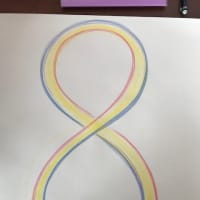







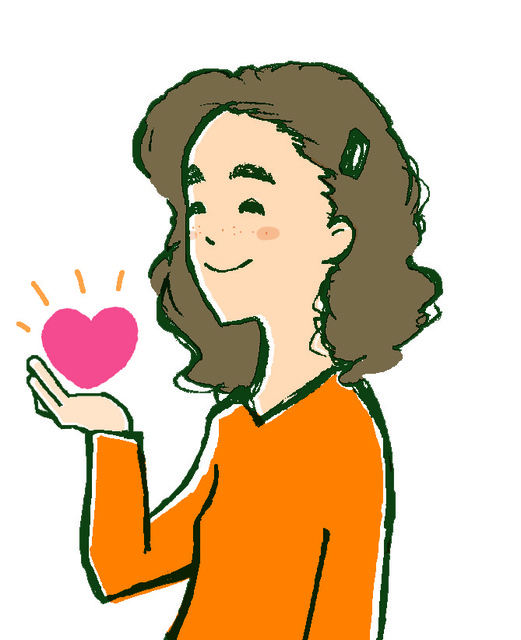

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます