
土佐のくじらです。
さて、源頼朝は、朝廷の軍事部門の長である、征夷大将軍に就任しました。
この征夷大将軍には、朝廷の政治に口を挟む権限はありません。
今の私たちが抱いているイメージである、征夷大将軍=実質的な日本国王という概念は、頼朝以前にはなかったものです。
征夷大将軍は、あくまで軍事部門の長ですから、時の天皇や公家たちは、「鎌倉殿(源頼朝)は、欲がないのう。おーほほほほほほ。(^O^)」と、思っていたでしょうね。
頼朝以前の平清盛は太政大臣という役職に付いて、直接朝廷政治を動かしました。
太政大臣は公家の最高の位です。
当時は貴族以外は政治参画できませんでしたから、平家は貴族化し、政治参入したのですね。
今で言うならば、政治は選挙で選ばれた議員しか行えませんから、国会議員になったのが平清盛で、議員にはならず他の方法で実質的な政治を成したのが源頼朝と言えましょうね。
頼朝の姿勢は、武士としての部をわきまえたもの・・・として、当時の公家たちにはむしろ、謙虚に写ったでしょう。
基本政策も保守的な、土地本位制の維持でしたので、古来の貴族の受けも良かったはずです。
頼朝の考えは平清盛のような、先進的な銭本位制ではありませんでした。
幕府・・・というのも、あくまで建前上は、武士を統括するための拠点であったわけです。
京から遠い鎌倉に、頼朝は幕府を構えましたが、これなども公家側からすれば、朝廷政治に口を挟まない姿勢として、好意的に認識されていたはずです。
ところがどっこい(笑)、当時は土地本位制の時代ですから、領地主を任命する人事権と、税を取り立てる徴税権を、頼朝が事実上握ったことで、実質的な権力は、頼朝の幕府が握ることになったのですね。
頼朝は、武士が貴族の臣下の立場を執りながら、実質的な実権は、ごっそりいただく・・・(笑)。
そういう手法です。
これがその後の武士政権の、一つの模範的な事例となるのですね。このように全国的な影響力を持った頼朝でしたが、幕府内では困った問題を抱えていました。それは・・・。
頼朝には、自分の領地が、全くなかったのです。
頼朝は子供の頃から、たった一人での人質生活でしたし、成人してからは戦続きでした。
当時の領地の概念は、自分で開墾するか、先祖代々受け継いだものでしたので、領地を造る機会も暇もなかった頼朝には、領地は全くありませんでした。
領地がないので、実は自分の直属の家来もほとんどいなかったのですね。
頼朝には、自分の領地がありませんので、御家人に領地を与えることはできませんでした。
「領地を○○の物だと認める。」のが、頼朝流なのです。(笑)
しかしこれで、御家人の間では、領地を巡る争いはなくなったので、そのときは良かったのです。
また、頼朝に忠誠を誓うということで、頼朝の協力者は御家人になりました。
御家人とは言わば、契約社員、傭兵みたいなものですね。
そういう経済構造でしたから、幕府内での頼朝は、北条氏など有力御家人に、食べさせてもらっている立場でした。
故に頼朝は、御家人たちに対して、強い立場での発言は、どうしてもできなかったのです。
言わば、タレント議員一期生で、いきなり総理大臣になったようなものです。(笑)
また、一時期の風によって当選した議員のようなものです。
ですから頼朝は、幕府内では、御家人たちの意向を聞かざるを得ませんでした。
頼朝時代には、都の警護の期間を短くしたり、武士の待遇改善がかなり進みますけど、そういう頼朝の置かれていた環境も、当然影響していると思います。
自分の領地を持たない源氏は、実績もあり、カリスマ性もあった頼朝在世中は、何とか維持されましたが、頼朝の死後、急速に源氏の発言力が小さくなります。
武士の人事権を持つ将軍が、自分の領地がない・・・。
不思議な事実ですけど、後の室町幕府の足利氏も、群馬県の足利郷しか自領を持っていません。
更に後の徳川家康は、天下取りの後も領地の拡大政策を続けますが、その行動原理は、恐らくこういった過去の歴史的教訓から導き出されたものではないかと思います。
そして、鎌倉幕府の源氏は、3代将軍実朝が嫡子を残さず没したことで、嫡流は途絶えました。
その後は、他の土地にいる源氏の血筋の人を探し、お飾り将軍に祭り上げて、一応幕府は続きます。
実権は、最大御家人である北条氏が握り、執権という立場で、実質的な運営を行います。
今も昔も、多くの支持者と安定した政治資金は、とても重要なのですね。













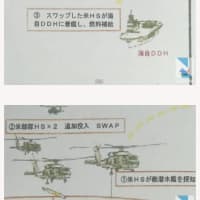






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます