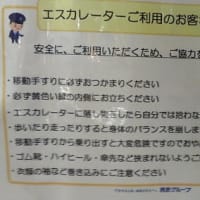4月18日(金)バッハ・コレギウム・ジャパン 第107回定期演奏会
東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル
【曲目】
バッハ/マタイ受難曲 BWV244


【演 奏】
TⅠ&福音史家:ゲルト・テュルク、TⅡ:櫻田亮、BⅠ&イエス:ペーター・コーイ、BⅡ:浦野智行/SⅠ:ハンナ・モリソン、SⅡ:松井亜希、カウンターTⅠ:クリント・ファン・デア・リンデ、カウンターTⅡ:青木洋也 他
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
BCJのマタイを聴くのは6年ぶり。その時の演奏も素晴らしかったが、どこかで共感しきれないものがあった。しかし、ちょうど聖金曜日の今夜聴いたこの「マタイ」は、自分にとって心の底から共感でき、大きな感銘を受ける公演となった。
その感銘は冒頭合唱から始まった。BCJは、全曲のなかでも大きなウェイトを占めてインパクトも強いこの曲に、受難曲全体の全てが凝縮されていることを強く訴えかけてきた。イエス受難の悲痛な気持ちを、今まさにイエスが磔刑にかけられるのをこの目で見ているようなリアリティーで伝え、また、ただ愛ゆえに人の罪を背負ったイエスへの思いが熱く歌われた。「見よ」「いずこを」「私たちの罪深さを」と歌われるくだりでは、変わることのない篤い信仰心を持ち続けることさえ危うい人の弱さを的確に表しているのが手に取るように伝わってきた。その一方でコラールは、イエスがいかに穢れのない存在であるかを強く訴えてくる。善と悪、愛と憎しみ、聖と俗・・・ こうした世界がリアリティーを伴って迫ってきた。
そして繰り広げられて行くイエスの受難劇は、指揮の鈴木雅明とBCJのメンバーが魂を込めて、まさしく渾身のエネルギーを振り絞って伝えてきた圧巻とも言えるリアリティー溢れるドラマ。彼らは一瞬たりともこの受難劇の傍観者になることなく、常にイエスに寄り添って、共に嘆き、共におののき、時に共に怒りを露わにし、共に祈っていた。「十字架につけろ!」と叫ぶ群衆の合唱などは、イエスを責めたてる側に自分が加わってしまっている罪深さへの怒りが込もっているようにも感じられた。更に、後光を表す弦楽合奏を伴ったイエスを含めて、人間臭い姿が赤裸々に描き出されていたことが、聴いていて益々の共感につながったのだと思う。
メンバーの誰もがクリスチャンというわけでは全くないとは思うが、演奏しているときの彼らの心、思いは一つで、熱く、迷うことなく真っ直ぐに一点を見つめている。その「思い」をどのような手段で演奏によって伝えるかということを鈴木雅明は熟知している。その一つとして特筆したいのが、第1曲から第68曲まである楽曲をどのような間隔で配置するかという綿密な設計図が描かれているのを感じたこと。エヴァンゲリストのレチタティーヴォから間髪入れずに合唱が畳み掛けて手に汗握る切迫感を伝えたり、一瞬の間が緊張感を高めたり、沈黙の間が聴き手自らが自分に問う時間を与えたり… 実に臨場感に溢れ、活き活きとストーリーが進行していった。
もう一つ例を挙げるなら、バッハが意図した合唱の明確な役割分担を鮮やかに体現していたこと。イエスを責め立てる群衆の役目を担った合唱、アリアで歌われるテクストを、心の叫びとして訴える合唱、そして常にイエスに寄り添い、信仰への強い決意を歌い上げるコラールとしての合唱。これらが、全く違ったキャラクターを持った生き物のように活き活きと、自らの役割を演じていた。それがあまりにリアリティーに富んでいたせいか、さっきは「イエスを解き放て!」と叫んでいた合唱Ⅱが、合唱Ⅰと一緒になって「十字架につけろ!」と声を合わせている現実や意味にまで考えが及ぶほどだった。
BCJのメンバーは、合唱もオーケストラもソリストも、鈴木が描こうとするこの全く妥協のない世界を、世界でも今考えられる最高の演奏レベルで、実際の音として表現し、訴えかけてきた。ウィーンやベルリンで現地のオケやオペラを聴いたり観たりして、こんな素晴らしい演奏会やオペラを身近で体験できることを羨ましく感じることがあるが、今夜は「世界のBCJのマタイ」を東京で聴くことができる幸せを噛みしめた。
BCJのマタイ (2008.3.21 東京オペラシティコンサートホール)
東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル
【曲目】
バッハ/マタイ受難曲 BWV244



【演 奏】
TⅠ&福音史家:ゲルト・テュルク、TⅡ:櫻田亮、BⅠ&イエス:ペーター・コーイ、BⅡ:浦野智行/SⅠ:ハンナ・モリソン、SⅡ:松井亜希、カウンターTⅠ:クリント・ファン・デア・リンデ、カウンターTⅡ:青木洋也 他
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
BCJのマタイを聴くのは6年ぶり。その時の演奏も素晴らしかったが、どこかで共感しきれないものがあった。しかし、ちょうど聖金曜日の今夜聴いたこの「マタイ」は、自分にとって心の底から共感でき、大きな感銘を受ける公演となった。
その感銘は冒頭合唱から始まった。BCJは、全曲のなかでも大きなウェイトを占めてインパクトも強いこの曲に、受難曲全体の全てが凝縮されていることを強く訴えかけてきた。イエス受難の悲痛な気持ちを、今まさにイエスが磔刑にかけられるのをこの目で見ているようなリアリティーで伝え、また、ただ愛ゆえに人の罪を背負ったイエスへの思いが熱く歌われた。「見よ」「いずこを」「私たちの罪深さを」と歌われるくだりでは、変わることのない篤い信仰心を持ち続けることさえ危うい人の弱さを的確に表しているのが手に取るように伝わってきた。その一方でコラールは、イエスがいかに穢れのない存在であるかを強く訴えてくる。善と悪、愛と憎しみ、聖と俗・・・ こうした世界がリアリティーを伴って迫ってきた。
そして繰り広げられて行くイエスの受難劇は、指揮の鈴木雅明とBCJのメンバーが魂を込めて、まさしく渾身のエネルギーを振り絞って伝えてきた圧巻とも言えるリアリティー溢れるドラマ。彼らは一瞬たりともこの受難劇の傍観者になることなく、常にイエスに寄り添って、共に嘆き、共におののき、時に共に怒りを露わにし、共に祈っていた。「十字架につけろ!」と叫ぶ群衆の合唱などは、イエスを責めたてる側に自分が加わってしまっている罪深さへの怒りが込もっているようにも感じられた。更に、後光を表す弦楽合奏を伴ったイエスを含めて、人間臭い姿が赤裸々に描き出されていたことが、聴いていて益々の共感につながったのだと思う。
メンバーの誰もがクリスチャンというわけでは全くないとは思うが、演奏しているときの彼らの心、思いは一つで、熱く、迷うことなく真っ直ぐに一点を見つめている。その「思い」をどのような手段で演奏によって伝えるかということを鈴木雅明は熟知している。その一つとして特筆したいのが、第1曲から第68曲まである楽曲をどのような間隔で配置するかという綿密な設計図が描かれているのを感じたこと。エヴァンゲリストのレチタティーヴォから間髪入れずに合唱が畳み掛けて手に汗握る切迫感を伝えたり、一瞬の間が緊張感を高めたり、沈黙の間が聴き手自らが自分に問う時間を与えたり… 実に臨場感に溢れ、活き活きとストーリーが進行していった。
もう一つ例を挙げるなら、バッハが意図した合唱の明確な役割分担を鮮やかに体現していたこと。イエスを責め立てる群衆の役目を担った合唱、アリアで歌われるテクストを、心の叫びとして訴える合唱、そして常にイエスに寄り添い、信仰への強い決意を歌い上げるコラールとしての合唱。これらが、全く違ったキャラクターを持った生き物のように活き活きと、自らの役割を演じていた。それがあまりにリアリティーに富んでいたせいか、さっきは「イエスを解き放て!」と叫んでいた合唱Ⅱが、合唱Ⅰと一緒になって「十字架につけろ!」と声を合わせている現実や意味にまで考えが及ぶほどだった。
BCJのメンバーは、合唱もオーケストラもソリストも、鈴木が描こうとするこの全く妥協のない世界を、世界でも今考えられる最高の演奏レベルで、実際の音として表現し、訴えかけてきた。ウィーンやベルリンで現地のオケやオペラを聴いたり観たりして、こんな素晴らしい演奏会やオペラを身近で体験できることを羨ましく感じることがあるが、今夜は「世界のBCJのマタイ」を東京で聴くことができる幸せを噛みしめた。
BCJのマタイ (2008.3.21 東京オペラシティコンサートホール)