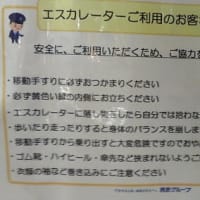9月11日(金)ウィーン国立歌劇場オペラ公演
ウィーン・シュターツオーパー
【演目】
ワーグナー/歌劇「さまよえるオランダ人」

ゼンタを歌ったメルベスも強い存在感でオランダ人の相手役を歌い、演じ切った。オランダ人への取りつかれたような執着心、恋人のエリックとの非情なほどの嫌悪感を剥き出しにしたやり取りなど、真に迫った見事な表現だった。ゼンタの恋人、エリック役のヘルベルト・リッパードは、今回のキャストで唯一名前を知っているベテランの歌手。純粋武骨な田舎のあんちゃんといった雰囲気で、一生懸命なのは伝わってくるが、これではオランダ人に勝ち目はない。そのほか、狡猾さが顔を覗かせるダーラント役のケーニヒから、出番は多くないが人情味を感じるマリー役のウィルソンにいたるまで、誰もが世界を代表するオペラハウスの公演として遜色のないハイレベルの歌唱を聴かせた。
大型船の甲板風の、遠近法を利用した奥行きを感じる舞台の前面に立つ移動式の巨大な装置が、船の着岸や出航をイメージさせ、黒と赤の基調色で不気味な雰囲気を醸し出す。オランダ人は、顔面に血糊がつき、幽霊船の主という容貌を強調していたが、彼が「女」を求めるちょっと滑稽なシーンや、恐ろしい容姿の男にゼンタがこれほどまでに惹かれる様子には、ちょっと違和感。また、水夫と女達が幽霊船に向かって「出てこい!」と叫ぶ場面では、集団の男女による露骨な乱行シーンが繰り広げられたが、これは「早く出て来て女の一人ぐらいものにしろ」ということが言いたいのだろうか。このシーンの意図がよくわからず、不快感さえ覚えた。
演出で最もインパクトがあったのは幕切れでゼンタが死ぬ場面。舞台中央に開いた大きな穴にゼンタが何かを投げ込むと、そこが炎に包まれ、ゼンタは燃え盛る炎のなかに自ら入っていく。これは、舞台としてのインパクトもさることながら、「熱くないの?火傷は大丈夫?」という現実的な心配までしてしまった。ゼンタが自らの死をもってオランダ人を救済するわけだが、オランダ人がどのような形で救済されたかは、舞台を見ている限りではわからなかった。
演出に疑問を感じるところはあったが、とにかくオーケストラの雄弁さは圧倒的だったし、歌手も皆素晴らしかったし、男声合唱も圧巻で、本格的な舞台美術も楽しめ、公演自体は、あの「ラインの黄金」の感動の再来というわけには行かなかったものの、さすがはウィーン国立歌劇場の公演と言っていい。
一方で 女声合唱はボリューム感だけでなく、アンサンブルとしての弱さが気になった。女声合唱に関して言えば、日本の新国立劇場で観た「オランダ人」の合唱の勝ち。ウィーンのオーケストラの雄弁さはやはりすごいが、公演全体として訴えてくる力は、新国立劇場の公演だって全然負けていない。本場と言われるシュターツオーパーの公演を観たことで、なるほど素晴らしいことは確かだが、日本のオペラ水準の高さを確かめる機会ともなった。

ウィーン・フォルクスオーパーの「魔笛」(2015.9.12)
ウィーン・シュターツオーパー
【演目】
ワーグナー/歌劇「さまよえるオランダ人」


| 【配役】 ダーラント:ハンス=ペーター・ケーニヒ、ゼンタ:リカルダ・メルベス、エリック:ヘルベルト・リッパード、マリー:キャロル・ウィルソン、舵手:トーマス・エーベンシュタイン、オランダ人:ミヒャエル・ヴォッレ (Michael Volle) 【演出】クリスティーネ・ミーリッツ 【舞台】シュテファン・マイヤー 【衣装】ヴェラ・リヒター 【演奏】 ペーター・シュナイダー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団/ウィーン国立歌劇場合唱団 6年ぶりにウィーンを訪れ、ウィーン・シュターツオーパーの公演に出かけた。ウィーン滞在中に3演目ほどあった観られる公演から選んだのはワーグナー。6年前にここでウェルザー=メスト指揮で観た「ラインの黄金」の圧倒的な公演の再来を期待して。 いきなり序曲で、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の実力を見せつけた。指揮のシュナイダーは、重たい錨を軽々と振り回すように、力とスピードのドライブをコントロールして音楽を力強く押し進め、重厚でボリューム感たっぷり。オーケストラは全幕を通して(今夜は休憩なしで上演された)終始絶大な存在感を示しつづけた。幕が上がれば、今度は水夫たちの力強く輝かしい男声合唱が轟く。 ソリスト陣も実力派揃い。なかでも群を抜いて素晴らしい歌唱を聴かせたのが、タイトルロールのオランダ人を歌ったミヒャエル・ヴォッレ。まず心に響いてきたのが言葉の美しさ。ヴォッレのドイツ語の発音は、混ざりものがなくくっきりと透明で、聞いていると相手の心の底まで見抜く、澄んだ「眼」が感じられる。清澄でよく通る美しいバリトンの声が、堂々とした物腰から発せられる。その安定感のある朗々とした歌唱が、オランダ人の超越した人物像を幕切れまで一貫して聴衆に強烈に印象づけた。 |   シュターツオーパーの豪華な内装は何度見てもため息。。 |
ゼンタを歌ったメルベスも強い存在感でオランダ人の相手役を歌い、演じ切った。オランダ人への取りつかれたような執着心、恋人のエリックとの非情なほどの嫌悪感を剥き出しにしたやり取りなど、真に迫った見事な表現だった。ゼンタの恋人、エリック役のヘルベルト・リッパードは、今回のキャストで唯一名前を知っているベテランの歌手。純粋武骨な田舎のあんちゃんといった雰囲気で、一生懸命なのは伝わってくるが、これではオランダ人に勝ち目はない。そのほか、狡猾さが顔を覗かせるダーラント役のケーニヒから、出番は多くないが人情味を感じるマリー役のウィルソンにいたるまで、誰もが世界を代表するオペラハウスの公演として遜色のないハイレベルの歌唱を聴かせた。
大型船の甲板風の、遠近法を利用した奥行きを感じる舞台の前面に立つ移動式の巨大な装置が、船の着岸や出航をイメージさせ、黒と赤の基調色で不気味な雰囲気を醸し出す。オランダ人は、顔面に血糊がつき、幽霊船の主という容貌を強調していたが、彼が「女」を求めるちょっと滑稽なシーンや、恐ろしい容姿の男にゼンタがこれほどまでに惹かれる様子には、ちょっと違和感。また、水夫と女達が幽霊船に向かって「出てこい!」と叫ぶ場面では、集団の男女による露骨な乱行シーンが繰り広げられたが、これは「早く出て来て女の一人ぐらいものにしろ」ということが言いたいのだろうか。このシーンの意図がよくわからず、不快感さえ覚えた。
演出で最もインパクトがあったのは幕切れでゼンタが死ぬ場面。舞台中央に開いた大きな穴にゼンタが何かを投げ込むと、そこが炎に包まれ、ゼンタは燃え盛る炎のなかに自ら入っていく。これは、舞台としてのインパクトもさることながら、「熱くないの?火傷は大丈夫?」という現実的な心配までしてしまった。ゼンタが自らの死をもってオランダ人を救済するわけだが、オランダ人がどのような形で救済されたかは、舞台を見ている限りではわからなかった。
演出に疑問を感じるところはあったが、とにかくオーケストラの雄弁さは圧倒的だったし、歌手も皆素晴らしかったし、男声合唱も圧巻で、本格的な舞台美術も楽しめ、公演自体は、あの「ラインの黄金」の感動の再来というわけには行かなかったものの、さすがはウィーン国立歌劇場の公演と言っていい。
一方で 女声合唱はボリューム感だけでなく、アンサンブルとしての弱さが気になった。女声合唱に関して言えば、日本の新国立劇場で観た「オランダ人」の合唱の勝ち。ウィーンのオーケストラの雄弁さはやはりすごいが、公演全体として訴えてくる力は、新国立劇場の公演だって全然負けていない。本場と言われるシュターツオーパーの公演を観たことで、なるほど素晴らしいことは確かだが、日本のオペラ水準の高さを確かめる機会ともなった。

ウィーン・フォルクスオーパーの「魔笛」(2015.9.12)