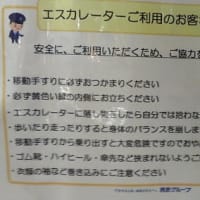静寂の部屋 Raum der Stille
ブランデンブルク門はベルリンを象徴する建造物だが、この門のすぐ手前でベルリンは壁によって東西に引き裂かれ、門は封鎖され、ブランデンブルク門は東西分断の象徴となった。そして1989年11月には、ベルリンの壁崩壊によって、今度はこの場所が統一を象徴する場として注目を浴びた。

そんなドイツ近代史の生き証人とも言えるこのブランデンブルク門の袖に”Raum der Stille”(静寂の部屋)という看板が立っている入口を見つけた。
「ベルリン町中探訪 その1」で紹介した教会やカフェや公園にも大都会の中の静寂はあるが、ここは外の喧騒は全く入って来ない無音の部屋。言葉を交わす人も、本を読んでいる人も、携帯をいじっている人もいない。ここではそのような行為を行わないことが暗黙の了解であるかのように、誰もがただじっと佇み、「静寂」を一身に受け止めている。
やがて他の人たちは部屋を出て行って、しばらくの間、独りだけになった。自分が今どこにいるのか、ここで何を感じ・考えるべきか、座禅をやるとこんな心境になるかも知れない、とも思った。
入口でもらった日本語のプリントに「ここは人種や階層など全ての違いを越えて、全ての人が沈黙を享受できるように提供された場」と書いてあった。平和の門として建てられたというブランデンブルク門の本来の理念を尊重し、ベルリンの壁崩壊の後、この部屋を作ろうという市民運動がきっかけとなってできた部屋だそうだ。
歴史の波に翻弄されたベルリンの町の中心に、こうした静寂の間があることの意味は大きい。ブランデンブルク門に来たら、ちょっとでもここに立ち寄って、静寂の中で何かを感じたい。
ホロコースト記念碑 Holocaust-Mahnmal
ブランデンブルク門からエーベルト通り(Ebertstraße)に入ってすぐのところに、無数の無機質な石碑が整然と並んだ、巨大な墓地のようなところがある。ここは「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑/略称:ホロコースト記念碑」(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)と名付けられ、ドイツが行なった歴史上まれに見る大量殺戮行為を省み、亡くなったユダヤ人への哀悼を捧げ、永遠の平和を誓うために計画され、2005年に完成した2711基の石碑のモニュメントである。

これらのおびたたしい数の石碑は、縦横のサイズは統一されているが、高さは様々で、高さの違いでリズムやアクセントを作り出し、それが何かを訴えているように見える。石碑が並び立つフィールドにはいつでも自由に入ることが出来、石碑の間を歩き回ることができる。

このモニュメントの一角に、地下にある「情報センター」(Ort der Information)への入口がある。この情報センターは、テーマ別に6つの部屋に分かれていて、パネルや写真、映像、遺品など、ヨーロッパのユダヤ人虐殺に関する様々な資料が体系的に展示されている。

瓦礫を除去するように遺体がブルドーザーで「片付けられて」いく
外の石碑モニュメントでユダヤ人の死の恐怖やおののきを象徴的に体験したあとここに来ると、今度は具体的な展示で、ナチスのユダヤ人絶滅政策とその具体的なプロセスが、よりリアルに、強烈な戦慄を持って迫ってくる。
展示はホロコースト以前のユダヤ人の多様な生活世界を紹介するものもあり、人間的・文化的な生活を営んできたユダヤ人社会を知ることで、ホロコーストの理不尽さ、残酷さがより鮮明に浮き彫りにされる。
情報センターは入場無料だが、立派なミュージアムと言ってもいいほど施設も資料も充実していて、ホロコーストについて知ることができる。ずっと昔、まだドイツ統一以前に東ドイツを訪れたとき、ワイマールの近くのブーヘンヴァルト(Buchenwald)というところにあるユダヤ人強制収容所跡を見学したことがある。その体験は、そのあと食事が喉を通らなくなるほどショッキングなものだったが、そのときの体験が甦ったような気がした。
情報センターの開館時間:火~日 10:00~20:00
ドイツという国は、自らが行なった過ちを、こうして徹底的に反省し、後世に伝える努力を怠らない姿勢を貫いていることに、驚嘆と尊敬の念を禁じえない。一方で、ドイツのこうした姿は、ある疑問を投げかけてくる。ドイツは、戦争中に自国のユダヤ人やポーランドなど近隣の国々に大きな災禍をもたらしたことに真摯に向き合い、戦後それを清算してきた。過ちを徹底的に検証し、償い、二度と同じことを行なわないという誓いを打ち立てた。日本について見れば、当事国だけでなく、国際社会が日本に対して、犯した過ちに真に向き合うことを求めることが度々ある。ドイツと比べて、日本の他国に対する戦後処理はやはり不十分と言わざるを得ないだろう。
ドイツや日本が、未だに戦争の清算を求められているのは、もちろん理解できるし、真摯に受け止めるべきだとは思うが、翻って第2次世界大戦の戦勝国が犯した罪は全く何も問われなくていいのだろうか。戦後70年近く経っても世界の力関係は、国連で戦勝国(常任理事国)が幅を利かせるという構図で成り立っているって、いったいどういうこと?
連合国軍が、空襲で無数の市民を殲滅し、町を壊滅したこと、米軍が原爆を投下したこと、ソ連軍が降伏後に日本の領土に侵攻したことなどは、本当に全く問われなくていいのだろうか。こうした「不幸な出来事」を、戦勝国側からも検証し、反省するべきところは反省し、未来永劫同じような不幸をもたらさないよう行動すべきではないか。戦勝国とか敗戦国とかに関係なく、どの国もドイツのように行動すれば、本当の世界平和と融和が実現するだろうに、と思うのだが、それは叶わぬ夢だろうか…
本のない図書館 Versunkene Bibliothek
ナチスの犯した過ちに向き合い、後世にそれを伝える記念碑的なスポットをもう一つ訪れた。ブランデンブルク門からウンター・デン・リンデン通りを進むと、左に、ドイツでも有数の名高いフンボルト大学が立派な正門を構えている。そのフンボルト大学の真向かいにあるベーベル広場(Bebelplatz)がそのスポットだ。

ベルリン・フンボルト大学 (Humbold-Universität zu Berlin)
ヒトラー率いるナチスが政権を取った年(1933年)の5月10日に、この広場で「ドイツ的精神に反する」とされた書物が、ゲッベルス主導の下、ナチスの学生達(Nationalsozialistische Studenten)によって燃やされる「焚書(ふんしょ)」が行なわれた。焚書の犠牲になった書物の著者には、ハイネ、ケストナー、フロイト、それに向かいのフンボルト大学で学んだカール・マルクスなども含まれ、約2万冊が火にくべられたという。そして、このセレモニーを皮切りに、ドイツでは、重さにして「50万キロ分」もの書物が処分されたそうだ。
著作物を燃やす、という行為は、人類がそれまでに育んできた自由な精神活動に対する冒涜であり、この忌まわしきセレモニーは世界史の中でも特筆される事件として記憶されることになる。この出来事を決して忘れない、という思いを込めて作られた記念碑が「本のない図書館」だ。
「図書館」は石畳の広場の中央にある、正方形のガラス張りの小窓から見る。その小窓は地下室の天窓のようで、中を覗くと、その地下の空間は1冊の書物も置かれていない真っ白な空っぽの書棚に囲まれていた。この書架は焚書に遭った書物の数を象徴して、約2万冊分のスペースがあるそうだ。ただそれだけのモニュメント。

石畳にプレートが埋め込まれているほかには目立った看板もなく、知らずにここを歩いていたら気づかないかも知れない。窓に気づいたとしても、ただの地下室の天窓だと思ってしまうだろう。それほど目立たないことが、逆にメッセージ性を高めている。

作者であるイスラエルのアーティスト、ミハ・ウルマン(Micha Ullmann)は、窓を覗いた人が、この地下の空っぽの書架から、燃やされた書物たちの無言の抗議の声に耳を澄ませてもらいたい、という思いを込めたのだと思う。この行為がなければ、市民がナチスの扇動に徒に踊らされることもなく、ユダヤ人粛清を許すこともなかったかも知れない、という思いもあるのだろうか。
世の中で何が正しいかを見極める力を持つには、書物の力に拠るところが大きい。それを世の権力者が統制し、人々から知る自由を奪ったことが、歴史上まれに見る悲劇を生んだ。このことへの永遠の警鐘を、ベーベル広場の地下から、ここを通る人々に静かに鳴らし続けている。

石畳に埋められたプレートには、ここで焚書が行われたことが記されている。
このプレートの左隣にはもうひとつ、詩人のハイネの言葉が刻まれたプレートがある。そこには「これは序幕の出来事に過ぎなかった。書物が焼かれるところでは、最後には人間までもが焼かれるのだ。」という言葉が刻まれている。ハイネが1820年に著した戯曲「アルマンゾル」で焚書を警告した言葉だ。ハイネは自らの作品の中で、自分の著作が焚書に遭うことを予見したのだろうか。
日本でも戦時下において、当局により厳しい言論統制や検閲が行なわれた。人々が知る自由を得るために存在すべき図書館もこれに加担してきた。図書館に、「図書館の自由に関する宣言」の条文が貼ってあるのを見ることがある。「基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料を提供することを最も重要な任務とする」という大原則のもと、全ての図書館はいかなる圧力や権力からも国民の知る自由を守ることを謳った宣言文だ。これには、戦時下に図書館が犯した苦い過去への反省が込められている。
未だに存在する、本を読む自由が奪われている国が、今後どのような運命を辿るか、それはこうした歴史が物語っているだろう。
DDRミュージアム DDR Museum
ウンター・デン・リンデン通りを更に進むと、道はカール・リープクネヒト通り(Karl-Liebknechtstraße)となり、いくつもの有名な博物館が集まるシュプレー川の中州(博物館島)にやって来る。この博物館島は世界遺産にも登録されているが、その対岸、ベルリン大聖堂を正面に見る場所に、DDRミュージアムはある。

ミュージアム付近からのベルリン大聖堂と、遊覧ボートが行き交うシュプレー川の眺め
DDR(デーデーエル)とは、ドイツが分断されていた時代の東ドイツ(ドイツ民主共和国:Deutsche Demokratische Republik)の略称で、ドイツ語で東独を指すときの呼称。冷戦時代、東側の共産圏世界で、経済的には一番の優等生と言われていた東ドイツだが、西側の経済発展との格差は大きく、ベルリンの壁が崩れて東独市民が西側へなだれ込み、その発展ぶりに仰天した姿は、映画「ゴー・トラビ・ゴー」でもコミカルに描かれていた。西ドイツに吸収合併のようにして消えてしまったそんな東ドイツの様子を知ることができるのが、このミュージアムだ。
ドイツ語では、「東」のことを“Osten“(オステン)と言うが、特に統一後、旧東独の人々は、「東の人たち」という意味で「オッシー」“Ossi“と呼ばれた。これに対して西側の人たちは「ヴェッシー」“Wessi“と呼ばれるが、「オッシー」は「遅れた奴ら」「お荷物」といった意味を込めて軽蔑的に使われることもある。
統一後、オッシー達は、西ドイツのように豊かな暮らしができることを期待していたが、現実には、旧東独地域の生活水準は一向に向上せず、失業者は激増し、社会主義体制のもと、国家が一定レベルの生活を保障していた統一前より悪くなる状況に陥った。西側の製品が押し寄せてきて、「東ドイツ製」の商品はたちまち競争力を失い、市場から消えて行った。
西側の競争主義、商業主義に嫌気も覚え、日常親しんでいた品々が消える寂しさも手伝って、のんびりモードだった統一前の生活を「昔も悪くなかった」と懐かしむようになる。これを、「東(オステン)」と「ノスタルジー」を掛けて「オスタルジー(ドイツ語ではオスタルギー“Ostalgie“)」と称する。「グッバイ・レーニン」は、そんな「オスタルジー」をテーマにした映画だったが、このミュージアムでは、数々の展示がオッシーたちのオスタルジーを満たしてくれる。日本人にとっても、ヴェールに包まれていた当時の東の様子や、「昭和」に重なるような展示はとても興味深い。
DDRミュージアムでは、東独時代の生活に関連した様々な展示があるだけでなく、「体験型」と称して、Made in East Germanyのトレードマークとも言える乗用車「トラバント」に乗り込み、シミュレーターで東独時代の街並みを運転体験したり、映像を観たり、ヘッドホンで東独時代の放送を聞いたり、無数の引き出しや小さな扉を自分で開けて、中にあるありとあらゆるグッズをさわったり、おもちゃで遊んだりなど、五感を使って旧東独の暮らしを体験することができる。旧東独の人々の間に広がっていた 「裸文化」について紹介するコーナーなど、当時の人々の暮らしに多方面から光を当て、紹介されているのを見るのも興味深い。

ベルリン町中探訪 その1 クーダム周辺、戦勝記念塔、アスパラ、綿毛…
ベルリン町中探訪 その3 カリーヴルスト、ニコライ地区、ジャンダルメン広場、CDショップDussmann
◆ベルリン関連記事◆
閉店法
ベルリンの壁
ウィーン&ベルリン コンサート&オペラの旅レポート 2009メニューへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
ブランデンブルク門はベルリンを象徴する建造物だが、この門のすぐ手前でベルリンは壁によって東西に引き裂かれ、門は封鎖され、ブランデンブルク門は東西分断の象徴となった。そして1989年11月には、ベルリンの壁崩壊によって、今度はこの場所が統一を象徴する場として注目を浴びた。

そんなドイツ近代史の生き証人とも言えるこのブランデンブルク門の袖に”Raum der Stille”(静寂の部屋)という看板が立っている入口を見つけた。
| 興味がわいて中に入ってみた。入口に座っていた係りのおばさんに「ここには何があるんですか?」と訊ねると、意味ありげな微笑を浮かべて「Stille(静寂よ)」と静かに一言。 ますます気になったので更に中の扉を開けてその「静寂の部屋」へ入ってみた。 タペストリが掛けられた壁に淡い光が当たり、その下には日本の石庭にあるような置石が置かれた部屋に、椅子が並んでいる。何人かの人が座ってじっとしていた。 |  |
「ベルリン町中探訪 その1」で紹介した教会やカフェや公園にも大都会の中の静寂はあるが、ここは外の喧騒は全く入って来ない無音の部屋。言葉を交わす人も、本を読んでいる人も、携帯をいじっている人もいない。ここではそのような行為を行わないことが暗黙の了解であるかのように、誰もがただじっと佇み、「静寂」を一身に受け止めている。
やがて他の人たちは部屋を出て行って、しばらくの間、独りだけになった。自分が今どこにいるのか、ここで何を感じ・考えるべきか、座禅をやるとこんな心境になるかも知れない、とも思った。
入口でもらった日本語のプリントに「ここは人種や階層など全ての違いを越えて、全ての人が沈黙を享受できるように提供された場」と書いてあった。平和の門として建てられたというブランデンブルク門の本来の理念を尊重し、ベルリンの壁崩壊の後、この部屋を作ろうという市民運動がきっかけとなってできた部屋だそうだ。
歴史の波に翻弄されたベルリンの町の中心に、こうした静寂の間があることの意味は大きい。ブランデンブルク門に来たら、ちょっとでもここに立ち寄って、静寂の中で何かを感じたい。
ホロコースト記念碑 Holocaust-Mahnmal
ブランデンブルク門からエーベルト通り(Ebertstraße)に入ってすぐのところに、無数の無機質な石碑が整然と並んだ、巨大な墓地のようなところがある。ここは「虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑/略称:ホロコースト記念碑」(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)と名付けられ、ドイツが行なった歴史上まれに見る大量殺戮行為を省み、亡くなったユダヤ人への哀悼を捧げ、永遠の平和を誓うために計画され、2005年に完成した2711基の石碑のモニュメントである。

これらのおびたたしい数の石碑は、縦横のサイズは統一されているが、高さは様々で、高さの違いでリズムやアクセントを作り出し、それが何かを訴えているように見える。石碑が並び立つフィールドにはいつでも自由に入ることが出来、石碑の間を歩き回ることができる。

 | 石碑の高さは簡単に腰掛けられる程度のものもあれば、身長より高いものなどさまざま。 自分の身長よりはるかに高い灰色の石碑が並ぶ中を歩いていると、周囲の街並みも視界から消え、とても圧迫感を感じる。 タイル張りの地面には微妙な傾斜があり、石碑の高さも不揃いのために平衡感覚がぐらついて、不安な気持ちが助長される。早くここから抜け出したい、という気持ちになり、抜け出して外界が見えたときはなんだかホッとした。 常に抑圧され続け、死の恐怖に怯えていた当時のユダヤ人たちの感覚を追体験するような意図があるのかも知れない。 |
このモニュメントの一角に、地下にある「情報センター」(Ort der Information)への入口がある。この情報センターは、テーマ別に6つの部屋に分かれていて、パネルや写真、映像、遺品など、ヨーロッパのユダヤ人虐殺に関する様々な資料が体系的に展示されている。

瓦礫を除去するように遺体がブルドーザーで「片付けられて」いく
外の石碑モニュメントでユダヤ人の死の恐怖やおののきを象徴的に体験したあとここに来ると、今度は具体的な展示で、ナチスのユダヤ人絶滅政策とその具体的なプロセスが、よりリアルに、強烈な戦慄を持って迫ってくる。
展示はホロコースト以前のユダヤ人の多様な生活世界を紹介するものもあり、人間的・文化的な生活を営んできたユダヤ人社会を知ることで、ホロコーストの理不尽さ、残酷さがより鮮明に浮き彫りにされる。
情報センターは入場無料だが、立派なミュージアムと言ってもいいほど施設も資料も充実していて、ホロコーストについて知ることができる。ずっと昔、まだドイツ統一以前に東ドイツを訪れたとき、ワイマールの近くのブーヘンヴァルト(Buchenwald)というところにあるユダヤ人強制収容所跡を見学したことがある。その体験は、そのあと食事が喉を通らなくなるほどショッキングなものだったが、そのときの体験が甦ったような気がした。
情報センターの開館時間:火~日 10:00~20:00
ドイツという国は、自らが行なった過ちを、こうして徹底的に反省し、後世に伝える努力を怠らない姿勢を貫いていることに、驚嘆と尊敬の念を禁じえない。一方で、ドイツのこうした姿は、ある疑問を投げかけてくる。ドイツは、戦争中に自国のユダヤ人やポーランドなど近隣の国々に大きな災禍をもたらしたことに真摯に向き合い、戦後それを清算してきた。過ちを徹底的に検証し、償い、二度と同じことを行なわないという誓いを打ち立てた。日本について見れば、当事国だけでなく、国際社会が日本に対して、犯した過ちに真に向き合うことを求めることが度々ある。ドイツと比べて、日本の他国に対する戦後処理はやはり不十分と言わざるを得ないだろう。
ドイツや日本が、未だに戦争の清算を求められているのは、もちろん理解できるし、真摯に受け止めるべきだとは思うが、翻って第2次世界大戦の戦勝国が犯した罪は全く何も問われなくていいのだろうか。戦後70年近く経っても世界の力関係は、国連で戦勝国(常任理事国)が幅を利かせるという構図で成り立っているって、いったいどういうこと?
連合国軍が、空襲で無数の市民を殲滅し、町を壊滅したこと、米軍が原爆を投下したこと、ソ連軍が降伏後に日本の領土に侵攻したことなどは、本当に全く問われなくていいのだろうか。こうした「不幸な出来事」を、戦勝国側からも検証し、反省するべきところは反省し、未来永劫同じような不幸をもたらさないよう行動すべきではないか。戦勝国とか敗戦国とかに関係なく、どの国もドイツのように行動すれば、本当の世界平和と融和が実現するだろうに、と思うのだが、それは叶わぬ夢だろうか…
本のない図書館 Versunkene Bibliothek
ナチスの犯した過ちに向き合い、後世にそれを伝える記念碑的なスポットをもう一つ訪れた。ブランデンブルク門からウンター・デン・リンデン通りを進むと、左に、ドイツでも有数の名高いフンボルト大学が立派な正門を構えている。そのフンボルト大学の真向かいにあるベーベル広場(Bebelplatz)がそのスポットだ。

ベルリン・フンボルト大学 (Humbold-Universität zu Berlin)
ヒトラー率いるナチスが政権を取った年(1933年)の5月10日に、この広場で「ドイツ的精神に反する」とされた書物が、ゲッベルス主導の下、ナチスの学生達(Nationalsozialistische Studenten)によって燃やされる「焚書(ふんしょ)」が行なわれた。焚書の犠牲になった書物の著者には、ハイネ、ケストナー、フロイト、それに向かいのフンボルト大学で学んだカール・マルクスなども含まれ、約2万冊が火にくべられたという。そして、このセレモニーを皮切りに、ドイツでは、重さにして「50万キロ分」もの書物が処分されたそうだ。
著作物を燃やす、という行為は、人類がそれまでに育んできた自由な精神活動に対する冒涜であり、この忌まわしきセレモニーは世界史の中でも特筆される事件として記憶されることになる。この出来事を決して忘れない、という思いを込めて作られた記念碑が「本のない図書館」だ。
「図書館」は石畳の広場の中央にある、正方形のガラス張りの小窓から見る。その小窓は地下室の天窓のようで、中を覗くと、その地下の空間は1冊の書物も置かれていない真っ白な空っぽの書棚に囲まれていた。この書架は焚書に遭った書物の数を象徴して、約2万冊分のスペースがあるそうだ。ただそれだけのモニュメント。

石畳にプレートが埋め込まれているほかには目立った看板もなく、知らずにここを歩いていたら気づかないかも知れない。窓に気づいたとしても、ただの地下室の天窓だと思ってしまうだろう。それほど目立たないことが、逆にメッセージ性を高めている。

作者であるイスラエルのアーティスト、ミハ・ウルマン(Micha Ullmann)は、窓を覗いた人が、この地下の空っぽの書架から、燃やされた書物たちの無言の抗議の声に耳を澄ませてもらいたい、という思いを込めたのだと思う。この行為がなければ、市民がナチスの扇動に徒に踊らされることもなく、ユダヤ人粛清を許すこともなかったかも知れない、という思いもあるのだろうか。
世の中で何が正しいかを見極める力を持つには、書物の力に拠るところが大きい。それを世の権力者が統制し、人々から知る自由を奪ったことが、歴史上まれに見る悲劇を生んだ。このことへの永遠の警鐘を、ベーベル広場の地下から、ここを通る人々に静かに鳴らし続けている。

石畳に埋められたプレートには、ここで焚書が行われたことが記されている。
このプレートの左隣にはもうひとつ、詩人のハイネの言葉が刻まれたプレートがある。そこには「これは序幕の出来事に過ぎなかった。書物が焼かれるところでは、最後には人間までもが焼かれるのだ。」という言葉が刻まれている。ハイネが1820年に著した戯曲「アルマンゾル」で焚書を警告した言葉だ。ハイネは自らの作品の中で、自分の著作が焚書に遭うことを予見したのだろうか。
日本でも戦時下において、当局により厳しい言論統制や検閲が行なわれた。人々が知る自由を得るために存在すべき図書館もこれに加担してきた。図書館に、「図書館の自由に関する宣言」の条文が貼ってあるのを見ることがある。「基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料を提供することを最も重要な任務とする」という大原則のもと、全ての図書館はいかなる圧力や権力からも国民の知る自由を守ることを謳った宣言文だ。これには、戦時下に図書館が犯した苦い過去への反省が込められている。
未だに存在する、本を読む自由が奪われている国が、今後どのような運命を辿るか、それはこうした歴史が物語っているだろう。
DDRミュージアム DDR Museum
ウンター・デン・リンデン通りを更に進むと、道はカール・リープクネヒト通り(Karl-Liebknechtstraße)となり、いくつもの有名な博物館が集まるシュプレー川の中州(博物館島)にやって来る。この博物館島は世界遺産にも登録されているが、その対岸、ベルリン大聖堂を正面に見る場所に、DDRミュージアムはある。

ミュージアム付近からのベルリン大聖堂と、遊覧ボートが行き交うシュプレー川の眺め
DDR(デーデーエル)とは、ドイツが分断されていた時代の東ドイツ(ドイツ民主共和国:Deutsche Demokratische Republik)の略称で、ドイツ語で東独を指すときの呼称。冷戦時代、東側の共産圏世界で、経済的には一番の優等生と言われていた東ドイツだが、西側の経済発展との格差は大きく、ベルリンの壁が崩れて東独市民が西側へなだれ込み、その発展ぶりに仰天した姿は、映画「ゴー・トラビ・ゴー」でもコミカルに描かれていた。西ドイツに吸収合併のようにして消えてしまったそんな東ドイツの様子を知ることができるのが、このミュージアムだ。
ドイツ語では、「東」のことを“Osten“(オステン)と言うが、特に統一後、旧東独の人々は、「東の人たち」という意味で「オッシー」“Ossi“と呼ばれた。これに対して西側の人たちは「ヴェッシー」“Wessi“と呼ばれるが、「オッシー」は「遅れた奴ら」「お荷物」といった意味を込めて軽蔑的に使われることもある。
統一後、オッシー達は、西ドイツのように豊かな暮らしができることを期待していたが、現実には、旧東独地域の生活水準は一向に向上せず、失業者は激増し、社会主義体制のもと、国家が一定レベルの生活を保障していた統一前より悪くなる状況に陥った。西側の製品が押し寄せてきて、「東ドイツ製」の商品はたちまち競争力を失い、市場から消えて行った。
西側の競争主義、商業主義に嫌気も覚え、日常親しんでいた品々が消える寂しさも手伝って、のんびりモードだった統一前の生活を「昔も悪くなかった」と懐かしむようになる。これを、「東(オステン)」と「ノスタルジー」を掛けて「オスタルジー(ドイツ語ではオスタルギー“Ostalgie“)」と称する。「グッバイ・レーニン」は、そんな「オスタルジー」をテーマにした映画だったが、このミュージアムでは、数々の展示がオッシーたちのオスタルジーを満たしてくれる。日本人にとっても、ヴェールに包まれていた当時の東の様子や、「昭和」に重なるような展示はとても興味深い。
DDRミュージアムでは、東独時代の生活に関連した様々な展示があるだけでなく、「体験型」と称して、Made in East Germanyのトレードマークとも言える乗用車「トラバント」に乗り込み、シミュレーターで東独時代の街並みを運転体験したり、映像を観たり、ヘッドホンで東独時代の放送を聞いたり、無数の引き出しや小さな扉を自分で開けて、中にあるありとあらゆるグッズをさわったり、おもちゃで遊んだりなど、五感を使って旧東独の暮らしを体験することができる。旧東独の人々の間に広がっていた 「裸文化」について紹介するコーナーなど、当時の人々の暮らしに多方面から光を当て、紹介されているのを見るのも興味深い。

| ただ、オスタルギーに浸っている人達も、東独時代の全てが良かったと思っているわけではない。東独時代は周知のように、独裁政権によって管理され、徹底した監視システムが敷かれ、密告制度がはびこり、人々の自由が抑圧された暗い面を忘れてはならない。映画「善き人のためのソナタ」では、そんな暗い時代の悲哀が描かれているが、そうした暗い面を象徴する展示を見ることもできる。 帰りには、ミュージアムショップに寄って、アンペルメンヒェン関連のグッズなどを選ぶのも楽しい。腹がへったら、併設のDDRレストランで、東独時代のメニューを試すこともできる。このミュージアムは楽しみがたくさんある。 DDRミュージアム(英語版) |  ベルリンの壁の随所にあった監視塔(Wachturm)の模型。壁を越えようとする者は、ここから容赦なく射殺された。 |
ベルリン町中探訪 その1 クーダム周辺、戦勝記念塔、アスパラ、綿毛…
ベルリン町中探訪 その3 カリーヴルスト、ニコライ地区、ジャンダルメン広場、CDショップDussmann
◆ベルリン関連記事◆
閉店法
ベルリンの壁
ウィーン&ベルリン コンサート&オペラの旅レポート 2009メニューへ