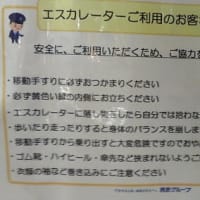1月19日(木)レナード・スラットキン指揮 NHK交響楽団
《2012年1月Bプロ》 サントリーホール
【曲目】
1. ロッシーニ/歌劇「泥棒かささぎ」序曲

2. ルトスワフスキ/チェロ協奏曲(1970)

【アンコール】
バッハ/無伴奏チェロ組曲第1番~サラバンド
Vc:ジャン・ギアン・ケラス
3.ショスタコーヴィチ/交響曲第10番ホ短調Op.93

昨夜は風邪で38度5分の熱にうなされ、今回のN響定期は病欠も覚悟したが、解熱剤が効いたようで今朝は35度まで下がった。一日中頭はボーッとしていたが、何とか無事に演奏会を聴くことができた。スラットキンはN響ではおなじみだが、久々の登場ではないだろうか。全体に少々お肉がついて、それまでの颯爽としたイメージよりもおじいちゃん的な風采が感じられたが、演奏が始まると、指揮姿にも、そして出てくる音にも、年寄りじみたものは微塵も感じない、これまで通り颯爽とした姿で颯爽とした演奏を堪能させてくれた。もっとも、年齢からしてスラットキンは指揮者として老境に入るトシではないが。
一曲目のロッシーニ、目立った合図もなく突如として打ち鳴らされたステージ両翼の小太鼓の凄まじい響きに、ギョッとするほど身が引き締まったが、演奏全体も、実に引き締まった颯爽たるもので、序奏からは、華やいだ雰囲気のなかにも、忍び寄る黒雲が垂れこめる緊張感が漂っているのを感じた。それに続く主要部では、ロッシーニならではのクレッシェンドも、その果ての大爆発も、或いは囁くようなパッセージも冴えに冴え、スラットキン/N響ならではの華やかで鮮やかなオーケストレーションを堪能した。
続いては、ガラリと雰囲気が変わってルトスワフスキのコンチェルト。独奏チェロのケラスによる長いモノローグから、トランペットとの対峙、そしてオケのトゥッティとの対峙と発展して行くが、この様子を聴いていて、ケラスのあまりに鮮やかで軽々とした弓さばきから発せられる柔軟なチェロの調べからは、プログラムの解説で述べられているような、権力との闘争といった深刻な空気は感じられず、むしろ楽しげなディヴェルティメント的気分が伝わってきた。
しかし、曲が進み、チェロがピッチカート主体からアルコ主体へと移ったあたりから、両者によるせめぎ合いが見る見るテンションを上げてきた。ケラスのチェロは研ぎ澄まされ、鋭く深くオケに切り込んで行き、オケはこれに鼓舞されるがごとく反発し、戦意を剥き出しにする。こうしたやりとりによる相乗効果によって演奏はどんどん熱を帯び、最初の気楽な雰囲気はすっかり吹き飛び、聴き手を熱く激しい闘いの中へ引きずり込んで行った。最後のチェロのA音の叫びは、勝利の雄叫びか、それとも断末魔の叫びか… とにかくスゴい演奏だった。アンコールで聴かせたバッハは、戦いを終えた戦士に押し寄せる望郷の念にも聴こえた。
プログラム後半は、N響Bプロでシリーズのように取り上げられているショスタコーヴィチのシンフォニー。正直このシリーズは、長大でなじみが薄いうえに、意味ありげなところがどうもピンと来ない曲が多かったが、今夜の10番は、アシュケナージの指揮で聴いた4番の時以来、久々に感動した。これは演奏によるところ大。
解説を読んでもこの曲がいかなるコンセプトで書かれたかがよくわからないが(結局「戦争3部作」の3作目として構想されたか否かが判然としない)、音楽からは闘争や抵抗の気概がありありと伝わってきた。その闘いは泥臭いものではなく、強靭な剣を振りかざし、毅然と立ち向かう颯爽とした姿で、なんとも格好いい。
ボリューム感たっぷりで強力な金管楽器群が周囲を固め、木管が微妙な風向きを読んで方向を定めると、勇ましいパーカッションの一撃のもと、磨き抜かれた輝かしい光を伴って、鋼のような強靭さで切り込むN響弦楽器群を先陣に、全軍が豪遊果敢になだれ込む。このサウンドの強靭さ、柔軟さ、ドラマチックな表現力は、「世界に冠たるオケの底力を見せつけた」と言えるほど素晴らしいものだった。こうしたパワフルなシーンのみならず、第3楽章の情感溢れる表現も大人の魅力に満ちたもので、これが全体を品格ある演奏にしていた。
先週のエリシュカとはまた別のタイプだが、N響の名演が続いた。もし熱が下がらなかったら「ま、いいか・・・」とやめてしまっただろう。危うく名演を聞き逃すところだった。
《2012年1月Bプロ》 サントリーホール
【曲目】
1. ロッシーニ/歌劇「泥棒かささぎ」序曲


2. ルトスワフスキ/チェロ協奏曲(1970)


【アンコール】
バッハ/無伴奏チェロ組曲第1番~サラバンド
Vc:ジャン・ギアン・ケラス
3.ショスタコーヴィチ/交響曲第10番ホ短調Op.93


昨夜は風邪で38度5分の熱にうなされ、今回のN響定期は病欠も覚悟したが、解熱剤が効いたようで今朝は35度まで下がった。一日中頭はボーッとしていたが、何とか無事に演奏会を聴くことができた。スラットキンはN響ではおなじみだが、久々の登場ではないだろうか。全体に少々お肉がついて、それまでの颯爽としたイメージよりもおじいちゃん的な風采が感じられたが、演奏が始まると、指揮姿にも、そして出てくる音にも、年寄りじみたものは微塵も感じない、これまで通り颯爽とした姿で颯爽とした演奏を堪能させてくれた。もっとも、年齢からしてスラットキンは指揮者として老境に入るトシではないが。
一曲目のロッシーニ、目立った合図もなく突如として打ち鳴らされたステージ両翼の小太鼓の凄まじい響きに、ギョッとするほど身が引き締まったが、演奏全体も、実に引き締まった颯爽たるもので、序奏からは、華やいだ雰囲気のなかにも、忍び寄る黒雲が垂れこめる緊張感が漂っているのを感じた。それに続く主要部では、ロッシーニならではのクレッシェンドも、その果ての大爆発も、或いは囁くようなパッセージも冴えに冴え、スラットキン/N響ならではの華やかで鮮やかなオーケストレーションを堪能した。
続いては、ガラリと雰囲気が変わってルトスワフスキのコンチェルト。独奏チェロのケラスによる長いモノローグから、トランペットとの対峙、そしてオケのトゥッティとの対峙と発展して行くが、この様子を聴いていて、ケラスのあまりに鮮やかで軽々とした弓さばきから発せられる柔軟なチェロの調べからは、プログラムの解説で述べられているような、権力との闘争といった深刻な空気は感じられず、むしろ楽しげなディヴェルティメント的気分が伝わってきた。
しかし、曲が進み、チェロがピッチカート主体からアルコ主体へと移ったあたりから、両者によるせめぎ合いが見る見るテンションを上げてきた。ケラスのチェロは研ぎ澄まされ、鋭く深くオケに切り込んで行き、オケはこれに鼓舞されるがごとく反発し、戦意を剥き出しにする。こうしたやりとりによる相乗効果によって演奏はどんどん熱を帯び、最初の気楽な雰囲気はすっかり吹き飛び、聴き手を熱く激しい闘いの中へ引きずり込んで行った。最後のチェロのA音の叫びは、勝利の雄叫びか、それとも断末魔の叫びか… とにかくスゴい演奏だった。アンコールで聴かせたバッハは、戦いを終えた戦士に押し寄せる望郷の念にも聴こえた。
プログラム後半は、N響Bプロでシリーズのように取り上げられているショスタコーヴィチのシンフォニー。正直このシリーズは、長大でなじみが薄いうえに、意味ありげなところがどうもピンと来ない曲が多かったが、今夜の10番は、アシュケナージの指揮で聴いた4番の時以来、久々に感動した。これは演奏によるところ大。
解説を読んでもこの曲がいかなるコンセプトで書かれたかがよくわからないが(結局「戦争3部作」の3作目として構想されたか否かが判然としない)、音楽からは闘争や抵抗の気概がありありと伝わってきた。その闘いは泥臭いものではなく、強靭な剣を振りかざし、毅然と立ち向かう颯爽とした姿で、なんとも格好いい。
ボリューム感たっぷりで強力な金管楽器群が周囲を固め、木管が微妙な風向きを読んで方向を定めると、勇ましいパーカッションの一撃のもと、磨き抜かれた輝かしい光を伴って、鋼のような強靭さで切り込むN響弦楽器群を先陣に、全軍が豪遊果敢になだれ込む。このサウンドの強靭さ、柔軟さ、ドラマチックな表現力は、「世界に冠たるオケの底力を見せつけた」と言えるほど素晴らしいものだった。こうしたパワフルなシーンのみならず、第3楽章の情感溢れる表現も大人の魅力に満ちたもので、これが全体を品格ある演奏にしていた。
先週のエリシュカとはまた別のタイプだが、N響の名演が続いた。もし熱が下がらなかったら「ま、いいか・・・」とやめてしまっただろう。危うく名演を聞き逃すところだった。