
日本列島にヒトが登場したのが、37,000~38,000年頃前だと言われています。
現時点、世界最古の磨製石器が出土されたことで、日本人のルーツは概ねその辺りというイメージがされていて、結構長い間日本人はこの列島で生活をしているという事になります。
その間の一時は文字を持たずに口伝で物語が伝承されてそれが、神話へと熟成されてきたのかもしれません。
おそらくはそんなこんなで、日本の神話へと昇華されたのではないでしょうか。
やがて人口も増えてきて集団の数や人口も肥大化して、日本人は10,000年以上にわたって狩猟採集生活を営んでいた。
農耕を覚えて日本人は縄文時代を弥生時代へと日々の生活に変革を取り入れた。
大陸では3,100~3,400年前頃に甲骨文字が活用されるようになって、甲骨文字が漢字になって日本に登場するのが1世紀頃だというから、甲骨文字からなら日本では、1,000年以上経ってから文字を知るようになったと・・・。
飛鳥時代になって聖徳太子(厩戸皇子)が十七条の憲法を制定したのが、604年。
古事記が編纂されたのが、720年。
記紀は仏教が伝来されてから100年後くらいに編纂された。
十七条の憲法には、篤く三宝を敬えと言われて、それまでの神々にかけて十七条にしたという説があります。
1. 雨之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)
2. 高御産巣日神(たかひむすひのかみ)
3. 神産巣日神(かみむすひのかみ)
4. 宇麻志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこじのかみ)
5. 天之常立神(あめのとこたものかみ)
6. 国之常立神(くにのとこたちのかみ)
7. 豊雲野神(とよくものかみ)
8.9. 宇比地邇神・須比地邇神(うひちにのかみ・すひちにのかみ)
10.11. 角木杙神・活木杙神(つのくひのかみ・いくくひのかみ)
12.13. 意富斗能地神・大斗乃弁神(おほとのちのかみ・おほとのへのかみ)
14.15. 於母陀琉神・阿夜詞志古泥神(おもたるのかみ・あやかしこねのかみ)
16.17. 伊邪那岐神・伊耶那美神(いさなきのかみ・いざなみのかみ)
以上の十七柱の神々にかけて十七条の憲法を制定されたと・・・。
これが帝国憲法まで神話のエッセンスが、挿入されていて日本人には今より深い神話が日々の生活に深く浸透していたイメージです。
最後の終戦を迎えて今まで神話の濃度がこの国では、希釈されたかのような印象も否めません。
生前、歴史学者アーノルド・J・トインビーは、子どもの頃に神話を教えてあげないと亡国の憂き目に遭うと言っていたとか・・・。
という事で、記紀は小さい頃から教えてあげてあげたいお話しだとも思うのです。
当の自分自身すら上述の神々の中で知っているのは、数柱・・・(>_<)
トインビーの言が正しければ、亡国の憂き目に遭いそうなお国が、近い将来にも現れるのでしょうか・・・?
そもそも人類は物語が大好きな生き物なのだから、神話をもっと拡散されてもよさそうな気もします。
神話には長年培ってきた悲喜こもごものお話、伝え残しておきたい言霊が包まれている印象があります。
神話にはそんな奥の深いマークが潜んでいそうで、そこには民族の多様性を匂わせてくれていて、それは地球上の生物の宿命の多様性の維持に繋がっていて、どちらかと言えば神話の語り継ぎは至極健全なイメージな気もします。 
【タロットカード】日本神話タロット 極














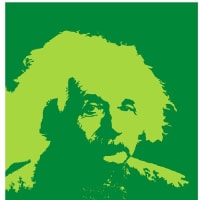
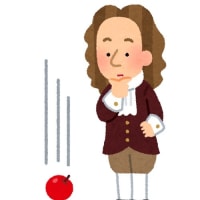




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます