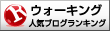話すことは山ほどある。だが、今日は「教員になるには」に的をしぼる。このことに関して、読者の質問に答える形で、先日の朝日新聞に回答者が答えていた。便宜上、私立校と公立校を分けると、以下のような主旨の回答であった。
(1)私立校教員になるには、大学等で教員免許を取得すればそれでよい。
(2)公立校教員になるには、教員免許を取得し、各県などで行われる採用試験に合格すればよい。
だが、(2)の場合、各県の試験に合格すれば、採用されるように回答していた。正確に言うと、誤りである。合格=採用ではない のだ。私の頃と現在の制度は多分同じであろう。つまり、採用候補者名簿に登載されるだけで、しかも、期間は1年間。その年に採用予定より多く合格させ、欠員が生じたら、その名簿から各校長が選んでいくことになっている(多分、現在もそうだろう。まさか、それまでも教育委員会が決めるようにはなってはいないと思うが--)。
夏目漱石の時代は、公立校と云えども、試験も何もせず、校長が決めた。大学の就職掲示板を見て、「四国の松山のほうに口があるな、よし行ってみるか」ということで、若き日の漱石は教師になったのであろう。教育委員会がのさばることのない、旧き良き時代であった。
漱石の時代は、教員免許も怪しいものだ。現在では、取得の過程で教育実習というのがある。学校で2週間以上見習いをしなければいけない。これが問題なのだ。実習校を大学で探してくれる所は少ないはずだ。だって、学生を受け入れる側にとって、こんな迷惑なことは無い。この面倒を見るのは、校長でも教頭でも、教育委員会でもない。現場の教師である。実習生を預かる教師は、他の仕事をしなくていい、なんてことは絶対無いのだ。
だから、学生は出身校に行って頼み込むことになる。自分の教え子に頼み込まれたら、断るわけにはいかないだろう。だが、担当教師も、すべての面倒を自分一人でできるはずがない。その一部は、他の同僚に頼むことになる。頼まれたほうは、他校から転任してきたばかりで、自分の教え子でもない学生の面倒の一端を担うことになる。
{ ここで、脱線するが、「同一勤務校に長くいてはいけない」という教育委員会の命令で、現在は愛校心溢れる名物教師はいない。卒業生にしてみれば、母校に行っても、(自分の勤務校に愛着の薄い)知らない教師ばかり。}
ここで、この採用試験の倍率に触れる。これは、その時の社会情勢に大いに影響される。好不況の経済もある。新人を沢山必要とする年と、教員が余って、新規採用にブレーキがかかる年がある。同じ実力の学生も、Aの年なら合格、Bの年受験なら不合格となるのだ。
私の卒業の年は不況で、どこの県も採用を控え、厳しかった。私の所属クラブには教育学部の4年生も数人おり、彼らは小学校教員を目指して大学に入ってきたのだ。ところが、我々が卒業の年は、東京都の小学校教員採用試験は行われなかった。つまり、採用ゼロの年---こういうこともある。
話を元に戻す。コネや口利きの件だ。私立の場合は、多分理事長というワンマンがいるのだろう。新規採用の人選は、その学校の教員が口を挟む余地はまずないだろう---この先は言うまでもない。
さて、公立校の採用候補者名簿である。現在もこの制度が生きていると思う。
試験の点数改ざんなど、一切の不正も無く、ここまでたどり着いたとしよう。だが、ここから先は、コネや口利きが入っても仕方ないだろう。
校長側から見て、何の縁もない者を採用するだろうか?例えば、学閥。首都圏の公立高校の場合、メイケイ会がダントツ。現在で云えば、筑波大のOBたち。どこの高校に赴任しても、その高校の主流は(私の親友を含めて)メイケイ派。そこ出身の校長が、未知の人間の名簿から選ぶ基準は何だろうか?
学閥と関係なくても、地元の有力者・議員----、いろいろな接近が校長にはあるはずだ。
私は、コネがなかったので、大学の先生にお願いした。だが、私の出身校は、メイケイでも、トーダイでも、トウモン会でもない。不況の時代であったので、下手な鉄砲数撃ちゃ当たるとばかり、関東一円の県の教員採用試験は、日程が重ならない限り、半分以上受けた。だが、せっかく名簿に登載されても、コネが無かったせいか、静岡県からも、神奈川県からも、いっさい呼び出しが無かった。呼び出しがあったのは、たった一つ、千葉県茂原農業の校長からであった。大学の先生が、(教育界にほんの一握りの)母校OBの高校長に依頼し、その校長が茂原農高の校長に推薦したのであろう。その意味では、母校のお世話になったわけで、感謝している。
以上、教育実習という壁、採用試験で、一次試験→二次試験→三次試験(実技)と絞られていく過程での重圧、そして最後にコネ・口利き、そして社会情勢。教員になるのは大変だ。しかも、せっかく夢を叶えても、勉強嫌いの子供たち、ケイタイ氾濫の現場、学級崩壊、無理難題をふっかける親たち---またまた、大変だ。これじゃぁ、精神を病んで休職状態に入る教師も年々増えるわけだ。