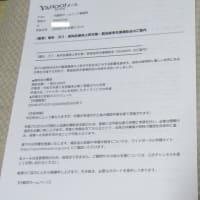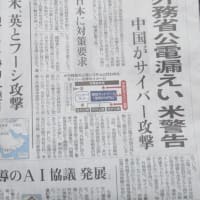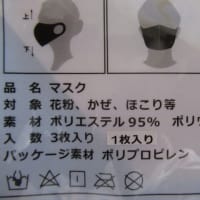揚げ足取り
「戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。」
これに噛みついたのがよくテレビに出て来る大学准教授。
「慰安婦の一言付ければいいんですよ」と来た。
バカじゃないだろうか、戦争時には慰安婦以外に一般市民も強姦された事実を知らないのか。
何とかの一つ覚えで謝罪だのなんだのと。
「日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」
これは今回の談話を持って今後一切謝罪を続けない、と言うものではなく
今後はあの大戦時の愚を繰り返してその件で再び謝罪をさせ続ける宿命を背負わせない。
と解釈出来る。
総じて、今回の(有識者達が一所懸命ひねり出した)
安倍談話よりはテレビ企画の若者達の戦後70年談話の方が優れているのは確かである。
以下、全文
◆私たちの戦後70年談話
戦争を経験していない私たちは、どのように過去を捉え、何を引き継いでいくのか。私たちは一市民として戦後70年と向き合い、犠牲になられた全世界の方を想うとともに、未来について考えました。
当時の国際情勢のもとでは、多くの国が戦争への道を歩みました。日本はアジア太平洋諸国をはじめとする国々へ植民地支配と侵略を行い、甚大なる被害を生み出しました。
同時に、沖縄をはじめとする地上戦や、全国各地での空襲、広島・長崎に落とされた原爆などによって、多大な犠牲がありました。
「戦争は人を人でなくす」と体験者は私たちに語ります。目に見える被害だけでなく、人々の心を深く傷つけ、多くの関係を分断しました。国内外におけるこれらの傷は、戦後70年経った今でも消えていません。
尊い命のバトンを引き継ぐ私たちは、平和のために何をしていかなければならないでしょうか。自分たちの経験をもとに話し合いました。
私たちは、現地を訪ねること、実体験を聞くことを通して、言葉にできない生々しさを感じました。戦争体験者が少なくなっている今、その声を次の世代に語り継いでいくことが、私たちにできる平和への貢献のひとつだと考えます。
歴史や政治の問題は複雑に絡み合っています。それぞれの立場や解釈があり、実際に私たちも議論を通して改めてそれらと向き合う難しさを感じました。いまの日本では誰でも自由に発言することが認められています。私たちひとりひとりは国家の行動に対して責任を持ち、自ら考え、自分たちの意思を表現する必要があるのではないでしょうか。
また私たちが生きる現代は、人やモノ、情報などが国を越えて自由に行き交い、様々な違いに直面する機会が多くなりました。その違いを認めないことは新たな争いを生むことに繋がります。だからこそ、私たちは国内外の市民交流などを通して、一歩ずつ相互理解を進めていく必要があります。
談話作成を通して、私たちは戦争という悲劇を繰り返してはいけないという強い想いを新たにしました。そして、日本だけでなく、世界の平和を実現するために、私たちは様々な視点から学び、行動し続けていきます。
2015年8月14日
「戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。」
これに噛みついたのがよくテレビに出て来る大学准教授。
「慰安婦の一言付ければいいんですよ」と来た。
バカじゃないだろうか、戦争時には慰安婦以外に一般市民も強姦された事実を知らないのか。
何とかの一つ覚えで謝罪だのなんだのと。
「日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。」
これは今回の談話を持って今後一切謝罪を続けない、と言うものではなく
今後はあの大戦時の愚を繰り返してその件で再び謝罪をさせ続ける宿命を背負わせない。
と解釈出来る。
総じて、今回の(有識者達が一所懸命ひねり出した)
安倍談話よりはテレビ企画の若者達の戦後70年談話の方が優れているのは確かである。
以下、全文
◆私たちの戦後70年談話
戦争を経験していない私たちは、どのように過去を捉え、何を引き継いでいくのか。私たちは一市民として戦後70年と向き合い、犠牲になられた全世界の方を想うとともに、未来について考えました。
当時の国際情勢のもとでは、多くの国が戦争への道を歩みました。日本はアジア太平洋諸国をはじめとする国々へ植民地支配と侵略を行い、甚大なる被害を生み出しました。
同時に、沖縄をはじめとする地上戦や、全国各地での空襲、広島・長崎に落とされた原爆などによって、多大な犠牲がありました。
「戦争は人を人でなくす」と体験者は私たちに語ります。目に見える被害だけでなく、人々の心を深く傷つけ、多くの関係を分断しました。国内外におけるこれらの傷は、戦後70年経った今でも消えていません。
尊い命のバトンを引き継ぐ私たちは、平和のために何をしていかなければならないでしょうか。自分たちの経験をもとに話し合いました。
私たちは、現地を訪ねること、実体験を聞くことを通して、言葉にできない生々しさを感じました。戦争体験者が少なくなっている今、その声を次の世代に語り継いでいくことが、私たちにできる平和への貢献のひとつだと考えます。
歴史や政治の問題は複雑に絡み合っています。それぞれの立場や解釈があり、実際に私たちも議論を通して改めてそれらと向き合う難しさを感じました。いまの日本では誰でも自由に発言することが認められています。私たちひとりひとりは国家の行動に対して責任を持ち、自ら考え、自分たちの意思を表現する必要があるのではないでしょうか。
また私たちが生きる現代は、人やモノ、情報などが国を越えて自由に行き交い、様々な違いに直面する機会が多くなりました。その違いを認めないことは新たな争いを生むことに繋がります。だからこそ、私たちは国内外の市民交流などを通して、一歩ずつ相互理解を進めていく必要があります。
談話作成を通して、私たちは戦争という悲劇を繰り返してはいけないという強い想いを新たにしました。そして、日本だけでなく、世界の平和を実現するために、私たちは様々な視点から学び、行動し続けていきます。
2015年8月14日