散骨(Wikipediaより抜粋)
散骨をめぐる問題
散骨が海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、陸地で行われることについては、散骨を行いたいとする者やそれをビジネスとしている業者と、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。
陸地で行われる場合、土地所有者に無断で行うことができないのはもちろんである。土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めない。
2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張しているが、それは過剰反応であるという受け止め方もある。
なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人葬送の自由をすすめる会が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあるのが現状である。
実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので。まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われない。

お墓であっても、「自然に還す」とかいってお骨を撒いていませんか?
自分ん家のお墓のカロートの中に散骨してはいませんか?
札幌市内には、墓地の跡地がいくつかあるのをご存知だろうか?
豊平墓地跡(札幌市豊平区豊平5条11丁目)
明治37年、豊平村が設立した墓地。低地やくぼ地が多く、戦時中は食糧増産のため耕作されるなど荒廃していた。現在は移転されている。面積約42,000m2。現在ここに北海道立新体育センターきたえーるが建築されているが、樹木の移転作業中、北海道開拓時代らしい時期の人骨15体が発見され、里塚の無縁供養塔に納骨した。(平成8年10月26日北海道新聞)
つまり土葬時代の人骨!
まだ残っているかも・・・
そんなところに住んでいるんですよ!
最新の火葬場で焼かれ、その上散骨用にパウダー加工された焼骨が、農作物にどんな影響を及ぼすというのだろうか?
樹木葬散骨を問題視するのは、散骨による農作物への風評被害ではなく、
民間企業が事業として実施する以上、企業が倒産した場合である。
一般の民間霊園の場合だと、お墓を建立した後には毎年管理費がかかってくる。
お寺の場合だと、檀家になって護持費を払う。
お墓建立者が増えることによって、継続的に確実に入ってくるお金があるから運営していける。
樹木葬散骨だと、散骨の実施費用のみで、以後継続的に入ってくるお金はない。
常に新しい散骨希望者を求め続けなければならない。
よって、事業としての継続性が危ういということになる。
お墓のように移転することもできない。
Wikipediaの記述の通り、宗教法人でないと、樹木葬散骨は厳しいのではないかと考えてしまいます。
散骨をめぐる問題
散骨が海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、陸地で行われることについては、散骨を行いたいとする者やそれをビジネスとしている業者と、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。
陸地で行われる場合、土地所有者に無断で行うことができないのはもちろんである。土地所有者の許可がある場合や、自己の所有地で行う場合であっても、散骨は風習として新しいため、近隣住民などが違和感・拒否感を抱く場合があることは否めない。
2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張しているが、それは過剰反応であるという受け止め方もある。
なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人葬送の自由をすすめる会が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあるのが現状である。
実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても、散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなど民事的な問題が起こりうるので。まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われない。

お墓であっても、「自然に還す」とかいってお骨を撒いていませんか?
自分ん家のお墓のカロートの中に散骨してはいませんか?
札幌市内には、墓地の跡地がいくつかあるのをご存知だろうか?
豊平墓地跡(札幌市豊平区豊平5条11丁目)
明治37年、豊平村が設立した墓地。低地やくぼ地が多く、戦時中は食糧増産のため耕作されるなど荒廃していた。現在は移転されている。面積約42,000m2。現在ここに北海道立新体育センターきたえーるが建築されているが、樹木の移転作業中、北海道開拓時代らしい時期の人骨15体が発見され、里塚の無縁供養塔に納骨した。(平成8年10月26日北海道新聞)
つまり土葬時代の人骨!
まだ残っているかも・・・
そんなところに住んでいるんですよ!
最新の火葬場で焼かれ、その上散骨用にパウダー加工された焼骨が、農作物にどんな影響を及ぼすというのだろうか?
樹木葬散骨を問題視するのは、散骨による農作物への風評被害ではなく、
民間企業が事業として実施する以上、企業が倒産した場合である。
一般の民間霊園の場合だと、お墓を建立した後には毎年管理費がかかってくる。
お寺の場合だと、檀家になって護持費を払う。
お墓建立者が増えることによって、継続的に確実に入ってくるお金があるから運営していける。
樹木葬散骨だと、散骨の実施費用のみで、以後継続的に入ってくるお金はない。
常に新しい散骨希望者を求め続けなければならない。
よって、事業としての継続性が危ういということになる。
お墓のように移転することもできない。
Wikipediaの記述の通り、宗教法人でないと、樹木葬散骨は厳しいのではないかと考えてしまいます。















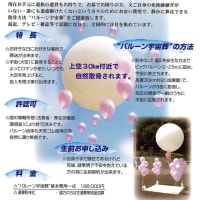
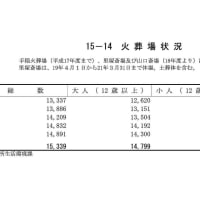




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます