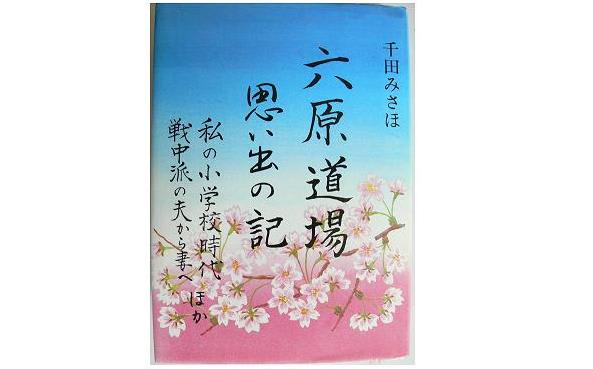
《1↑ 『六原道場思い出の記』(千田みさほ著)表紙》
以前”再び「雄叫び」について”において次のような写真を載せ
**********************************************************************************
【一〇 雄叫び】

ということで「雄叫び」のイメージがある程度できた。写真からはグラウンドを行進しながら歌などを歌っているようだ。もしかすると小冊子『雄叫び』の中にある歌などを声高に歌っていたのではなかろうか。
**********************************************************************************
と推測してみた。とはいえ、いまひとつ「雄叫び」というものがはっきり解らなかった。
ところがこの度『六原道場思い出の記』(千田みさほ著)という著書を手に入れることができ、嬉しいことにそこには「雄叫び」についての説明があった。
『朝の行事』の中でまず次のようなことを述べ
清掃された早朝の神社の前に太鼓の音と共に集合し、青教男子、農指生、長期生、短期生男子、次に女子の順で整列し、班長が当番の先生に人員報告をする。
その後、修祓に移る。先ず当番の先生が社前にすすみ、二拝二拍手の後祝詞をあげ、幣を振りその後納めて修祓を得る。ついで『君が代』斉唱と共に国旗掲揚、その後教育勅語奉読、全員参拝。この次に「雄叫び」に移る。
引き続き「雄叫び」について説明している。同著からそのまま引用すれば
『雄叫び』は、男子先輩の、力強い”建国の歌”の音頭に始まり、全員足踏みしながら、大合唱となり、男子と女子が二列ずつ併行して行進し、第一運動場に移行し、神話の、いざなぎ、いざなみのみことの故事に習って、男子は左、外廻りを、女子は右、内廻りを、合唱しながら、それぞれ大きな円を描いて進んで行った。”建国の歌”が終わると”植民の歌”が続けられた。…(中略)…
植民の歌の四番が終わる頃には、体操の出来る体系に間隔を離して、その場、足踏みとなり、合唱終了と共に雄叫びも終わった。
というように説明してあった。
したがって予想はほぼ正しかったようで、前掲の写真【一〇 雄叫び】はまさしくこの説明にあるような「雄叫び」の一場面であったのだった。
なお、”建国の歌”とか”植民の歌”については
《2 『雄叫び』(岩手県立青年学校教員養成所編、岩手県立青年学校教員養成所報国発行)》

《3 〃の目次》

の中にもあり、歌詞はそれぞれ
”建国の歌”
一
澎湃みなぎる青海原に
我等御祖の言の葉凝りて
御生れましたる豊秋津洲
朝日夕日の直照るところ
光明の国我等が日本
二
照る日の下に鋭鎌を握り
岩根木根立ち踏みさくみけむ
我等祖先の直進みてし
建国の御業仰ぐ尊し
宏遠の国我等が日本
三
懐古の念凝り建国の魂
吹気に集ふ健児我等
岩手の霊峰何をか教へ
北上の清流何をか語る
秀麗の国我等が日本
四
まがつひの雲湧き立ち昇り
世は常闇となり果てぬとも
見よわがしるべ明るき浄き
直き誠の力こもれり
信念の国我等が日本
五
天つ日かげを真面にかざし
世界の表に先立ち行かん
これぞ我等が尊き使命
行くては希望の光に満てり
正大の国我等が日本
”植民の歌”
一
萬世一系比ひなき
すめらみことを仰ぎつゝ
天涯萬里野に山に
荒地開きて敷島の
大和魂を植るこそ
日本男児の誉なれ
二
北海の果て樺太に
斧鉞入らざる森深く
北斗輝く蝦夷の地に
金波なびかぬ野は広し
金剛聳ゆる鶏林に
未墾の沃野吾を持つ
三
峻嶺雲衝く新高の
芭蕉の葉影草茂る
広漠千里満洲の
地平の果てに夕陽は赤く
興安嶺の森暗し
いざ立て健児いざ行かん
四
高鳴る胸の血潮もて
紅ひそめし日章旗
高き理想と信仰の
御旗かざして吾行かむ
東亜の天地黎明の
晨を告ぐる鐘ぞ鳴る
というように、雄々しいものだった。
ところで、この著者千田みさほさんは「青教生」であったという。すなわち、青年学校教員養成所生であったというが、青年学校教員養成所とは一体なんだっんだろうか。
同著には次のように書かれている。
青教生の中には、助教員を何年かした後、有資格者にと、入学してくる人もいて、年齢は十七歳から二十五歳までの開きがあった。…(略)…青教の二年の課程を終えると、県内の青年学校の教諭となり…(略)
ということは
青年学校教員養成所=青年学校の教員養成所
ということであろう。
因みに
《4『彗星の如く 岩手県青年学校教育の記録と回想』》

(済みません著者及び発行所調査中です)
には次のような事柄が書いてある。
青年学校は実業補習学校と青年訓練所の統合によって設立された青年教育制度である。
実業補習学校は、ほぼ例外なく地元の小学校に併設され、その小学校長が実業補習校の校長を兼務し、教師も殆ど小学校教員の兼務であった。このような学校事情の中で、師範学校制度がほぼ実業補習学校教育をも担当する教員養成の一端をになっていたのである。
明治26年に交付された実業補習学校規定により実業補習学校の専任教員の養成が提唱され、大正10年に「岩手県立実業補習学校教員養成所」が盛岡高等農林学校に併設された。
本来、実業補習学校は農山漁村の青少年を教育して、農業に関する専門的知識、技能を身につけさせ、一般教養を高めて、新しい活力に満ちた社会を建設するため実業補習学校の一層の充実発展を図ることが国家的、社会的要請であった。
昭和10年実業補習学校と青年訓練所を廃止し、青年学校を一斉に発足させた。岩手県は県立六原青年道場に岩手県立青年学校教員養成所を設置した。修業年限は二ヶ年とし、生徒定数を一学年50名とした。
青年学校教員養成所に入学したものは、先ず六原青年道場に入所し三週間の短期訓練を終えねばならなかった。此の短期訓練証を手にし、はじめて青年学校教員養成所生として寮に入り生活を始めた。 短期訓所の三週間は午前五時に起床し、参拝、体操(やまとばたらき)・駆け足、朝食午前八時より午前の作業(開墾)講義、十二時昼食、午後は一時より作業(開墾)講義、午後五時参拝、五時三十分~六時夕食、八時三十分まで自習、八時三十分修道夜会、消灯九時という日課であり、移動は総べて駆け足となっていた。
このことからも、六原青年道場の「雄叫び」を青教生(青年学校教員養成所生)も体験していることが解る。したがって、青教生であった千田みさほさんが『六原道場の思い出』で語っている「雄叫び」は六原青年道場の「雄叫び」そのものであるということが確認できる。
さてこうなると次に生じる疑問は『青年学校』とは一体何なんだろうということである。
このことに関しては雑誌『キング』(昭和13年3月号、大日本雄辯會講談社)の中の
《5 「時事問題早わかり」》

<『キング』(昭和13年3月号、大日本雄辯會講談社)より>
には次のように書いてあった。
兵役法と青年学校
問……いよいよ兵役法が改正されるさうですネ。
答……陸軍の歩兵は、これから兵営に二年つとめることになります。細かくいふと一月一日に入営しまして、一年十ヶ月と二十日間訓練することになるのです。
問……そのわけは――。
答……いままでは歩兵は、他の兵科の人たちよりも訓練が簡単でありましたが、いろいろの兵器が出来たり、いはゆる近代戦となり、そのうへ各兵科を一緒にしたものともいふべきもので、他の兵科以上に仕事をせねばならぬからです。いままで青年学校を出て歩兵として入隊したものは六ヶ月早く除隊が出来ましたが、こんどは、それもやめることになります。やつぱり二ヶ年の間みつちり訓練を受けるのです。
問……その青年学校も、どうしてもやらねばならぬ義務教育に改めるといふではありませんか。
答……義務教育がいまの小学校六年では短いから、もつと延ばせといふ議論がやかましかつたのですが、こんどは、それを青年学校の方でやらうといふのです。やつぱり、こんどの事変がもとになつて考えられたといつてよいでせう。
問……そのわけは――。
答……戦地の第一線に立つ兵士のうちで青年学校を出たものが眼に見えて成績がよいのと、国内でも防護団としての働きぶりもよいので、軍部と文部省との間に青年学校を活用するといふことに話が進められたのです。
問……それでどういふことになるのですか。
答……いま文部省で考へてゐるのは、高等小学校なり中学校などにゆかないものは、――(それが青年学校に入るのですが、いま生徒は二百三十万人もあり、学校も一万七千もあります)――尋常高等小学校卒業後十二歳から十九歳までの間に、普通科二年(高等小学校)本科五年の青年学校教育を受けさすことにするのです。また、当分のうち、尋常小学を出ただけで十四歳未満のものは、普通科に入らすのです。とにかく、実務教育と実際教育とに力を入れ、それぞれの地方の状況や青年の境遇に合ふ教育をしようといふのです。
とあった。
したがって、「青年学校」とは簡単に言えば、勤労青年のための1939年~47年(昭和22)まで存続した義務性の定時制の学校だった。そしてそれはそれまでにあった2つの学校、農業に従事する青少年の教育機関である「実業補習学校」と軍事教練を主とした「青年訓練所」とを青年学校として統合したものだったようだ。
続き
 ”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPへ移る。
”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPへ移る。
前の
 ”加藤完治と戦争責任”のTOPに戻る
”加藤完治と戦争責任”のTOPに戻る
 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
 ”目次(続き)”へ移動する。
”目次(続き)”へ移動する。
 ”目次”へ移動する。
”目次”へ移動する。
以前”再び「雄叫び」について”において次のような写真を載せ
**********************************************************************************
【一〇 雄叫び】

ということで「雄叫び」のイメージがある程度できた。写真からはグラウンドを行進しながら歌などを歌っているようだ。もしかすると小冊子『雄叫び』の中にある歌などを声高に歌っていたのではなかろうか。
**********************************************************************************
と推測してみた。とはいえ、いまひとつ「雄叫び」というものがはっきり解らなかった。
ところがこの度『六原道場思い出の記』(千田みさほ著)という著書を手に入れることができ、嬉しいことにそこには「雄叫び」についての説明があった。
『朝の行事』の中でまず次のようなことを述べ
清掃された早朝の神社の前に太鼓の音と共に集合し、青教男子、農指生、長期生、短期生男子、次に女子の順で整列し、班長が当番の先生に人員報告をする。
その後、修祓に移る。先ず当番の先生が社前にすすみ、二拝二拍手の後祝詞をあげ、幣を振りその後納めて修祓を得る。ついで『君が代』斉唱と共に国旗掲揚、その後教育勅語奉読、全員参拝。この次に「雄叫び」に移る。
引き続き「雄叫び」について説明している。同著からそのまま引用すれば
『雄叫び』は、男子先輩の、力強い”建国の歌”の音頭に始まり、全員足踏みしながら、大合唱となり、男子と女子が二列ずつ併行して行進し、第一運動場に移行し、神話の、いざなぎ、いざなみのみことの故事に習って、男子は左、外廻りを、女子は右、内廻りを、合唱しながら、それぞれ大きな円を描いて進んで行った。”建国の歌”が終わると”植民の歌”が続けられた。…(中略)…
植民の歌の四番が終わる頃には、体操の出来る体系に間隔を離して、その場、足踏みとなり、合唱終了と共に雄叫びも終わった。
というように説明してあった。
したがって予想はほぼ正しかったようで、前掲の写真【一〇 雄叫び】はまさしくこの説明にあるような「雄叫び」の一場面であったのだった。
なお、”建国の歌”とか”植民の歌”については
《2 『雄叫び』(岩手県立青年学校教員養成所編、岩手県立青年学校教員養成所報国発行)》

《3 〃の目次》

の中にもあり、歌詞はそれぞれ
”建国の歌”
一
澎湃みなぎる青海原に
我等御祖の言の葉凝りて
御生れましたる豊秋津洲
朝日夕日の直照るところ
光明の国我等が日本
二
照る日の下に鋭鎌を握り
岩根木根立ち踏みさくみけむ
我等祖先の直進みてし
建国の御業仰ぐ尊し
宏遠の国我等が日本
三
懐古の念凝り建国の魂
吹気に集ふ健児我等
岩手の霊峰何をか教へ
北上の清流何をか語る
秀麗の国我等が日本
四
まがつひの雲湧き立ち昇り
世は常闇となり果てぬとも
見よわがしるべ明るき浄き
直き誠の力こもれり
信念の国我等が日本
五
天つ日かげを真面にかざし
世界の表に先立ち行かん
これぞ我等が尊き使命
行くては希望の光に満てり
正大の国我等が日本
”植民の歌”
一
萬世一系比ひなき
すめらみことを仰ぎつゝ
天涯萬里野に山に
荒地開きて敷島の
大和魂を植るこそ
日本男児の誉なれ
二
北海の果て樺太に
斧鉞入らざる森深く
北斗輝く蝦夷の地に
金波なびかぬ野は広し
金剛聳ゆる鶏林に
未墾の沃野吾を持つ
三
峻嶺雲衝く新高の
芭蕉の葉影草茂る
広漠千里満洲の
地平の果てに夕陽は赤く
興安嶺の森暗し
いざ立て健児いざ行かん
四
高鳴る胸の血潮もて
紅ひそめし日章旗
高き理想と信仰の
御旗かざして吾行かむ
東亜の天地黎明の
晨を告ぐる鐘ぞ鳴る
というように、雄々しいものだった。
ところで、この著者千田みさほさんは「青教生」であったという。すなわち、青年学校教員養成所生であったというが、青年学校教員養成所とは一体なんだっんだろうか。
同著には次のように書かれている。
青教生の中には、助教員を何年かした後、有資格者にと、入学してくる人もいて、年齢は十七歳から二十五歳までの開きがあった。…(略)…青教の二年の課程を終えると、県内の青年学校の教諭となり…(略)
ということは
青年学校教員養成所=青年学校の教員養成所
ということであろう。
因みに
《4『彗星の如く 岩手県青年学校教育の記録と回想』》

(済みません著者及び発行所調査中です)
には次のような事柄が書いてある。
青年学校は実業補習学校と青年訓練所の統合によって設立された青年教育制度である。
実業補習学校は、ほぼ例外なく地元の小学校に併設され、その小学校長が実業補習校の校長を兼務し、教師も殆ど小学校教員の兼務であった。このような学校事情の中で、師範学校制度がほぼ実業補習学校教育をも担当する教員養成の一端をになっていたのである。
明治26年に交付された実業補習学校規定により実業補習学校の専任教員の養成が提唱され、大正10年に「岩手県立実業補習学校教員養成所」が盛岡高等農林学校に併設された。
本来、実業補習学校は農山漁村の青少年を教育して、農業に関する専門的知識、技能を身につけさせ、一般教養を高めて、新しい活力に満ちた社会を建設するため実業補習学校の一層の充実発展を図ることが国家的、社会的要請であった。
昭和10年実業補習学校と青年訓練所を廃止し、青年学校を一斉に発足させた。岩手県は県立六原青年道場に岩手県立青年学校教員養成所を設置した。修業年限は二ヶ年とし、生徒定数を一学年50名とした。
青年学校教員養成所に入学したものは、先ず六原青年道場に入所し三週間の短期訓練を終えねばならなかった。此の短期訓練証を手にし、はじめて青年学校教員養成所生として寮に入り生活を始めた。 短期訓所の三週間は午前五時に起床し、参拝、体操(やまとばたらき)・駆け足、朝食午前八時より午前の作業(開墾)講義、十二時昼食、午後は一時より作業(開墾)講義、午後五時参拝、五時三十分~六時夕食、八時三十分まで自習、八時三十分修道夜会、消灯九時という日課であり、移動は総べて駆け足となっていた。
このことからも、六原青年道場の「雄叫び」を青教生(青年学校教員養成所生)も体験していることが解る。したがって、青教生であった千田みさほさんが『六原道場の思い出』で語っている「雄叫び」は六原青年道場の「雄叫び」そのものであるということが確認できる。
さてこうなると次に生じる疑問は『青年学校』とは一体何なんだろうということである。
このことに関しては雑誌『キング』(昭和13年3月号、大日本雄辯會講談社)の中の
《5 「時事問題早わかり」》

<『キング』(昭和13年3月号、大日本雄辯會講談社)より>
には次のように書いてあった。
兵役法と青年学校
問……いよいよ兵役法が改正されるさうですネ。
答……陸軍の歩兵は、これから兵営に二年つとめることになります。細かくいふと一月一日に入営しまして、一年十ヶ月と二十日間訓練することになるのです。
問……そのわけは――。
答……いままでは歩兵は、他の兵科の人たちよりも訓練が簡単でありましたが、いろいろの兵器が出来たり、いはゆる近代戦となり、そのうへ各兵科を一緒にしたものともいふべきもので、他の兵科以上に仕事をせねばならぬからです。いままで青年学校を出て歩兵として入隊したものは六ヶ月早く除隊が出来ましたが、こんどは、それもやめることになります。やつぱり二ヶ年の間みつちり訓練を受けるのです。
問……その青年学校も、どうしてもやらねばならぬ義務教育に改めるといふではありませんか。
答……義務教育がいまの小学校六年では短いから、もつと延ばせといふ議論がやかましかつたのですが、こんどは、それを青年学校の方でやらうといふのです。やつぱり、こんどの事変がもとになつて考えられたといつてよいでせう。
問……そのわけは――。
答……戦地の第一線に立つ兵士のうちで青年学校を出たものが眼に見えて成績がよいのと、国内でも防護団としての働きぶりもよいので、軍部と文部省との間に青年学校を活用するといふことに話が進められたのです。
問……それでどういふことになるのですか。
答……いま文部省で考へてゐるのは、高等小学校なり中学校などにゆかないものは、――(それが青年学校に入るのですが、いま生徒は二百三十万人もあり、学校も一万七千もあります)――尋常高等小学校卒業後十二歳から十九歳までの間に、普通科二年(高等小学校)本科五年の青年学校教育を受けさすことにするのです。また、当分のうち、尋常小学を出ただけで十四歳未満のものは、普通科に入らすのです。とにかく、実務教育と実際教育とに力を入れ、それぞれの地方の状況や青年の境遇に合ふ教育をしようといふのです。
とあった。
したがって、「青年学校」とは簡単に言えば、勤労青年のための1939年~47年(昭和22)まで存続した義務性の定時制の学校だった。そしてそれはそれまでにあった2つの学校、農業に従事する青少年の教育機関である「実業補習学校」と軍事教練を主とした「青年訓練所」とを青年学校として統合したものだったようだ。
続き
 ”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPへ移る。
”「岩手県国民高等学校」と賢治”のTOPへ移る。前の
 ”加藤完治と戦争責任”のTOPに戻る
”加藤完治と戦争責任”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。
”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。
”目次”へ移動する。

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます