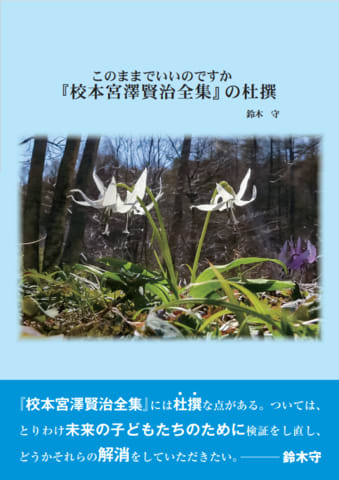
鈴木 ここまで、「杜撰」という視点から幾つか見てきたのだが、その典型があの「新発見」だと私は思っている。
吉田 たしかに。
荒木 そしてその「新発見」の「杜撰」さによって何が起こったか。賢治が生前、血縁以外の女性の中で最も世話になったのが高瀬露であるというのに、その露はとんでもない〈悪女〉にされていて、いわゆる〈高瀬露悪女伝説〉が全国に流布したことが否定出来ない。しかも、少し調べてみただけでも露はとてもそうとは言えなさそうだから、濡れ衣の可能性が大だ。
吉田 なぜ荒木はそう思うのだ。
荒木 それはほら、鈴木が『本統の賢治と本当の露』の中の111p~113pにこう書いているからだ。
それはまず、賢治の主治医だったとも言われているという佐藤隆房が、
よってこれらの証言から、露はしばしば下根子桜の宮澤家別宅を訪れており、賢治は露にいろいろと助けてもらっていたこと、露とはオープンで親密なよい関係にあったということが少なくとも導かれるということだ。
一方で露本人は、
君逝きて七度迎ふるこの冬は早池の峯に思ひこそ積め
師の君をしのび來りてこの一日心ゆくまで歌ふ語りぬ
というような、崇敬の念を抱きながら亡き賢治を偲ぶ歌を折に触れて詠んでいたことを『イーハトーヴォ第四號』(菊池暁輝編輯、宮澤賢治の會、昭和15年)等によって知ることができる。そしてもう一つ大事なことがあり、露は19歳の時に洗礼を受け、遠野に嫁ぐまでの11年間は花巻バプテスト教会に通い、結婚相手は神職であったのだが、夫が亡くなって後の昭和26年に遠野カトリック教会で洗礼を受け直し、50年の長きにわたって信仰生涯を歩み通した(雑賀信行著『宮沢賢治とクリスチャン花巻編』(雑賀編集工房)143p~)クリスチャンであったという。
したがってこれらのことから常識的に判断すれば、巷間流布している〈悪女・高瀬露〉はあやかしである蓋然性がかなり高い。
櫻の地人協會の、會員といふ程ではないが準會員といふ所位に、内田康子(〈註二十〉)さんといふ、たゞ一人の女性がありました。
内田さんは、村の小學校の先生でしたが、その小學校へ賢治さんが講演に行つたのが緣となつて、だんだん出入りするやうになつたのです。
來れば、どこの女性でもするやうに、その邊を掃除したり汚れ物を片付けたりしてくれるので、賢治さんも、これは便利と有難がつて、
「この頃は美しい會員が來て、いろいろ片付けてくれるのでとても助かるよ。」
と、集つてくる男の人達にいひました。〈『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年)175p~〉
と『宮澤賢治』で述べているからだ。さらに、宮澤賢治の弟清六も、内田さんは、村の小學校の先生でしたが、その小學校へ賢治さんが講演に行つたのが緣となつて、だんだん出入りするやうになつたのです。
來れば、どこの女性でもするやうに、その邊を掃除したり汚れ物を片付けたりしてくれるので、賢治さんも、これは便利と有難がつて、
「この頃は美しい會員が來て、いろいろ片付けてくれるのでとても助かるよ。」
と、集つてくる男の人達にいひました。〈『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年)175p~〉
白系ロシア人のパン屋が、花巻にきたことがあります。…(筆者略)…兄の所へいっしょにゆきました。兄はそのとき、二階にいました。…(筆者略)…二階には先客がひとりおりました。その先客は、Tさんという婦人の客でした。そこで四人で、レコードを聞きました。…(筆者略)…。レコードが終ると、Tさんがオルガンをひいて、ロシア人はハミングで讃美歌を歌いました。メロデーとオルガンがよく合うその不思議な調べを兄と私は、じっと聞いていました。〈『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)236p〉
と追想している。そして、下根子桜の宮澤家別宅に出入りしていてオルガンで讃美歌が弾けるイニシャルTの女性といえば高瀬露がいるし、露以外に当て嵌まる女性はいないから、「Tさん」とは露であることが判る。したがって、賢治はある時、下根子桜の宮澤家の別宅に露を招き入れて二人きりで二階にいた、と清六は実質的に証言していたということになるからだ。あるいはまた、 宮沢清六の話では、この歌は賢治から教わったもの、賢治は高瀬露から教えられたとのこと。〈『新校本宮澤賢治全集第六巻詩Ⅴ校異篇』(筑摩書房)225p〉
というわけで、賢治は露から歌(讃美歌)を教わっていたということも弟が証言していたことになるからだ。よってこれらの証言から、露はしばしば下根子桜の宮澤家別宅を訪れており、賢治は露にいろいろと助けてもらっていたこと、露とはオープンで親密なよい関係にあったということが少なくとも導かれるということだ。
一方で露本人は、
君逝きて七度迎ふるこの冬は早池の峯に思ひこそ積め
師の君をしのび來りてこの一日心ゆくまで歌ふ語りぬ
というような、崇敬の念を抱きながら亡き賢治を偲ぶ歌を折に触れて詠んでいたことを『イーハトーヴォ第四號』(菊池暁輝編輯、宮澤賢治の會、昭和15年)等によって知ることができる。そしてもう一つ大事なことがあり、露は19歳の時に洗礼を受け、遠野に嫁ぐまでの11年間は花巻バプテスト教会に通い、結婚相手は神職であったのだが、夫が亡くなって後の昭和26年に遠野カトリック教会で洗礼を受け直し、50年の長きにわたって信仰生涯を歩み通した(雑賀信行著『宮沢賢治とクリスチャン花巻編』(雑賀編集工房)143p~)クリスチャンであったという。
したがってこれらのことから常識的に判断すれば、巷間流布している〈悪女・高瀬露〉はあやかしである蓋然性がかなり高い。
吉田 要は、〈高瀬露悪女伝説〉は濡れ衣の可能性が極めて大であり、もしそうであるとするならばそれは人権問題だから、他のこととは違ってそれが重視される今の時代は特に放っておくわけにはいかないということだな。
荒木 ということだ。
吉田 ちなみに、賢治の主治医だったとも言われている佐藤隆房は、
櫻の地人協會の、會員といふ程ではないが準會員といふ所位に、内田康子(筆者註:高瀬露のこと)さんといふ、たゞ一人の女性がありました。…投稿者略…
來れば、どこの女性でもするやうに、その邊を掃除したり汚れ物を片付けたりしてくれるので、賢治さんも、これは便利と有難がつて、
「この頃は美しい會員が来て、いろいろ片付けてくれるのでとても助かるよ。」
と、集つてくる男の人達にいひました。〈『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年)175p〉
と述べていて、これに基づけば、露は賢治にとっては〈悪女〉どころかその逆だからな。來れば、どこの女性でもするやうに、その邊を掃除したり汚れ物を片付けたりしてくれるので、賢治さんも、これは便利と有難がつて、
「この頃は美しい會員が来て、いろいろ片付けてくれるのでとても助かるよ。」
と、集つてくる男の人達にいひました。〈『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年)175p〉
さらに、『新校本宮澤賢治全集第六巻詩Ⅴ校異篇』によれば、
この歌の原曲は…筆者略…「いづれのときかは」で、賢治が愛唱した讃美歌の一つである。宮沢清六の話では、この歌は賢治から教わったもの、賢治は高瀬露から教えられたとのこと。 〈『新校本 宮澤賢治全集第六巻詩Ⅴ校異篇』(筑摩書房)225p〉
ということだから、賢治は露から讃美歌を教わっていたということを、賢治の弟清六は証言していたことになる。また清六は、
私とロシア人は二階へ上ってゆきました。
二階には先客がひとりおりました。その先客は、Tさん(筆者註:高瀬露のこと)という婦人の客でした。そこで四人で、レコードを聞きました。…筆者略…。レコードが終ると、Tさんがオルガンをひいて、ロシア人はハミングで讃美歌を歌いました。メロデーとオルガンがよく合うその不思議な調べを兄と私は、じっと聞いていました。〈『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)236p〉
ということも証言している。二階には先客がひとりおりました。その先客は、Tさん(筆者註:高瀬露のこと)という婦人の客でした。そこで四人で、レコードを聞きました。…筆者略…。レコードが終ると、Tさんがオルガンをひいて、ロシア人はハミングで讃美歌を歌いました。メロデーとオルガンがよく合うその不思議な調べを兄と私は、じっと聞いていました。〈『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)236p〉
よって、これらの証言等から、賢治は露からとても世話になっていたということや、当時、賢治と露はオープンで親しい関係にあった、ということが導かれる。
鈴木 しかも雜賀信行氏によれば、露は一九二一年(一九歳の時)に洗礼を受け、遠野に嫁ぐまでの一一年間は花巻バプテスト教会に通い、結婚相手は神職であったのだが、夫が亡くなって後の一九五一年にカトリック遠野教会で洗礼を受け直し、「五〇年の長きにわたって信仰の生涯を歩み通した」クリスチャンであった(『宮沢賢治とクリスチャン 花巻編』(雜賀信行著、雜賀編集工房)143~147p)、という。
荒木 ということであればもはや、露が〈悪女〉であるとは常識的には考えにくいのに、なぜ殆どの賢治研究者は〈高瀬露悪女伝説〉を問題視しないのかな。
鈴木 そうなんだよな。賢治に関しては常識的におかしいところは、検証してみるとほぼ皆おかしいということを私は何度も痛感しているからな。
吉田 「義を見てせざるは勇なきなり」、ということかもな。
荒木 どういうこっちゃ?
吉田 賢治研究者は優秀な人が多いのだからこの伝説が濡れ衣だということに気づいていないはずがない。が実は、それを公にはしにくいという事情が裏に潜んでいる、ということが否定出来ないということだ。
荒木 たしかに、俺たちでさえもそのことに気づけるのだから、学者が気付かぬはずがないもんな。
そういえばそうそう、鈴木が『本統の賢治と本当の露』を出版した直後にとある学会がその学会員全員に、鈴木を個人攻撃をする文書を送付したこともあったしな。
鈴木 実は私もその時のことを思い出し、ちょっと身震がいした。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 「〝このままでいいのですか『校本全集』の杜撰〟の目次」へ移る。
「〝このままでいいのですか『校本全集』の杜撰〟の目次」へ移る。***********************************************************************************************************
《新刊案内》この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵教授が目の前で、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだが、そのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
と嘆いたことである。そして、私は定年後ここまでの16年間ほどそのことに関して追究してきた結果、それに対する私なりの答が出た。延いては、
小学校の国語教科書で、嘘かも知れない賢治終焉前日の面談をあたかも事実であるかの如くに教えている現実が今でもあるが、純真な子どもたちを騙している虞れのあるこのようなことをこのまま続けていていいのですか。もう止めていただきたい。
という課題があることを知ったので、 『校本宮澤賢治全集』には幾つかの杜撰な点があるから、とりわけ未来の子どもたちのために検証をし直し、どうかそれらの解消をしていただきたい。
と世に訴えたいという想いがふつふつと沸き起こってきたことが、今回の拙著出版の最大の理由である。しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感した。
まず、周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
きわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながらも道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。
と述べていることを私は思い出した。同時に、石井洋二郎氏が、 あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という、研究における方法論を教えてくれていることもである。すると、この基本を心掛けて取り組めばなんとかなるだろうという根拠のない自信が生まれ、歩き出すことにした。
そして歩いていると、ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているということを知った。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
そうして粘り強く歩き続けていたならば、私にも自分なりの賢治研究が出来た。しかも、それらは従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと嗤われそうなものが多かったのだが、そのような私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、私はその研究結果に対して自信を増している。ちなみに、私が検証出来た仮説に対して、現時点で反例を突きつけて下さった方はまだ誰一人いない。
そこで、私が今までに辿り着けた事柄を述べたのが、この拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます