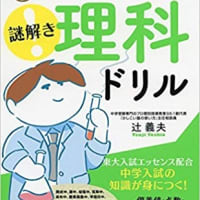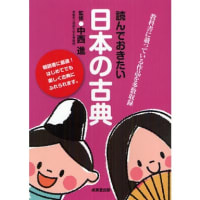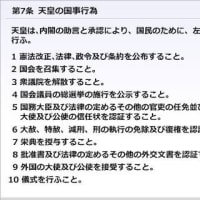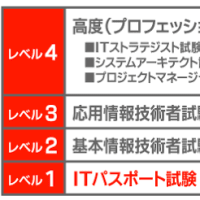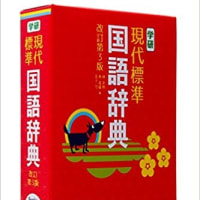文化庁による、2008年度「国語に関する世論調査」が、発表されました。解答は文末に。
問い;どの意味で使いますか?
(1)「時を分かたず」
いつも 14.1
すぐに 66.8
(2)「破天荒(はてんこう)」
誰も成し得なかったことをすること 16.9
豪快で大胆(だいたん)な様子 64.2
(3)「御(おん)の字」
大いにありがたい 38.5
一応、納得できる 52.4
(4)「敷居しきい)が高い」
相手に不義理などをしてしまい、行きにくい 42.1
高級過ぎたり上品過ぎたりして、入りにくい 45.6
(5)「手をこまねく」
何もせずに傍観(ぼうかん)している 40.1
準備して待ち構える 45.6
問い;どの言い方で使いますか?
(6)「チームや部署に指示を与え、指揮すること」
さい配を振る 28.6
さい配を振るう 58.4
(7)「目上の人に気に入られること」
お眼鏡にかなう 45.1
お目にかなう 39.5
(8)「よく分かるようにていねいに説明すること」
噛(か)んで含めるように 43.6
噛(か)んで含むように 39.7
塾長は、(1)と(4)の二つまちがっていました(/ω\)ハズカシー
調べてみると、中国の故事成語がもとになっていたり。
はてんこう【破天荒】唐の時代、荊州地方から官吏(公務員)登用試験の合格者が出ず、世の人はこれを天荒(凶作などで雑草の生い茂る様)と言っていた。やがて劉蛻(リュウゼイ)という人が合格し、「天荒を破った」と言われた故事に由来する。
しきい【敷居】門戸の内と外とを区別するために敷いた横木。部屋の境の戸・障子(しょうじ)・ふすまの下にあって、あけたてするための溝のついた横木。
しばらくあいさつなどに顔も出さず義理を欠いているため、門の前まで行ってもまたぎにくい様子を表しています。若い時はあまり使う状況はないと思いますが、年を重ね礼儀や義理が大事になってくると使う機会も増えますね。
小中高校生の国語学習の一環というだけでなく、大人の社会生活での知恵を学ぶ意味が大きいと思いました。正解率より、大人から子供へ伝えていくことが大事なのでしょう。(塾長)
解答;すべて、二択の上の方が正解です。数字は正答率(%)。
文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語に関する世論調査 | 平成20年度(PCサイト)
「8、カタカナ語の認知・意味の理解・使用」の結果も興味ひきますよ。
問い;どの意味で使いますか?
(1)「時を分かたず」
いつも 14.1
すぐに 66.8
(2)「破天荒(はてんこう)」
誰も成し得なかったことをすること 16.9
豪快で大胆(だいたん)な様子 64.2
(3)「御(おん)の字」
大いにありがたい 38.5
一応、納得できる 52.4
(4)「敷居しきい)が高い」
相手に不義理などをしてしまい、行きにくい 42.1
高級過ぎたり上品過ぎたりして、入りにくい 45.6
(5)「手をこまねく」
何もせずに傍観(ぼうかん)している 40.1
準備して待ち構える 45.6
問い;どの言い方で使いますか?
(6)「チームや部署に指示を与え、指揮すること」
さい配を振る 28.6
さい配を振るう 58.4
(7)「目上の人に気に入られること」
お眼鏡にかなう 45.1
お目にかなう 39.5
(8)「よく分かるようにていねいに説明すること」
噛(か)んで含めるように 43.6
噛(か)んで含むように 39.7
塾長は、(1)と(4)の二つまちがっていました(/ω\)ハズカシー
調べてみると、中国の故事成語がもとになっていたり。
はてんこう【破天荒】唐の時代、荊州地方から官吏(公務員)登用試験の合格者が出ず、世の人はこれを天荒(凶作などで雑草の生い茂る様)と言っていた。やがて劉蛻(リュウゼイ)という人が合格し、「天荒を破った」と言われた故事に由来する。
しきい【敷居】門戸の内と外とを区別するために敷いた横木。部屋の境の戸・障子(しょうじ)・ふすまの下にあって、あけたてするための溝のついた横木。
しばらくあいさつなどに顔も出さず義理を欠いているため、門の前まで行ってもまたぎにくい様子を表しています。若い時はあまり使う状況はないと思いますが、年を重ね礼儀や義理が大事になってくると使う機会も増えますね。
小中高校生の国語学習の一環というだけでなく、大人の社会生活での知恵を学ぶ意味が大きいと思いました。正解率より、大人から子供へ伝えていくことが大事なのでしょう。(塾長)
解答;すべて、二択の上の方が正解です。数字は正答率(%)。
文化庁 | 国語施策・日本語教育 | 国語に関する世論調査 | 平成20年度(PCサイト)
「8、カタカナ語の認知・意味の理解・使用」の結果も興味ひきますよ。