





師走の二十四日夕刻。半年間鍛えた操船を、身をもって試す時が来た。半七と筏職十名。 みのすけと強力百姓四名は、大船を、江戸に向けて釜石浦からまさに出航させるところであった。同時にはやばしりのよしは、飯能河原に走った。 船上ではみのすけたちが、足回りの手甲脚絆、黒装束、工具、食料の点検をしていた。こちらは大船の別動隊が総勢十五名。飯能河原の村からは頭の捨松、弥助ほか十七名。総勢で三十二名の、五年がかりの大部隊であった。訓練のおかげもあって、大船は穏やかな波をけって南下し、銚子沖を二十五日には超えた。
暮の二十八日夕刻。今日も江戸の町はよい天気だ。三之丞は稽古で汗を流し、牛込の道場から長屋まで戻り、井戸で洗い物をする。
「お師匠様。お帰りなさい」
「おうおう、はなと里ではないか。どこへでかけるのじゃ」
「はい かかの許しをえたので、二人で増上寺まで行くところよ」
年上の里が答える。
「もう夕の刻だ。二人きりなら、すぐに帰るのだぞ」
「はい。お師匠様」
と二人が手をつなぎ木戸を出るとすぐに、見慣れぬ男が、木戸を入り井戸端の三之丞をすり抜け、足早に北東のおいとの家に向かっていく。
・・・・・はて、おいとさんはまだ大黒屋のはずだが。届け物かな・・・
寺子屋に戻り居間で茶を飲んでいると、表から弥生の声がする。
「兄上 お帰りでございますか」
「今、稽古から帰ったところじゃが、よく参るのう。何用じゃな」
「お母上様からの書状を持ってまいりました。兄上の縁談ですよ。羽生家の娘御で、よいご縁ですから、すぐに返事をするようにとのおおせです。すぐに返事をしたいから、今晩、必ず築地の家に来るようにとのお言葉でございますよ」
「わかったが、まだわしにはその気はないのでのう。困ったな。丁寧にお断りはできぬものかな」
と母上の書状を傍らに置く。
何か気になることがあるようだ。弥生は兄のしぐさで分かるのだ。
「前にも話したがな。このところおいとさんのところに、飯能の村からよく人が出入りするのでな。先日は、川越で助けていただいた村医者方徳さん。今日もおいとさんが、大黒屋の務めのはずなのに。また知らぬ男が家に入って行った。届け物にしてはのう。男が帰らぬのもなあ・・・・不思議な気がしてな」
「それではおいとさんの家を訪ねて、男の方に・・どんな御用かとお聞きしてはいかがですか」
と弥生は澄まして言う。
「ま・・そこまで詮索するわけにはいくまいて」
「ところで母上へのご返事はいかがいたしましょう」
「お前から、まだその気がないようだと、母上に話してくれないものかのう」
「あら。いやでございますよう。兄上から今晩直接お話しくださいませな」
「ひとまずわたくしは築地に帰ります。今宵、必ずおいでくださいませよ」
それから一刻。新橋の金春湯屋に出向き、ゆっくり湯につかった三之丞は、帰りに店じまいした煮売りやおみよの店によって、頼んでおいた野菜の煮しめとイワシのめざしを受け取ると、遅い夕餉をゆっくりと食べ終わった。明日の子供たちへの手習いの準備も終わり、床をのべようとしていた。時はすでに子の刻に近い。入口をたたく音が聞こえた。
「兄上、兄上。まだお休み前ですか」
弥生の声がする。外は漆黒の闇だ。
「なんだこんなに遅く・・一人でまた参ったのか」
「母上がどうしても、今晩中でとお待ちでございます。どうしても連れてこいとのおおせでございますよ」
苦笑しながら三之丞は袴をはいた。
二人が外に出たその時・・三乃丞が門口で立ち止まり、ふーと天を仰ぎ見るとじっと立ち止まったままであった。
鋭い直感が三之丞を貫いたのだ。前にもしばしばこのような兄の直感に驚かされた弥生は・・思わず、
「いかん。この辺りで何か大事が起こるぞ。弥生はしばらくここにおれ」 そういうと、井戸端から向こうの長屋の端まで確かめに行った。北西の角のおいとの家の方向から、黒い影が飛び出し木戸へと駆け抜ける。
「弥生。今の男を追うぞ。大丈夫か」
その時黒い影の男は、木戸を大きく飛び上がり、通りを新橋方向に走る。
「兄上。何者でしょう。おいとさんの家からですね!」
三之丞と弥生は新橋方向に宇田川町から柴井町へと、男の後を追って走る。右に浜御殿と松平肥後守屋敷。露月町の角まで来ると、三之丞は立ち止まり、無言で姿勢を低くしろと弥生に合図した。
先ほどの男の影は見えない。と、 その時、浜御殿の海の方角から十数名の黒装束の賊が、西の源助町の方向に、疾風のような速さで走り抜ける。西の方角からも、別の十数名の黒装束の男たちが、あっというまに源助町の大黒屋の前で合流する。一団は勝手口に回り込み、大黒屋の屋敷内に消えた。くらい静寂だ。
「どうするべきか」
三之丞と弥生が、南町奉行所に走ろうとしたその時、三十数名の黒装束の賊たちは戻って、三丈間隔ほどで、浜御殿横の海に向かって走る。その先には大船が待ち構えていた。
「なんと準備の良いことだ!」
二人は驚いた。大黒屋からは、千両箱が手渡しで三十数名に引き継がれ、大船にあっという間に入ってゆく。猶予はない。まことに驚くはやわざだ。大黒屋の店の者たちはなんとしたことか。
「弥生。わしはあの大船の行く先を見届けねばならん。江戸湾に入ったからには、海から千住の河口か、西なら三浦から、伊豆半島方向に向かうだろう。わしの勘では千住方向だ。深夜だが、そなたは直ちに南町奉行所にいきさつを届け出ろ。築地の家から馬を用意し、千住の河口に向かってくれ。あの大船は河口口までしか入れんだろう。多分積み替えを準備していると思われる。頼んだぞ」
三之丞は東の両国方向に向けて走る。
「兄上。お気をつけて、相手は三十数名と思われますので!」
と声をかけると、新橋から数寄屋橋の南町奉行所へ、弥生も漆黒の闇を走った。
この疾風のーーいただきーーから一刻前のことであった。
西川の捨松は、増上寺方向から師走の寒風の中を二十名ほどで芝、源助町の大黒屋に向かって、音もたてずに走り着いていた。三十数名で勝手口から一階の店内に入る。夕餉の後か十名ほどが眠りこけ、ぐったりしていた。その中には、手引きのおいともいた。奥の店主夫婦の寝間に回ってみると、ここでも夫婦は昏睡中。まことに見事な薬草の効き目であった。かねてのつなぎのとおり、化粧棚の三段目から本蔵のカギも出てきた。
「予定どうりじゃ。皆の者。千両箱を、大船まで引継ぎで渡すのだ」
泥棒村の三十数名の賊たちは一気に店から大船まで走った。そして千両箱が、次々に大船へと運び入れられた。半時もかからない五年準備の早業であった。
人の命も殺めず、女子供も犯さず、本蔵から、二百箱近い千両箱の内、きっちり百箱ーーーいただいたーーーというわけであった。
「予定どうりであったな。おいとも、よく辛抱して成し遂げてくれた。さあ皆。大船に引き上げだ。千住でもう一仕事、残っておるからのう」と捨松。
三之丞は師走の闇を両国橋をぬけ、三ノ輪から千住に向けて走る。芝の江戸湾から大船で北を目指すなら、まずは千住の河口であろうと直感が告げていた。
千住の宿場を超え大橋を渡る。右は荒川、大川から江戸市中へ。左は千住の河口へ向かう土手であった。暗闇の向こうから海のざわめきが聞こえてきた。 いた! 大船は砂州の先に、すでに係留されていた。下には小舟が四艘。まさにいま、黒装束を脱いだ屈強の男たちが、千両箱を小舟におろしている。薄い月明かりの先で、頭と思われる男が声をかけていた。土手の右側に杉林があり、小さな地蔵堂があった。地蔵堂に姿を隠し、船の行方を見定める。宿場の方角から、馬に乗った弥生がやってくる。朝明けに、近づく影が大きくなる。
「おい ここだ」
三乃丞が一声かける。弥生は地蔵堂の蔭の柱に馬をつなぐ。
「兄上。ここでしたか。大船から、あの四艘に荷下ろしして、どこに向かうつもりでしょうか。南町奉行は二手に分かれ、西は東海道三浦方面と、こちら東は千住から銚子方向に向かう手筈ですが、到着は明け方になりましょう」
「それまでに、行き先を確かめねばならぬな。四艘が川を上り始めたぞ。われらは二人だけ。向こうは数十名の屈強な男どもだ。うかつなことはできんな。まずは悟られぬように、船を追って、奴らの拠点を突き止めねばならん」
「兄上の縁談話が・・とんだことになりましたね。父上も母上も、必死で止めましたが、概略だけ話して馬で飛んでまいりました」
気負いたつ弥生。「この馬で、賊どもを追うことができる。一人ではとてもな。しかし弥生。今後、無理はいかんぞ。腕に覚えがあろうとも、多勢に無勢であるからな」
うっすらとした明かりの中を、四艘が北千住から荒川をさかのぼる。漕ぎ手は、熟練のようで船足は相当に早い。川越からさらに入間川上流に入ってゆく。やがて川が二筋に別れ、入間川本流から右手の飯能方向に入る。土手沿いをわずかな提灯の光で、馬上は前が三之丞、後ろが弥生であった。あたりは川越藩の所領であったろう。しばらく進むと入間川が川上から大きく蛇行する地点。 飯能河原で四艘の船は係留し、千両箱を、河原の横の広場に降ろし積み上げた。あたりは、朝のひかりが立ち始めている。土手の手前で、馬から降りた二人はその様子をうかがう。さてどうしたものだろうか。
「思いの外にうまく運んだな。さて最後のの仕事じゃ。皆頑張っておくれ」 広場の奥には杉、檜が筏としてにいつでも組める状態で大量に置いてある。百姓強力みのすけの合図で、十人の屈強な男どもが、奥まった個所の杉や檜を運び出す。
ーーなんとその地点には、鉄の板で頑丈に入口を覆った竪穴の入口が現れたではないかーー
筏職の男も加わり千両箱、百箱はあっという間に地下に運ばれた。
あとはまた杉、檜で入口をすっかり覆い、その上にまた大量の杉、檜を載せた。
「さて。これで良し。この百箱と、ためておいた百箱。合計二百箱あればここ、五年は持つであろうな」
頭の西川の捨松は満足そうだ。
「当分は大丈夫でしょう。うまくいきましたね。五年間の準備が」
補佐の弥助も満足げにうなずく。
「では弥助さん。皆を帰しましょう。明日からはまた・・今までどうり平穏に西川材の仕事に精を出してな・・・・」
いつもの村人にかえって皆が家に戻る。
「まあ、ともかくも、この不思議な村の内容を調べねばなるまい」
驚く三之丞。
「まるで夢のような・・・・・村の男たちがほとんど大泥棒んて・・」
弥生も茫然とつぶやく。二人は頭と思しき男の後をそっと追う。
ーー後ろから人の気配を察知しながらも、捨松はゆっくりした足取りで、落ち着き払って左手奥の、やや大きめの百姓家に入っていったーー
「ここは多勢に無勢。われら二人ではいかんともしがたい」
百姓屋の入り口脇、薪を積んだ一角で、二人は中の様子を探ろうと・・その時・・・・・・
「こんなに朝のはようから何かご用かな」落ち着いた声だ。
しまった。きずかれたようだ。さすがに勘の鋭い男であった。
二人はじっとしばらく無言。飯能河原の宵が明けようとしていた。
「ま。そこでは、寒いじゃろうて。おはいり」
二人は迷ってまた無言。
その時三之丞の直感が頭を貫いた。目顔で弥生に合図を送ると扉を開けた。
大きな土間と左右は、何段もの棚が並び道具類が整然と詰まっている。その正面に囲炉裏が切ってあり、正面に白髪の老人がこちらを凝視している。再び無言。
「そこへお座り。若衆。おお、おう。凛々しい娘さんも一緒かな」
優しい言葉とは別で、二人を見定めるしもぶくれの顔の瞳の光はまことに鋭い。
危害は加えられないと三之丞の直感が告げていた。意を決して、
「今宵。芝、大黒屋から大船で千住河口へ。積み替え荒川、入間、そしてここ飯能河原まで、すべて見届けましたぞ。ま。 芝での偶然からですが。まことに驚いた大泥棒で言いようもない」
弥生もうなずく。捨松は依然二人を凝視して品定めであったが、彼にも直感があった。わきまえのある若者であろうと。囲炉裏の炭火をおこし、土瓶の湯を茶入れに注ぐと、二人に差し出す。
「それはそれは。すべて見られてしまっては、観念せねばならんかのう」
「整然たる所業は、見事と言わざるは得ないが、泥棒は泥棒。このままにしておくわけにはいかんだろう。まもなく、江戸から奉行一行が来る手筈をしてある。ここは神妙にする方がいいのでは」
ゆっくり毅然と三之丞。
「そうか。奉行たちが来るまでに間があるならば、少しわしの話も聞いてもらおうかの。少し長くなるで、ゆっくり茶で、手足を温めて聞いておくれ」
ーー信頼せよと直感が告げた捨松はゆっくりと村のいきさつを話し始めたーー
ーー自分は東北、釜石浦の生まれであること。漁師の息子であったが海よりも山や樹木が好きであること。秩父のこの山中に、良質な杉やヒノキが豊富にあること。四十年前から東北一円の飢饉で悲惨な暮らしの農民や漁民と、この地に移り住んだこと。二十数年前からここ飯能、川越、深谷、熊谷などの洪水や飢饉での悲惨な生活を見かね、「いただき」を始めたこと。そして今宵の五年がかりの、芝大黒屋での顛末。今回を含めこの村には千両箱が二百あること。これで当分数年は近隣・近郊を助けることが可能なこと。そして・・・・すべては自分一人の責任であって、村人は従わざるを得なかったであろうことーー
話し終わると、捨松はほっとした表情で二人を見た。
「あなたの話は承った。同情の余地もあるが、それと犯した罪は別であろう」
「それは覚悟はできているさ。ただ村の女子供や若衆たちは、何とか軽い裁きというわけにはいかんものかの」
弥生も小さくうなずいている。
「できる限りの口添えはしてみよう」
三之丞もそういうほかはなかった。
夜が明けた。南町奉行所からは与力服部采女之介を頭に与力三名、同心三名が村に到着した。服部は御家人の出であった。三之丞は昨晩からこの明け方までの顛末、また頭の捨松の話など詳細に報告する。
服部は落ち着いた大柄、で顔の小さな心きく与力であった。川越藩への応援も頭をよぎったようであったが、今宵の主犯捨松と弥助。他数名の主だった男、合計五名を捕縛し、奉行所に引き立てることとした。ほかの村の者たちは追って沙汰があることを告げる。
「弥生。馬で。そなたは直ちに兄上と父上に、事の次第を知らせなさい」
その時三之丞の頭をよぎったのは、ことの重大さと、隠居とはいえ父と柳沢吉保公との関係であった。奉行から老中には即刻報告が行くであろうことも。
「兄上。それではお先に。お気をつけて」
火急を悟った弥生でもあった。
築地の屋敷につくと直ちに弥生は二人の兄上と父の居間へと急いだ
「何。千両箱が今宵で百箱。村には二百はあろうと。芝の大黒屋といえば綿糸問屋でも屈指の大店。一人も傷つけずにし遂げただと。大事じゃ!」
普段は物静かな父が真剣なまなざしで一瞬考え、言った。
「柳沢公のところへ参るぞ。太郎左衛門。弥生も同行せよ。次郎左衛門は屋敷でわれらが連絡をまて」
まだまだ衰えていない左衛門であった。
明けの四つ。常盤橋の柳沢屋敷では吉保が登城に備え、腰元の介添えで召し換えの最中であった。
「なに。朝はようから菊池が息子、娘と参ったと。火急とな。よしこのままでよいからこの間にとおせ」
直ちに着替えの間に三人が平伏した。
「菊池殿。朝はようから何事じゃ。おうおう。そなたが娘の弥生殿か。また凛々しいお姿じゃな。剣術のほうも相当と聞いて居るが」と吉保。
「殿。朝はようから、ご登城の折にまことに失礼仕りますが・・」
と事の次第を述べた。
「弥生。付け足すことはないか」弥生は平伏のままであった。
「む。さようなことが・・・・千両箱で二百か。おそれいったな」
じっと庭の先を凝視していた。考え事があるようだ。三人は黙ったままだ。
「あいわかった。登城して老中、奉行からも話があるだろうて。大儀であった」
江戸城本丸。通称大城では明八つ。将軍綱吉の執務開始の時間であった。
平伏する吉保。綱吉の機嫌は普通だなと顔色から判断すると、大黒屋の昨夜の件を順を追って話し始めた。
「・・・・という次第でございます。まことに恐れ入った大泥棒。泥棒村でございます。が・・しかし飯能の河原の村にはなんと二百箱の千両箱がございます。・・・・・・・・・そのほとんど百五十箱を差し出させてはいかがでしょうか。もちろん頭と主だったもの数名は捕縛いたしておりますれば・・処罰することはできますが。村内の女子供 若衆はなんとか助けてやるわけには・・・・・・・」
「なに。柳沢。御政道を曲げろと申しておるのか。まことに不届きな奴らだ。それに差し出させるとはどうゆうことだ!」
「は。恐れながら・・・・海に運搬中の捕り物で、賊たちが箱をすべて江戸湾に沈めてしまったという次第では・・・・・」
上目で御上をうかがう吉保。
「大黒屋に全額返却せぬのか。それこそ、われらが大泥棒ではないか!」
「御上。大黒屋はまだまだ千両箱が百箱以上残りおり、傷ついたものとて一人もなく立派に立ち直りましょう」
「それに・・・・」
「なんだ。ほかにもあるのか」
「勘定方が苦労いたしております。御上もご存じのように、このところ金のひっ迫で、小判、大判ともに鋳造がままなりませぬ。ご老中から建白の改鋳の儀にも、この百数十箱は重要と・・・・・お恐れながらでございます・・」
じっと黙る綱吉。その時奥から猫が走り、綱吉の膝に乗る。
「柳沢。そちも・・・・・くせものよのう。ま。あいわかった。老中とよしなに。くれぐれも事件の尾を引かぬようにな。川越藩にもな」
と綱吉。
夕刻柳沢がいったん下城し屋敷に戻ると、菊池家の三人が待っていた。
「お帰りなさいませ。奥方様から昼餉をごちそうになり、お待ちしておりました。して、飯能の件は」
遠慮がちに聞く菊池左衛門に、
「おう。そちらの急報のおかげでな、南町奉行飛騨ノ守と老中から相談を受けてな・・ある提案をしたさ。ま。ここからは内聞にな。捕えた頭の捨松と奉行のあいだでな、百五十箱は御政道のために、代わりに、頭と数名の男の島流しで他は穏便に・・・いうことになった。捨松はなかなかの男であったそうな。飛騨ノ守も、戻って褒めておったは」
面長の顔で笑う吉保であった。
「それはそれは、間に合ってようございました」
「そちらのおかげじゃな。よい子息、娘御を持たれたものよ」
菊池家の三名は深く平伏して屋敷を辞去した。捨松は八丈島へ長く十年。副頭格の弥助が三宅島に五年、半七、みのすけが神津島に二年の流しと決まった。百五十箱は幕府の金座に運ばれた。表向きは賊を船で追う中で、百の箱は江戸湾に沈められた・・ということになっていた。主だった賊どもが島流しから帰った後、また何事かが仕組まれても・・それはその時のこと。われらの時代ではないわ。柳沢は割り切って御政道を考えていた。いいもわるいもそれが政治とゆうものかもしれなかった。
大晦日の煮売りやおみよ店。菊池家の兄弟の忘年会であった。長男太郎左衛門、次男次郎左衛門、そして三之丞と弥生。店奥の飯机で、珍しい四兄弟の会食でもあった。小松菜の煮びたし、たこと里芋の煮もの、マグロのねぎま鍋からは、いい匂いと湯気が上がっている。
「いやあ。このようなものがいただけて。このたこと芋はうまい」と次郎。
「三之丞。お手柄であったな。そちのおかげで普請頭を命ぜられたは。また、お奉行からいただいた酒もある」
太郎左衛門が剣菱の樽から酒を三之丞に注ぐ。
「それにしても村人の多くが救われましてございますね」と弥生。
おみよが入ってくる。満面笑顔を絶やさない。
「さあさあ。お話はそのくらいにして。鮪もこうして、根深と煮合わせるとおいしくいただけますよ」
と鍋を皆に勧める。四人は、剣菱を冷で茶碗でやりながら、湯気の立つねぎま鍋に箸を出す。
「それにしても 兄上の縁談がまたお流れですね」
弥生が笑う。
「まずは兄上たちであろう。順番というものがあるからな」と三之丞。
「いや。三之丞。遠慮はいらんぞ。母上は、まずそちと次郎を、何より気にかけておられる。そうじゃた。弥生もな」
と太郎左衛門。
「太郎殿も家督で長男ですから・・まずはお先に」
「弥生 そちはどうなんだ」
酒の勢いで次郎座衛門んが聞いた。
「兄上様方がいかれてから・・まだまだ、よいご縁もごいませんし」
その時、北の方角から増上寺百八つの鐘が寒空に響き始めた。
二年後の皐月、菖蒲の薫る入間川を、おいとと半七の祝言に赴く三之丞、弥生の姿が小舟の上にあった。
完










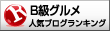














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます