ゴールデンウィークまっただ中ですが、いかがお過ごしでしょうか?
今年はコロナの影響でアウトドア系の趣味をサボっていたため体力が激落ちしており、ぼちぼちあちこち歩いていこうかと思っていたのですが、微妙に天気が悪いために結局山歩きではなく街歩きしかできておりません。今日から5日まで天気が良さそうなので、5日にでも久しぶりにそんなにキツくない山っぽいところでも歩きに行きますかね。
それはそれとして、年末年始に出かけてきた話がまだ残っているので、連休を活かして片づけていくことにします。
青春18きっぷを利用することを考えたとき、まず思いついたのが房総半島一周です。ただ、どこへ行くかというのがちょっと問題で、山登りでも良かったのですが、房総半島でそんなにキツくない山を探すと、鋸山とか、富山、伊予ヶ岳など、割と東京に近いエリアになってしまい、一周するまで行かないんですよね。
そこで、割と路線に近くて房総半島の奥の方まで行ける目的地と言うことで、館山市にある館山城と、勝浦市にある勝浦城に行ってきました。
まずは館山城へ。
館山城は安房里見氏の居城として、1580年に築城されます。その頃里見氏は、北条氏と組んだり、豊臣氏に近づいたりして、房総半島で勢力争いを繰り広げていました。一時は安房から上総、下総の一部までを勢力圏に納めます。
しかし、秀吉の小田原攻めには参加したものの、そのどさくさに紛れて領地拡大の戦を起こしたために秀吉の不興を買い、結局領地は安房一国まで減らされてしまいます。
その際に家康にとりなしてもらったことから、以降、里見氏は徳川に近づくことになります。関ヶ原の戦いにも東軍として参加し、常陸の領地を加増されて12万2千石の大名となり、当主・里見義康は館山藩の初代藩主となります。
しかしながら、二代藩主・里見忠義は、大久保忠隣の孫娘を正室に迎えていたため、大久保忠隣の改易に巻き込まれて安房を没収され、伯耆倉吉に転封となってしまいます。その後忠義は29歳で死去。跡取りの無かった里見家は断絶してしまいます。
忠義の転封後の館山藩は取り潰しとなり、その領地は一部が天領になったり、他藩の飛び地になったりしてバラバラに。館山城も廃城となってしまいました。
館山城へは、JR内房線の館山駅から、南へ2㎞弱ほど歩いていきます。

汐入川を渡ると丘の上に天守が見えます。
千葉県は高い山が無いことで有名なのですが、館山城は平地の中で一段高くなっている場所に築かれていることがわかります。

現在の館山城跡は、城山公園として整備されています。
まずはまっすぐ天守を目指しましょう。

舗装されていますが、そこそこ急な坂道を登っていきます。
どのくらい急かと言うと、地元の中学生や高校生が、部活で坂道ダッシュをしに来るくらい急です。部活に熱心なのはいいけど、こういう人の多いところでやらないで欲しいなぁ。

公園内はよく整備されており、いろんなルートが存在します。本当はのんびりぐるっと回るつもりだったのですが、舗装路は中学生の集団がダッシュしていて邪魔くさかったので、脇の階段を登っていきます。

天守のある本郭に到着。ここまで結構急な坂道でした。
公園内はかなり良く整備されているので歩きやすいのですが、整備されすぎていて、当時の縄張りみたいなものはよくわからなかったりするんですよね。しかし他のサイトで確認した館山城の縄張りと比較してみると、当時の郭跡みたいな場所はそれなりに残っていたようで、郭っぽい場所は今見ても大体確認することができるようです。


天守の手前からは、館山市内を一望することができます。
この日は朝から曇っていて、眺望はあまり良くありませんでしたけどね。

この場所は、恋人の聖地、また、なぜか128景あることで有名な関東の富士見100景にも選ばれています。

一番高い位置に立っているのが、館山城の天守。ただしこれは模擬天守で、実際に天守が立っていたという記録は無いそうです。
ここはふもとにある館山市立博物館の分館となっています。

本郭の近くには、茶室のある日本庭園もあります。

この後、さらに南の方へ向かう予定だったのですが、道を間違えて入ってきた北の方へ下りてしまいました。

仕方がないので、先に北側のふもとにある、館山市立博物館へ行きました。
博物館では安房里見氏の歴史に関する展示のほかに、一般的な漁師の家の再現など、地域の生活の様子などが展示されていました。

博物館を出た後、1回目とはなるべく違う道をあるきつつ、また天守を目指します。

天守付近には浅間神社もあります。
館山市立博物館の半券で、天守にある分館にも入ることができます。
分館は、南総里見八犬伝に関する資料が展示されています。江戸時代に出版された書籍類や、NHKで放映された人形劇「新八犬伝」の人形や映像などがありました。
途中の階(2階?)だけは別料金で、館山芸術大使であり、NHKの人形劇「新・三銃士」のキャラクターデザインを担当した井上文太の展覧会が開催されていました。別料金だったので入りませんでしたけど。
そして、最上階にある展望台から、館山市を一望することができます。





少し晴れ間も見えてきたので、最初は見えなかった富士山も見ることができました。

改めて、日差しの中の天守。
次に、天守から南へ向かいます。
北側は傾斜が急なのですが、南側はやや緩やかになっており、郭や館などは南側に多く配置されていたようですね。

南にあるのは万葉の径というエリア。

植えられている植物の前に、その植物を詠んだ万葉集の歌が添えられています。

とても雅な試みだと思うのですが、この看板はすげー大量に設置されているので、さすがに全部読むことはできませんでした。

その奥には八遺臣の墓があります。
八遺臣とは、前述したように改易させられて伯耆で亡くなった里見忠義に殉じ、後を追った八人の家臣のことです。その氏名は不明なのですが、後にその遺骨が分骨され、密かに館山まで運ばれて埋葬されたのがこの場所なのだそうです。
一説には、この八遺臣が南総里見八犬伝の八犬士のモデルになったとも言われています。

ここまではよく整備されていた歩きやすい道だったのですが、八遺臣の墓へ向かう道はちょっと山道っぽくなっています。

ある程度下ったところに、八遺臣の墓がひっそりと佇んでいました。


少し戻ったところに、館山藩初代藩主・里見義康の御殿跡があります。ここが館山城の政の中心だったようです。
建物のあった場所に礎石のようなものが埋められていますが、それは建物の位置が分かりやすいように埋められたもので、実際には礎石を用いた建物ではなかったそうです。

その上には梅林があります。
この写真ではわかりにくいかもしれませんけど、義康御殿、梅林、万葉の径、本郭と、明確に高低差がつけられており、それぞれが郭になっていたのだろうなと思います。


天守付近に置いてある、自動販売機。自販機も館山城仕様になっていますです。

最後に、帰り際に駐車場から望む館山城天守です。
館山駅に戻る前にもう一ヶ所、海沿いにある「渚の駅たてやま」にある、館山市立博物館のもう一つの分館・渚の博物館に行ってきました。

館山おさかな大使であり、渚の駅たてやまの名誉駅長でもあるさかなクンのイラストが建物に大きく描かれています。

入り口には、館山がアニメ「戦翼のシグリドリーヴァ」の聖地であることをPRした看板が立てられていました。シグルドリーヴァは見ていなかったのでよくわかりませんけど。って言うか、基本アニメはとりあえず1話はチェックするんですけど、切った記憶も無いんだよなぁ。
千葉県のご当地アニメと言えば、「輪廻のラグランジェ」の方が印象深いです。
中にはさかなクンの手によるイラストや立体物が大量に展示されているスペースをはじめ、漁船や網、針、銛などの釣り具、衣類、漁師の家の復元など、館山の漁業に関する展示、さらには企画展で館山港に関する写真などが展示されていました。
ここは無料で入れるのですが、無料の割には内容が盛りだくさんで、かなり楽しむことができました。

建物の裏にもさかなクンのイラストが。


渚の博物館の裏には、海に長く堤防が伸びているので、ちょっと歩いてみました。
この頃にはだいぶ晴れてきました。電車の時間まで少し余裕があったので、のんびりと海を満喫します。

工事中のため、一番奥までは行けませんでした。今はもう終わっているのかな?

堤防から見上げる館山城です。
館山城は意外と立体感があって、なかなか歩きごたえがありました。周囲はほぼ平野部になっているので、防御能力もそれなりにありそうです。博物館もあるので、歴史を学ぶこともできますしね。
ただ、ひとつ注文を付けるとすれば、館山城の縄張りを示す資料をどこかに用意しておいて欲しかったという点ですかね。どこが郭でどこが堀切でどこに門があって、などがまとめられていると、今でも地形的には割と分かりやすい形で残っているので、歩く際にもとても分かりやすかったと思います。
この後は内房線をさらに東へ移動。途中から外房線に切り替わり、勝浦市の勝浦城を目指します。
今年はコロナの影響でアウトドア系の趣味をサボっていたため体力が激落ちしており、ぼちぼちあちこち歩いていこうかと思っていたのですが、微妙に天気が悪いために結局山歩きではなく街歩きしかできておりません。今日から5日まで天気が良さそうなので、5日にでも久しぶりにそんなにキツくない山っぽいところでも歩きに行きますかね。
それはそれとして、年末年始に出かけてきた話がまだ残っているので、連休を活かして片づけていくことにします。
青春18きっぷを利用することを考えたとき、まず思いついたのが房総半島一周です。ただ、どこへ行くかというのがちょっと問題で、山登りでも良かったのですが、房総半島でそんなにキツくない山を探すと、鋸山とか、富山、伊予ヶ岳など、割と東京に近いエリアになってしまい、一周するまで行かないんですよね。
そこで、割と路線に近くて房総半島の奥の方まで行ける目的地と言うことで、館山市にある館山城と、勝浦市にある勝浦城に行ってきました。
まずは館山城へ。
館山城は安房里見氏の居城として、1580年に築城されます。その頃里見氏は、北条氏と組んだり、豊臣氏に近づいたりして、房総半島で勢力争いを繰り広げていました。一時は安房から上総、下総の一部までを勢力圏に納めます。
しかし、秀吉の小田原攻めには参加したものの、そのどさくさに紛れて領地拡大の戦を起こしたために秀吉の不興を買い、結局領地は安房一国まで減らされてしまいます。
その際に家康にとりなしてもらったことから、以降、里見氏は徳川に近づくことになります。関ヶ原の戦いにも東軍として参加し、常陸の領地を加増されて12万2千石の大名となり、当主・里見義康は館山藩の初代藩主となります。
しかしながら、二代藩主・里見忠義は、大久保忠隣の孫娘を正室に迎えていたため、大久保忠隣の改易に巻き込まれて安房を没収され、伯耆倉吉に転封となってしまいます。その後忠義は29歳で死去。跡取りの無かった里見家は断絶してしまいます。
忠義の転封後の館山藩は取り潰しとなり、その領地は一部が天領になったり、他藩の飛び地になったりしてバラバラに。館山城も廃城となってしまいました。
館山城へは、JR内房線の館山駅から、南へ2㎞弱ほど歩いていきます。

汐入川を渡ると丘の上に天守が見えます。
千葉県は高い山が無いことで有名なのですが、館山城は平地の中で一段高くなっている場所に築かれていることがわかります。

現在の館山城跡は、城山公園として整備されています。
まずはまっすぐ天守を目指しましょう。

舗装されていますが、そこそこ急な坂道を登っていきます。
どのくらい急かと言うと、地元の中学生や高校生が、部活で坂道ダッシュをしに来るくらい急です。部活に熱心なのはいいけど、こういう人の多いところでやらないで欲しいなぁ。

公園内はよく整備されており、いろんなルートが存在します。本当はのんびりぐるっと回るつもりだったのですが、舗装路は中学生の集団がダッシュしていて邪魔くさかったので、脇の階段を登っていきます。

天守のある本郭に到着。ここまで結構急な坂道でした。
公園内はかなり良く整備されているので歩きやすいのですが、整備されすぎていて、当時の縄張りみたいなものはよくわからなかったりするんですよね。しかし他のサイトで確認した館山城の縄張りと比較してみると、当時の郭跡みたいな場所はそれなりに残っていたようで、郭っぽい場所は今見ても大体確認することができるようです。


天守の手前からは、館山市内を一望することができます。
この日は朝から曇っていて、眺望はあまり良くありませんでしたけどね。

この場所は、恋人の聖地、また、なぜか128景あることで有名な関東の富士見100景にも選ばれています。

一番高い位置に立っているのが、館山城の天守。ただしこれは模擬天守で、実際に天守が立っていたという記録は無いそうです。
ここはふもとにある館山市立博物館の分館となっています。

本郭の近くには、茶室のある日本庭園もあります。

この後、さらに南の方へ向かう予定だったのですが、道を間違えて入ってきた北の方へ下りてしまいました。

仕方がないので、先に北側のふもとにある、館山市立博物館へ行きました。
博物館では安房里見氏の歴史に関する展示のほかに、一般的な漁師の家の再現など、地域の生活の様子などが展示されていました。

博物館を出た後、1回目とはなるべく違う道をあるきつつ、また天守を目指します。

天守付近には浅間神社もあります。
館山市立博物館の半券で、天守にある分館にも入ることができます。
分館は、南総里見八犬伝に関する資料が展示されています。江戸時代に出版された書籍類や、NHKで放映された人形劇「新八犬伝」の人形や映像などがありました。
途中の階(2階?)だけは別料金で、館山芸術大使であり、NHKの人形劇「新・三銃士」のキャラクターデザインを担当した井上文太の展覧会が開催されていました。別料金だったので入りませんでしたけど。
そして、最上階にある展望台から、館山市を一望することができます。





少し晴れ間も見えてきたので、最初は見えなかった富士山も見ることができました。

改めて、日差しの中の天守。
次に、天守から南へ向かいます。
北側は傾斜が急なのですが、南側はやや緩やかになっており、郭や館などは南側に多く配置されていたようですね。

南にあるのは万葉の径というエリア。

植えられている植物の前に、その植物を詠んだ万葉集の歌が添えられています。

とても雅な試みだと思うのですが、この看板はすげー大量に設置されているので、さすがに全部読むことはできませんでした。

その奥には八遺臣の墓があります。
八遺臣とは、前述したように改易させられて伯耆で亡くなった里見忠義に殉じ、後を追った八人の家臣のことです。その氏名は不明なのですが、後にその遺骨が分骨され、密かに館山まで運ばれて埋葬されたのがこの場所なのだそうです。
一説には、この八遺臣が南総里見八犬伝の八犬士のモデルになったとも言われています。

ここまではよく整備されていた歩きやすい道だったのですが、八遺臣の墓へ向かう道はちょっと山道っぽくなっています。

ある程度下ったところに、八遺臣の墓がひっそりと佇んでいました。


少し戻ったところに、館山藩初代藩主・里見義康の御殿跡があります。ここが館山城の政の中心だったようです。
建物のあった場所に礎石のようなものが埋められていますが、それは建物の位置が分かりやすいように埋められたもので、実際には礎石を用いた建物ではなかったそうです。

その上には梅林があります。
この写真ではわかりにくいかもしれませんけど、義康御殿、梅林、万葉の径、本郭と、明確に高低差がつけられており、それぞれが郭になっていたのだろうなと思います。


天守付近に置いてある、自動販売機。自販機も館山城仕様になっていますです。

最後に、帰り際に駐車場から望む館山城天守です。
館山駅に戻る前にもう一ヶ所、海沿いにある「渚の駅たてやま」にある、館山市立博物館のもう一つの分館・渚の博物館に行ってきました。

館山おさかな大使であり、渚の駅たてやまの名誉駅長でもあるさかなクンのイラストが建物に大きく描かれています。

入り口には、館山がアニメ「戦翼のシグリドリーヴァ」の聖地であることをPRした看板が立てられていました。シグルドリーヴァは見ていなかったのでよくわかりませんけど。って言うか、基本アニメはとりあえず1話はチェックするんですけど、切った記憶も無いんだよなぁ。
千葉県のご当地アニメと言えば、「輪廻のラグランジェ」の方が印象深いです。
中にはさかなクンの手によるイラストや立体物が大量に展示されているスペースをはじめ、漁船や網、針、銛などの釣り具、衣類、漁師の家の復元など、館山の漁業に関する展示、さらには企画展で館山港に関する写真などが展示されていました。
ここは無料で入れるのですが、無料の割には内容が盛りだくさんで、かなり楽しむことができました。

建物の裏にもさかなクンのイラストが。


渚の博物館の裏には、海に長く堤防が伸びているので、ちょっと歩いてみました。
この頃にはだいぶ晴れてきました。電車の時間まで少し余裕があったので、のんびりと海を満喫します。

工事中のため、一番奥までは行けませんでした。今はもう終わっているのかな?

堤防から見上げる館山城です。
館山城は意外と立体感があって、なかなか歩きごたえがありました。周囲はほぼ平野部になっているので、防御能力もそれなりにありそうです。博物館もあるので、歴史を学ぶこともできますしね。
ただ、ひとつ注文を付けるとすれば、館山城の縄張りを示す資料をどこかに用意しておいて欲しかったという点ですかね。どこが郭でどこが堀切でどこに門があって、などがまとめられていると、今でも地形的には割と分かりやすい形で残っているので、歩く際にもとても分かりやすかったと思います。
この後は内房線をさらに東へ移動。途中から外房線に切り替わり、勝浦市の勝浦城を目指します。










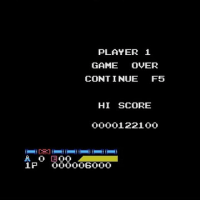

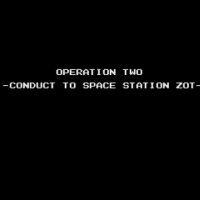












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます