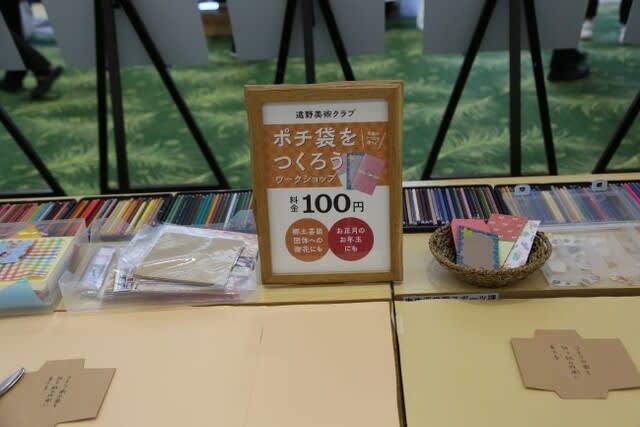共演会の最後です。今回の共演会、昨年までと何が違うと云われて、
一番大きな変化はお客さんの数でしょうか。
特別招待の相去鬼剣舞さん目当てか、初出演となった鱒沢獅子踊りを見るためか、
その両方のだったのかもしれません。
いずれにしても、前年よりお客さんが多いと云うのはうれしいものです。
関係者の皆さんの努力に感謝です!

休憩時間のホワイエも大賑わいでした。
ステージに移ります。

7番目は宮守町の塚沢早池峰神楽さん
この前の連休に遠野座でお会いしたばかりです。笑
見る機会が多いと云うことは、それだけ活動していると云うことになります。
そんな塚沢さんも長い間、低迷していた時期があるそうで、
そこで弟子神楽の平倉神楽さんから習い直しをして、演目の正しい舞を
復活をさせているとのことです。
今どきなので、同じ系統の舞の動画はあちらこちらで入手できますが、
ここで大事なのは正しい・正確なと云うことのようです。

この日の演目は機織の舞
伝えられている神楽本には載っているが、舞は既に絶えている団体が多い演目のひとつです。

若狭の国に住む機織の妻は、都に修行に出た夫へ仕送りをしていました。
ところが3年経っても帰って来ない夫は、都に女を囲っていると云う嘘の話を聞き、
池に身を投げてしまいます。

成仏できない妻は亡邪亡霊になって苦しみます。

それから7日後に夫が帰ってきて、事の次第を聞き、妻を手厚く供養したので、
妻は極楽浄土へ行けたというあらすじです。

亡霊となった妻が、地獄の責め苦を機織に合わせて歌う様を表します。

髪を振り乱しながら機を織る妻は、何ともおどろおどろしく・・・

こんなシーンを見せられると、悪い事はしていないのに、なんだか時々愛妻に
怒られそうで・・・笑

とうとう、刀を持って舞い始めました。

悪霊が付いたようにも見える髪を取り払い、成仏していく様子とでも云いましょうか。

お祭りには選択しにくい演目で、昔は若夫婦の居る家や機織の家では、やらなかったそうです。
レアなものを見せて頂きました!

レアと云えば、トリは鱒沢獅子踊りさんでした!
9月の遠野まつりとこの共演会に初出演です。
幕は丸に向かい鳩で、長野獅子踊りさんと同じ。

鱒沢小学校の生徒さんが習っていて運動会?か何かで演じていると云う情報は、
以前から入っていて、参加する前から、今年は遠野まつりに出るらしいと。

鱒沢獅子踊りの説明でよく云われるのは、寛永3年(1626)の記録で、鱒沢の寺で獅子踊りが
踊られ大勢の見物人があったと云うものですが、この時の獅子踊りが現在の鱒沢獅子踊りなのか
どうかはわかっていません。

小友町にある弘化3年(1848)の獅子踊供養碑には、鱒沢の人の名前があることから、
少なくても、その時期には鱒沢にも伝えられていたと考えられます。

これは昭和40年代に鱒沢の鞍迫観音・白山神社のお祭りで踊られている鱒沢獅子踊りです。
以前、荒谷前のSさんから頂いた写真です。
今はここで獅子踊りは行われませんが、おそらく江戸時代には、ここでも踊られていたものと。

ステージに立った皆さんの顔をファインダー越しに見ていると、太鼓の人で停まりました。
唄いながら太鼓をやっているので、この方が古株なんだと思います。

気になって、2014年の鱒沢三社まつりのデータを見ると、この時の種ふくべさんが
ステージの太鼓の方でした。

10年ぶりに見る鱒沢獅子踊りに感慨深いものがありました。

手踊りの子供達が太鼓の音を口伝で学習していて、キッタカカットデンコデンコ
と口ずさみながら踊る様子に、私も思わず口ずさみました。笑

宮守町鱒沢には、鱒沢獅子踊り、鱒沢神楽、白山神楽(しんがく)、白石神楽、
柏木平神楽(すんがく)、迷岡神楽が伝承されていました。
この中には指導者が亡くなり、伝えることができなくなっている神楽もあります。
人口減少も伴って、これだけの数を維持する困難さは想像以上だと思います。
今回、こうして鱒沢小学校の獅子踊りを見られ、伝承活動をされている皆さんに感謝です。