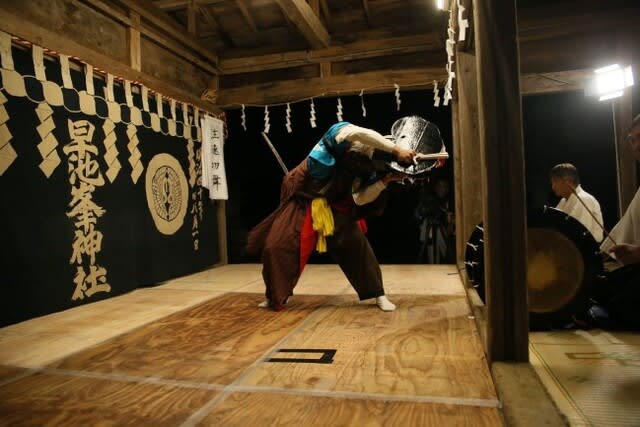16日(金)午後4時過ぎ、徳昌寺でシシ踊りを観た後、急いで帰宅。
汗だらけになったシャツを脱ぎ、ひとまず休憩です。
何だか怪しい天気でしたが、降ってきたら帰るつもりで午後6時過ぎ、また徳昌寺へ。

近くの地区センターでは久しぶりに町内の夏祭りがあり、人並はそちらへ。

時折、送り盆の為に徳昌寺には家族連れが訪れ、新コロ前の雰囲気と同じ感じでした。

関係者の集まり具合から、おそらく7時が舟っこ流しの時間だろうと
思いつつ、境内を散策

和尚様の指示に従い、関係者が半纏を着て、そろそろ出発と思っていた6時50分
火災のサイレンが鳴りました!

ここ上柳だと云うことで、山門を出ると黒い煙が。
夏祭りをしている地区センターの辺りか?いや町中だ!

徳昌寺から薬師橋を渡ると煙と共に赤い炎も・・・。
舟っこ流しに来ていた消防団も皆走りました。
サイレンが鳴ってから何分も経っていない現場では既に放水を始めていました。
初めに書いたように、この日は夏祭りも開催されており、町民の主だった人は
この周辺に来ていたからこその対応だったと思います。
火元は、店をやっている同級生の実家の隣。私が着いた時は、まだ家に人の姿があり、
間もなく、家族全員道路向かいに避難。
それからは、地元消防団や消防署から次々と到着し、延焼を何とかくい止めている頃、
お寺の様子が気になり、戻ると舟っこ流しをどうするか
まだ、結論は出ていないようでした。
以前にも天候の問題で、後日改めて行ったこともあるということでしたが、
別の日となると初盆に合わせて帰省している方もいて、また協力者の手配も。
もう少し、時間がかかりそうだということで、また火災現場へ。
サイレンから20分、ほぼ炎が見えなくなった頃、

薬師橋を歩く一団。舟は流さず、灯ろうだけを流すことに。
火災現場のメインストリート手前を右折し、人知れず猿ケ石川のある片岸橋上流へ。

例年通りであれば片岸橋上で和尚様の読経が聞こえるのですが、
今回は灯ろう流しのスタート地点辺りから声が聞こえました。

誰がこのようなことを想像できたでしょう。

途中、雨でずぶ濡れになるかもしれないとは思っていましたが、
まさか放水とは・・・・。

今年亡くなられた人の家族のことを思うと、この灯ろう流しも大切なこと。

橋の上からは、流していることに気づいた人達が見守っていました。

8時20分過ぎ、無事、灯ろう流しも終わり、火災現場へ戻ると、
放水は続けられていましたが、ほぼ消えた様子。
同級生に一声かけ、帰宅。
これでお盆休みの大きな行事は終わり、月曜から普段通りの生活かな?