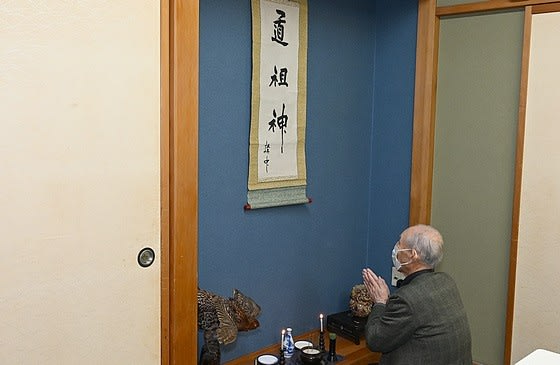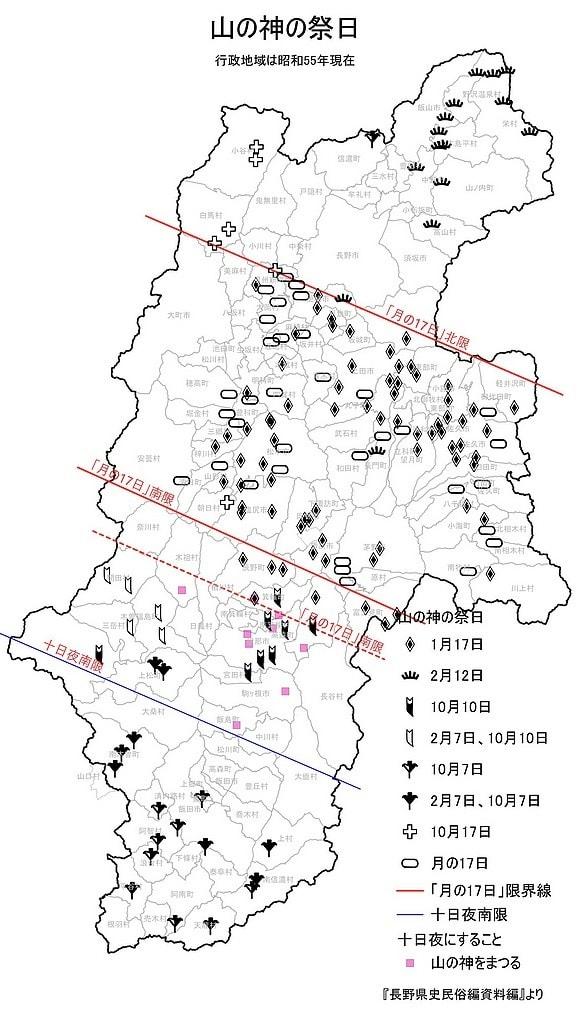(左上)数珠と鉦、(右上)数珠回し(左下)般若心経、(右下)ご詠歌
伊那市手良中坪の米垣外において数珠回しがあった。彼岸のころに数珠を回すところが多いことは、わたしが『長野県民俗の会会報』35号(平成25年)に投稿した「春彼岸の神送り行事」に報告している。それらは過去に実施されていて現在は行われていない事例が多かったわけだが、そこには掲載しなかった数珠回し(念仏)のひとつが米垣外のものである。
ところで「米垣外」と書いて「よながいと」と読む。知らなければ「よねがいと」と読むのが一般的だろう。「よなが」と読むところに少し違和感を抱いたわけであるが、その理由は江戸時代の集落名にあるのだろう。この数珠回しの数珠を納めている箱に掛軸が入っていて、そのひとつが「南無阿弥陀仏」であった。善光寺大勧進の権僧正が書いたと思われるもので、背面に年号が書き込まれている。「寛政十二庚申年冬従善光寺承之」(1800年)とあり、並べて同じ筆跡で「安政五戌午年八月再表具」(1858年)とある。したがって書かれたのは寛政12年ではないのだろうが、寛政12年に取得したものとすると、当時の権僧正は「等順」となる。等順の名が入る掛軸は、安曇野あたりにはいくつも見られる。同様の掛軸が伊那のあたりにもあったということになる。ちなみに等順は善光寺大勧進の住職で寛政10年に権僧正に昇進し、享和3年(1803)に大僧正に昇進している。寛政10年3月5日まで京都竜雲寺の御開帳に、彦根、大津より近江路、美濃路を巡行し、5月7日に馬籠宿へ。12から16日まで松本の生安寺で御開帳、19日に飯田の如来寺(元善光寺)に行き26日まで御開帳。その後高遠満光寺で御開帳を行っている。このころこの地域で念仏講が盛んになったのではないかと推測する。米垣外には念仏塔がいくつか残っており、その中に「当村女講中」で建立されたものがあり、「寛政十戌午天三月」と刻まれている。ようは当順が高遠へ来る直前に建てられたものである。
さて、等順のものと思われる掛軸の裏書には「世長戸講中」とも記されている。この「世長戸」は現在の「米垣外」のことと思われる。その読みが現在に残って「よながいと」と読まれているのだと推測する。米垣外の清水寺の下にある辻に石碑がいくつも並んでいて、その中に「世長戸」と刻まれたものがふたつほどある。いずれも江戸時代に建てられたもので、明治以降のものには「米垣外」とある。
数珠回しは移転して新しくなった清水寺(せいすいじ)の本堂で行われた。麓から少し登った清水寺の旧本堂でこれまで行われていたが、新築された本堂で数珠回しが行われるのは2度目と言う。最初は昨秋の彼岸に行われた数珠回しで、春の彼岸では初めて。コロナ禍を経て6年ぶりの春彼岸の数珠回しだったという。春秋2度行われている数珠回しであるが、清水寺はその場を借りているに過ぎず、数珠回しそのものは米垣外の行事と言う。したがって現在準備をされているのは米垣外常会の役員の方たち。現在21戸という米垣外であるが、井上井月顕彰会とヴィジュアルフォークロアが2011年に製作した動画では25戸であった。その動画を見ると大勢集まっているが、この日は8名だけの参加であった。しばらく女性だけが集まる数珠回しだったようだが、現在は誰でも参加できるということで声掛けをしているようだが、動画撮影されたころに集まっておられたお年寄りが出られなくなって、参加者は減ったという。当時輪の中心で鉦を叩かれて音頭をとられていた高齢の女性が昔の数珠回しのことを語っておられ、昔は男性が数珠回しに参加していたという。鉦を当時叩かれていた女性は数年前に亡くなられたという。
午後1時にみなが集まると数珠が回される。「なむあみだー、なむあみだー」と繰り返し唱え、長い数珠を右回りに3周半回す。それが終わると般若心経と三宝御和讃が唱えられ、数珠回しの行事は終わる。その後茶話会となるが、ここで話をするのが楽しみだという。井上井月顕彰会とヴィジュアルフォークロアが製作した「数珠回し 伊那市美篶笠原・山梨薬師堂 伊那市手良中坪米垣外・清水寺」のもうひとつ、笠原の山梨薬師堂の数珠回しは、コロナ禍で中止されていまもって復活される兆しはないという。