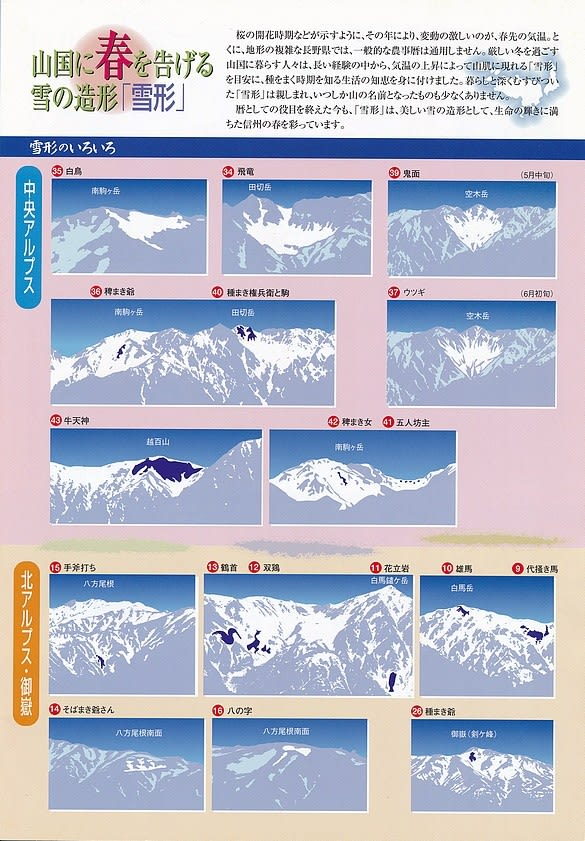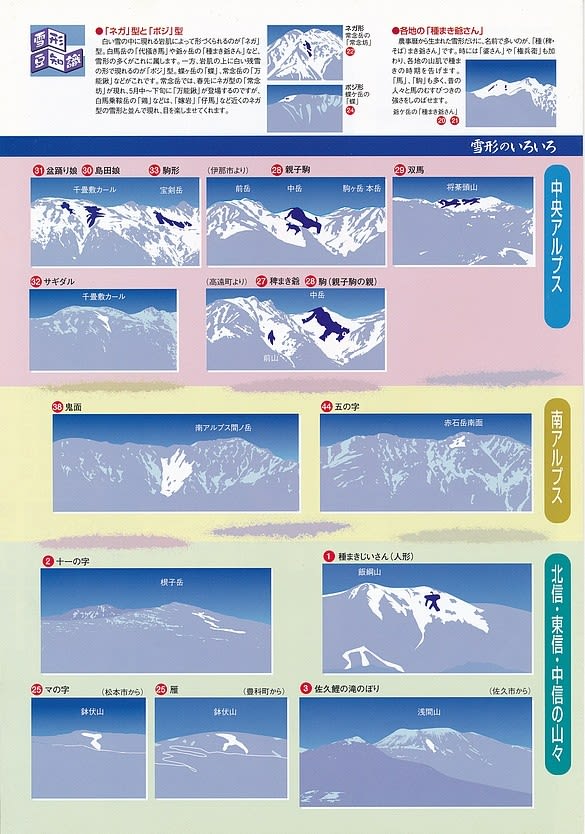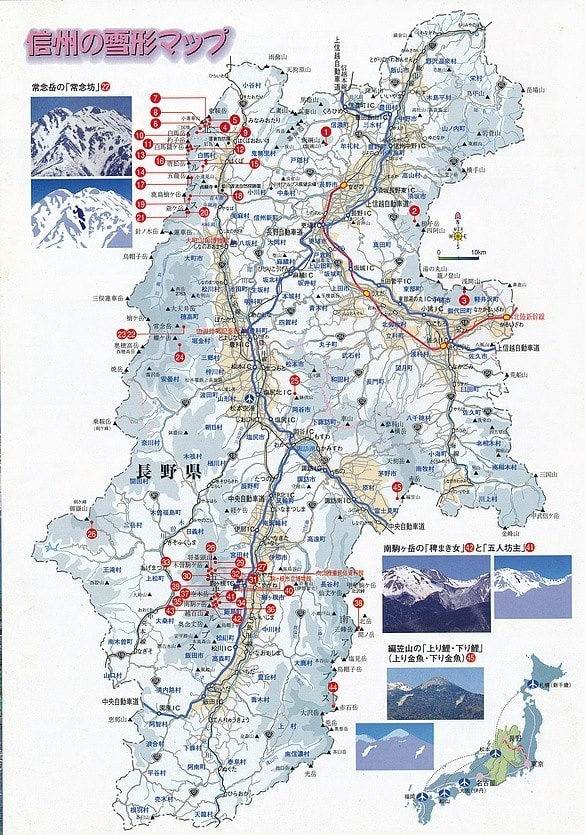ツツザキヤマジノギク 11月9日撮影
過去に何度か触れたツツザキヤマジノギク。長野県版レッドリストの絶滅危惧IA類に指定されているこの花。この地域独特の花だから保全活動も盛んになった。わたしがここに触れた2006年から2008年ころには、地元の人でも認識している人はごくわずかだった。中川村小渋川沿いでこの花が咲いていることを知ったのは、仕事で植生調査した際のこと。遡ること、日記に最初に触れた2006年よりさらに3年ほど前のこと。天竜川の河川敷に多く生育地があることは知ったが、陣馬形山にも生育しているとは聞いていた。その後保全活動が盛んになったのは、天竜川上流河川事務所のかかわりと、松川町に在住されている堤久先生の努力もある。記憶では保全活動が盛んになる前には、「ツツザキヤマジノギク」と検索するとわたしの日記の記事がトップに登場したものだ。
花はノギクと同じなのだが、花弁が筒のように変異を見せる。突然変異とも言えるもので、種を蒔いても必ずツツザキになるわけではない。今年10月9日ころの信濃毎日新聞の地方版に「雨露にぬれる松川町のツツザキヤマジノギク 絶滅の恐れ、はかなげな姿守り続ける住民ら 12日に観察会」という記事が掲載された。かなり大きな写真とともに紹介されたのだが、その記事の写真を見て、「これツツザキヤマジノギクじゃないよね」と家で話題になった。写真の花弁にはツツザキのものが無いのである。せっかく大きな写真を掲載しているのに、それらしい写真ではないのには唖然とした。繰り返すが突然変異だから必ずツツザキ状になるわけではなく、これがそれだと言われれば「そうか」と納得してしまうが、本来のツツザキヤマジノギクの特徴はまったくなかった。
さて、初めて小渋川の河川敷で見たツツザキヤマジノギクを、その後数年にわたって定点観測をしていたが、以後訪れたことはない。今はどうなっているのか知らないが、定点観測している間にも、徐々にその姿が少なくなっていく様子を把握していた。松川町での保全活動に関わっていた妻は、自宅でその種を蒔いて、種をとって増やす活動をしている。そうした活動の中でプランターに種を蒔いて花を咲かしたものが写真である。必ずしもツツザキヤマジノギクの特徴を示す花が咲くわけではないのだが、この株のそれは、ツツザキ状の花弁をどの花も見せている。通常は10月に咲く花だが、蒔いた時期が遅いものだから、今咲いている。「鉢植えでも咲くんだ」とわたし的には驚きであった。
過去の日記から