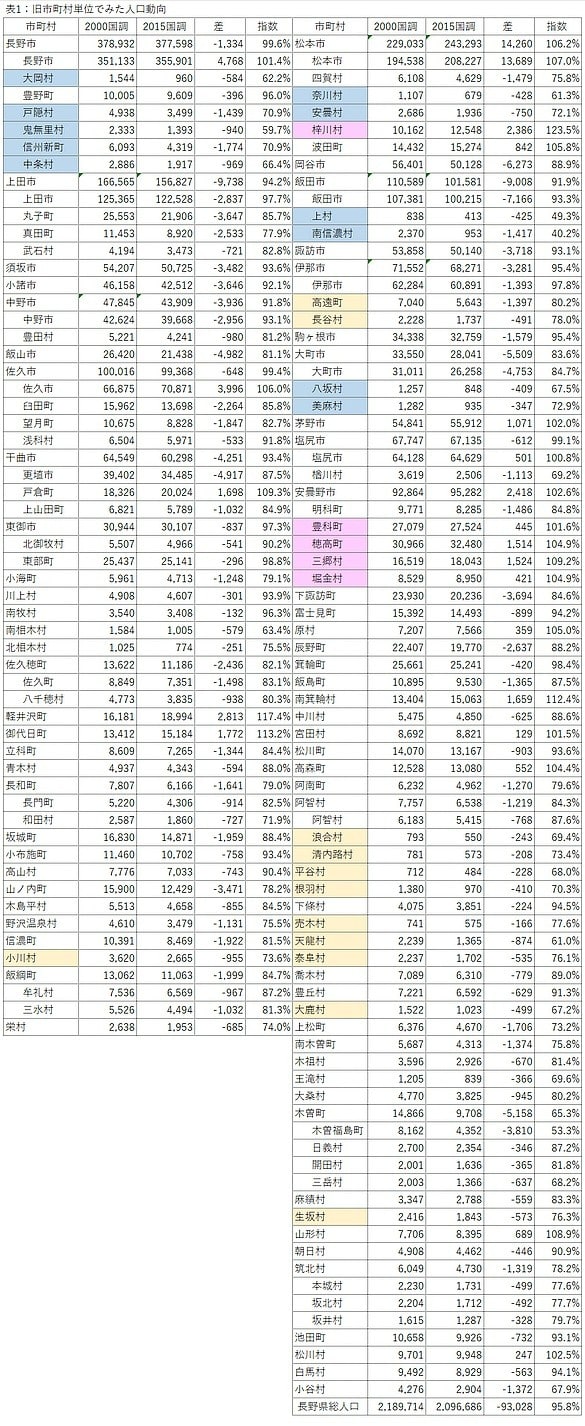先月美篶芦沢の「道祖神講」を訪れたことについて触れた。その際講員のひとり長島さんから子安神社境内にまとめられている自然石道祖神の中に銘文のあるものがあると教えられた。先ごろ講のことで長島さんを訪ねると、子安神社の文字が彫られている石を案内してくれるという。そこで仕事中だったが、子安神社まで案内してもらったわけである。いくつかある自然石の中にひとつだけ一面が平に加工されているものがあり、確かに文字が彫られていることに気がついた。しかし、木々によって太陽が隠されていて陰影がはっきりしない。後日あらためてその石を確認したわけであるが、先日長島さんからも午前9時50分、「今なら陽が当たって文字が浮き出ている」と連絡が入った。

中村伯先句碑(伊那市美篶芦沢子安神社境内)
さて、長島さんからその連絡が入る前にあらためて子安神社を先ごろ訪れたわけであるが、ストロボを利用して強制的に陰影をつけて撮影してみた。それが写真である。右端の文字がはっきり写り込んでいないが、「伯先」と見える。文字の流れが俳句のようにも見えることなどから、これは「中村伯先」の句碑ではないかと考えた。陰影をつけても文字がはっきりと読むことができなかったが、伯先といえば伊那市山寺に句碑があり、そこには「三尺の 雪のうへ照る 月夜哉」と彫られていると、『長野県歴史人物大辞典』(郷土出版社 1989年)の「中村伯先」の項にあった。あらためて子安神社の石に彫られている文字を見ると、まさに同じ句である。左端が欠けているため、完全ではないが、これは中村伯先の句碑であることがわかった。それが自然石道祖神の中に紛れているというところの背景がどういうものだったかは、いまとなってははっきりしないが、石としてはそれほど大きなものではなく、句碑といってもかなり小さな部類に入る。
中村伯先について書かれた前掲書(『長野県歴史人物大辞典』)の内容を下記に引用する。
中村伯先 なかむら・はくせん
江戸中期の儒医、俳人。一七五六(宝暦六)一八二〇年(文政三)。伊那郡西伊那部村(現伊那市)の医師吉川養玄(号は崇広、俳号は白紙関竜水)の長男に生まれ、本名元茂、号は淡斎、医名は昌玄(昌元)、俳号を伯先といった。一六歳で江戸に出て、医術、儒学を学び、三年後帰郷。二〇歳で根津平治郎の娘はくと結婚し、家を弟に譲って中村氏を称し飯島(現飯島町)に住み、二六歳から六年間上穂村(現駒ヶ根市)に済み、その居を駒嶽楼と称した。三二歳から四年間田畑村(現南箕輪村)に住んだ。三六歳の正月京都に行き、医術、本草、儒学を学び、八月に帰った。以来六五歳で死去するまで三〇年間山寺村(現伊那市)に住み、庵号を坎水園と称した。俳諧は初め美濃派の影響を受けていたが、二七歳ころから伊勢派麦林乙由の流れを汲む加舎白雄とまず文書のやりとりによる交流が始まった。二年後の一七八四年(天明四)に白雄の駒嶽楼来訪があり、ここで伯先は白雄門に入り、やがて北信戸倉の宮本虎杖と共に信州における「白雄が両の手の桃桜」と呼ばれたという。八六年(天明六〕には白雄揮毫の芭蕉句碑を上穂村に建立し、これを記念して最初の編著『葛の葉表』刊行した。以後三〇年余り、医学に俳諧に数多くの編著をなし、また後進を育成し、伊那の地に蕉風俳諧を広めた功績は大きい。死去した年に追善集『明月集』が出され、翌年次の句碑が居宅の坂の下に建立された。
三尺の雪のうへ照る月夜哉
ちなみに文責は竹入弘元氏である。
以下にここで取り上げられた昌玄坂の下にある「三尺の雪のうへ照る月夜哉」の句碑の写真をあげる。句碑には「文政四辛巳三月 舜齢及門人建之」とある。伯先の亡くなった翌年(1821年)に建てられたという(文政3年8月23日死去。65歳)。

石質は三峰川上流域のものと思われる。この句碑は『伊那市石造文化財』(伊那市教育委員会 昭和57年)に記載されているが、芦沢子安神社にあることが判明した句碑は、同書に記載はない。