何年か前にだいぶ流行って。その頃図書館で何十人か待ちだったので、課題図書リストの最後尾に入れ……
今回読む番が回ってきた。(しかし結果として図書館から借りずに人から借りた。)
まず、一言で評価をするなら「いい話」。
今どきこんな気持ちのいい高校生なんかいない、と言われたりするほど爽やかなキャラクターたち。
彼らが実に正攻法的に陸上部の成長を目指す。体力的にも。技術的にも。精神的にも。
まあ正直、こんな骨格の話はいくらでもある。いくらでもあるように見える。
しかしわたしは佐藤多佳子の(地味だが)稀有な長所は、技術的なところを逃げずに書くことだと思う。
こないだの「聖夜」でもそうですけどね。
陸上。たしかに一般人でも、学生の頃は運動会や体育の授業で短距離走や長距離走、
まあハードルなんかもやっているし、万人が一度はかじった種目と言えないことはない。
だが佐藤多佳子はそこでなあなあにせずに、ちゃんと調べて書くんだよな、競技としての陸上を。
その部分を書かなくても青春小説、成長小説として成立すると思うんだよ。
恋愛や友情や――自らの経験の範囲内で書けることの比重をもっと多くして、
調べなければ書けないことを減らすというもっと省エネな書き方が出来る。
でもそこを律儀に取材して、ちゃんと“高校陸上部”のハードとソフトを丹念に誠実に書く。
ここが佐藤多佳子のすごいところだね。
そこが第一段階のすごいところとするならば、
第二段階のすごいところは、取材をしさえすれば書けるわけでもないところをちゃんと書くところだ。
まあ結局根っこは同じなのだが、やっぱりそれとこれとは違う能力、違う努力だと思う。
思考は(極論すれば)いくらでも書ける。思考は言葉によって形作られるものだから。思考の材料は言葉だから。
でも感覚は。走っているランナーの感覚、たった12秒で終わってしまう、ある意味では
何も考えていないその12秒を言葉にするんだよ。
――これは相当な技術じゃないか?
赤をどう説明する?「夕日の色」「リンゴの色」に例える?じゃあ夕日やリンゴを見たことのない人に対しては?
本人が体験したことすら、その感覚を他人に伝えるのは困難なのに、
佐藤多佳子は陸上経験者でもなく、経験者の話の聞くことしか出来ない。
そこを我々読者がわかるようにまで工夫して書こうっていうんだから――けっこうチャレンジャーだね。
佐藤多佳子のやっていることは、言葉と感覚の間にある絶望的に深い谷に
人力でこつこつと橋を作っていく事なのかもしれない。
そんな言葉を彼女がどこから得たのかわたしは知りたい。
走っている競技者の走る感覚を――取材によって掬い取ったのか、彼らによって語られた言葉を材料にして
佐藤多佳子が想像力で作り上げたのか、いずれにしてもすごい。そしてその材料を提供した取材対象である
麻溝台高校陸上部の面々もすごい。
巻末に、久しぶりに顔を合わせた座談会が収録されていたが、本文の陸上部の雰囲気そのままで笑った。
昔の仲間と会うと昔に戻るもんね。
※※※※※※※※※※※※
人はもちろん自分の経験に照らし合わせて小説を読む。
陸上部の話は運動会の徒競走の経験を思い出して、
パイプオルガンの話は昔ピアノを習っていた頃の経験を思い出して読むことが出来る。
経験は人によって千差万別のもので、それを手掛かりにして、人は本を読んでいくんだよ。
あれ?ということはつまり、……わたしが面白いと思う本が少ないのは元手となる経験が乏しいから?
いやー、そんな風に考えたことはなかったなあ。目からうろこ。
読みすぎて好みが我儘になっているんだとばかり思っていたが。
でもわたしには好みを突き詰めていって、それがどこへ行くのかを見届けたい気持ちも多分にある。
だから好みの狭さを残念には思いつつも容認している。
結末は確信犯的尻切れトンボ。ここで切るのはある意味見事だが、
――恋愛を完成させてほしかったぞ!あの可愛い恋愛がちゃんと成就するところを見たかった。
わたしの中では谷口若菜ちゃんがフィギュアスケートの宮原智子のイメージで固定されている。
健一くんのリハビリ終わって元気にがんばってる姿も最後に見たかった。
そういう取りこぼしが残念。スピンオフで書いてくれよ、と思う今日この頃。
今回読む番が回ってきた。(しかし結果として図書館から借りずに人から借りた。)
まず、一言で評価をするなら「いい話」。
今どきこんな気持ちのいい高校生なんかいない、と言われたりするほど爽やかなキャラクターたち。
彼らが実に正攻法的に陸上部の成長を目指す。体力的にも。技術的にも。精神的にも。
まあ正直、こんな骨格の話はいくらでもある。いくらでもあるように見える。
しかしわたしは佐藤多佳子の(地味だが)稀有な長所は、技術的なところを逃げずに書くことだと思う。
こないだの「聖夜」でもそうですけどね。
陸上。たしかに一般人でも、学生の頃は運動会や体育の授業で短距離走や長距離走、
まあハードルなんかもやっているし、万人が一度はかじった種目と言えないことはない。
だが佐藤多佳子はそこでなあなあにせずに、ちゃんと調べて書くんだよな、競技としての陸上を。
その部分を書かなくても青春小説、成長小説として成立すると思うんだよ。
恋愛や友情や――自らの経験の範囲内で書けることの比重をもっと多くして、
調べなければ書けないことを減らすというもっと省エネな書き方が出来る。
でもそこを律儀に取材して、ちゃんと“高校陸上部”のハードとソフトを丹念に誠実に書く。
ここが佐藤多佳子のすごいところだね。
そこが第一段階のすごいところとするならば、
第二段階のすごいところは、取材をしさえすれば書けるわけでもないところをちゃんと書くところだ。
まあ結局根っこは同じなのだが、やっぱりそれとこれとは違う能力、違う努力だと思う。
思考は(極論すれば)いくらでも書ける。思考は言葉によって形作られるものだから。思考の材料は言葉だから。
でも感覚は。走っているランナーの感覚、たった12秒で終わってしまう、ある意味では
何も考えていないその12秒を言葉にするんだよ。
――これは相当な技術じゃないか?
赤をどう説明する?「夕日の色」「リンゴの色」に例える?じゃあ夕日やリンゴを見たことのない人に対しては?
本人が体験したことすら、その感覚を他人に伝えるのは困難なのに、
佐藤多佳子は陸上経験者でもなく、経験者の話の聞くことしか出来ない。
そこを我々読者がわかるようにまで工夫して書こうっていうんだから――けっこうチャレンジャーだね。
佐藤多佳子のやっていることは、言葉と感覚の間にある絶望的に深い谷に
人力でこつこつと橋を作っていく事なのかもしれない。
そんな言葉を彼女がどこから得たのかわたしは知りたい。
走っている競技者の走る感覚を――取材によって掬い取ったのか、彼らによって語られた言葉を材料にして
佐藤多佳子が想像力で作り上げたのか、いずれにしてもすごい。そしてその材料を提供した取材対象である
麻溝台高校陸上部の面々もすごい。
巻末に、久しぶりに顔を合わせた座談会が収録されていたが、本文の陸上部の雰囲気そのままで笑った。
昔の仲間と会うと昔に戻るもんね。
※※※※※※※※※※※※
人はもちろん自分の経験に照らし合わせて小説を読む。
陸上部の話は運動会の徒競走の経験を思い出して、
パイプオルガンの話は昔ピアノを習っていた頃の経験を思い出して読むことが出来る。
経験は人によって千差万別のもので、それを手掛かりにして、人は本を読んでいくんだよ。
あれ?ということはつまり、……わたしが面白いと思う本が少ないのは元手となる経験が乏しいから?
いやー、そんな風に考えたことはなかったなあ。目からうろこ。
読みすぎて好みが我儘になっているんだとばかり思っていたが。
でもわたしには好みを突き詰めていって、それがどこへ行くのかを見届けたい気持ちも多分にある。
だから好みの狭さを残念には思いつつも容認している。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】一瞬の風になれ(第1部) [ 佐藤多佳子 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4063%2f9784062764063.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4063%2f9784062764063.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】一瞬の風になれ(第1部) [ 佐藤多佳子 ] |
結末は確信犯的尻切れトンボ。ここで切るのはある意味見事だが、
――恋愛を完成させてほしかったぞ!あの可愛い恋愛がちゃんと成就するところを見たかった。
わたしの中では谷口若菜ちゃんがフィギュアスケートの宮原智子のイメージで固定されている。
健一くんのリハビリ終わって元気にがんばってる姿も最後に見たかった。
そういう取りこぼしが残念。スピンオフで書いてくれよ、と思う今日この頃。










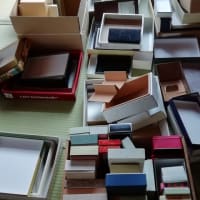














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます