全国のマナスル300ファンの皆様。お待たせしました。
って、何人いらっしゃるのやら?
もしも、これを見て試してみたくなった方はあくまでも自己責任にてお願いします。
ドナーとして購入したのはロジャース製M1950、1951年製でした。
こっちのが価値あるんじゃないかというそこはかとない疑問を抱きつつも写真も撮らずに解体。
予想通りネジ部は合いませんでした。まあ、ほら、オレってばアメリカで仕事した経験もあるし、その辺はティン♪と来るのサ。
いいえ、違います。見栄を張りましたッ。
初めて買ったクルマがJ52というジープで、コイツがエンジンは国産でメートルネジ、トランスミッション以降がアメリカのコピーでインチネジだったからです。
それで、その辺には敏感だったのですね。
話が脱線。
まず、必要箇所をバラして並べてみました。クリックで拡大別ウインドウ。
左がM1950で右がマナスル。
同じく左がM1950で右がマナスル。
上からバーナーヘッド(バーナーハウジング)
バーナージェット(ノズル)
ベーパライザー
プレヒート燃料受け皿
クリーニングニードル
プレヒート燃料受け皿はナットになっていてその下のバルブ部分にねじ込まれますが、ネジの規格は合いません。
その上のベーパライザーは、M1950が外径約9.5mm(3/8インチだな)、マナスルが10mm、これが、面倒なのでいちいち解説を入れないけれど、プレヒート燃料受け皿をフレアナットとしたフレア管接続でバルブに接続されているわけです。
低圧のフレア管接続ではナットとボルトのペアが揃っていれば、管の0.5mmの外径の差なぞ誤差の範囲よ。
マナスルのプレヒート燃料受け皿とM1950のその他の組み合わせ。
燃焼テスト(拡大ナシ)
しばらく燃やしたら、各つなぎ目に火を当ててガス漏れチェック。
ガスが漏れていると火が点く。
問題ナシ!
これでもうバーナー周りが熱劣化しても部品の入手は可能。
僕の人生分は十二分にクリア。それは僕にとっての永遠。
よく歌の文句に「永遠~」とか出てくるけど、僕らが直接関知出来るのは自分の人生分の時間だけ。
だから数十年も永遠も同じようなものさ。
長年(38年半か?)活躍してくれた、旧バーナー周りの部品は埋葬しましょう。
繰り返しますが試す場合は自己責任にて!
責められても
知らん知らんッ!俺はその頃シシリー島でスパゲッティを食べていたんだっ!!
(快傑ズバット23話)
ってとぼけるからね!

















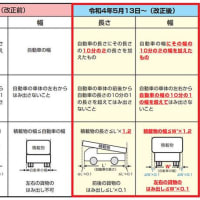




インチとミリ・・その昔、工業学校1年生の製図の時間に、「教科書には『インチネジ(JISで2種類)は、今年で規格廃止』と書いてあるけれど、君たちが現場に行ったときもまだ『残っている』から覚えておきなさい」・・・なんて言われてからほぼ半世紀過ぎるのに、巷にはインチネジも、工具もありふれてますね。
でも、「通しボルト」程度なら近い寸法のメートルネジで代用で来たりするし・・・。
私のカメラのレンズのマウント部、(Soligor 400mm)には学生の時旋盤で自作した精度の悪いネジ(M37)ついてて、しかも間違って60度でなくて、直角のバイトで切りだししてしまったけれど、嵌まるから、使えてるし、・・・水圧とかで漏れなければ使えるんですよね。
・・M50程度のネジ切れる旋盤ほしい・・・
特にサバイバルは意識していませんけどね。
手許にある道具は出来る限り使用可能な状態にしておきたいですね。
インチとメトリック混在で困るのは、建築で使う全ネジ棒です。
3/8と10ミリ、1/2と12ミリ、紛らわしいです。
近々またネジネタが出ます。