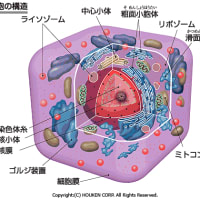1 ストレスが関係している症状はこんなにもある。とんでもない。
がんや精神疾患、その他下記のとおり。
| 部位 | 主な症状 |
|---|---|
| 呼吸器系 | 気管支喘息,過喚起症候群 |
| 循環器系 | 本態性高血圧症,冠動脈疾患(狭心症,心筋梗塞) |
| 消化器系 | 胃・十二指腸潰瘍,過敏性腸症候群,潰瘍性大腸炎,心因性嘔吐 |
| 内分泌・代謝系 | 単純性肥満症,糖尿病 |
| 神経・筋肉系 | 筋収縮性頭痛,痙性斜頚,書痙 |
| 皮膚科領域 | 慢性蕁麻疹,アトピー性皮膚炎,円形脱毛症 |
| 整形外科領域 | 慢性関節リウマチ,腰痛症 |
| 泌尿・生殖器系 | 夜尿症,心因性インポテンス |
| 眼科領域 | 眼精疲労,本態性眼瞼痙攣 |
| 耳鼻咽喉科領域 | メニエール病 |
| 歯科・口腔外科領域 | 顎関節症 |
 私自身は、ストレスから高血圧になっていますし(職場に入るだけで血圧が上がった。)、職場の先輩や部下は、十二指腸潰瘍や円形脱毛症、うつ病になっている。私の子供は、アトピー性皮膚炎や喘息になっている。ということで、身の回りに現実に体験してきたからよく理解できる。
私自身は、ストレスから高血圧になっていますし(職場に入るだけで血圧が上がった。)、職場の先輩や部下は、十二指腸潰瘍や円形脱毛症、うつ病になっている。私の子供は、アトピー性皮膚炎や喘息になっている。ということで、身の回りに現実に体験してきたからよく理解できる。
2 ストレスとは?
もともと物理学の分野で使われていた用語で、風船を指で押さえる力をストレッサーと言い、ストレッサーによって風船が歪んだ状態をストレス反応と言います。医学や心理学の領域では、こころや体にかかる外部からの刺激をストレッサーと言い、ストレッサーに適応しようとして、こころや体に生じたさまざまな反応をストレス反応と言います。
3 ストレッサーにはどんなものがあるの?
「物理的ストレッサー」(暑さや寒さ、騒音や混雑など)
「化学的ストレッサー」(公害物質、薬物、酸素欠乏・過剰、一酸化炭素など)
「心理・社会的ストレッサー」(人間関係や仕事上の問題、家庭の問題など)
その他として、遺伝や生育環境(虐待等)、日頃の思考や行動も関係するようだ。スマホは便利だが、常に現実世界の事象や人に引き戻され、ほっとする時間が失われていることも挙げられる。
4 ストレッサーによって引き起こされるストレス反応は?
心理面・・・活気の低下、イライラ、不安、抑うつ(気分の落ち込み,興味・関心の低下)
感情や記憶をつかさどる大脳辺縁系は、ストレスに弱い。
身体面・・・体のふしぶしの痛み、頭痛、肩こり、腰痛、目の疲れ、動悸や息切れ、胃痛、食欲低下、便秘や下痢、不眠
自律神経・ホルモン・免疫に不調が・・・。
行動面・・・飲酒量や喫煙量の増加、大食い・拒食、仕事でのミスや事故、ヒヤリハットの増加
これらの症状を軽くみないで、早めに対策しないといけないと思う。
5 ストレスホルモンの関係
アドレナリン・・・頑張るストレス 体の反応を引き起こす。
コルチゾール・・・我慢するストレス 心の反応を引き起こす。
6 実情(厚生労働省資料)
心の病に対する労災補償はかなり増加している。
2001年 請求265 人 認定70 人
2016年 請求1586人 認定498人
7 精神疾患
全ての症状に関心があるけど、今回は、精神疾患について、まとめておこうと思います。ストレスが関係していると言われています。すごく気になっています。急速に様々な精神疾患が現れた背景にストレス以外に何があるのか?
統合失調症
かつては 、「精神分裂病」と呼ばれていた。「精神自体の分裂」と解され、誤解や偏見を助長する傾向にあったため、平成14年呼称が変更された。100人に1人が発症。個人差がありるが、主な症状として、実際に存在しない声や音が聞こえる幻聴、あり得ないことを信じ込んでしまう妄想、頭の中が混乱して考えがまとまらなくなる思考障害、興奮症状等があり、これらはまとめて 「陽性症状」と呼ばれる。また意欲の低下や自閉傾向 (閉じこもりがちなこと)など、エネルギーが無くなったような状態になることも多く、これらは「 陰性症状」と呼ばれる。
気分(感情)障害
従来の「操うつ病」「うつ病」「操病」は、新しい分類法では、「気分(感情)障害」という。気分障害は、気分や感情の変化を基本とする障害で、気分が沈んだり、高ぶったりするのが特徴。気分の変化に伴って生活全般の活動性も変化します。また、ストレスが気分の変化のきっかけとなることが多く、しばしば再発を繰り返す。気分障害は、大きく「双極性感情障害」(操うつ病)と「うつ病」の2つのタイプに分けられる。「うつ病」は、以前は「操うつ病」のひとつのタイ プに含めていたが、現在は、独立した診断名としてあつかわれる傾向にある。
「双極性感情障害」は、気分が高揚し、生気がみなぎって活動的となる時期 (操病エピソード)と、気分が落ち込み、元気がなく活動性が下がる時期 (うつ病エピソー ド)を繰り返す病気。「うつ病」は、うつ病エピソードだけがみられる病気。この病気にかかると、患者は、通常、気分が沈み、興味や喜びが失われ、生気がなく活動的でなくなる。ちょっとしたことでも、ひどく疲れやすく感じる。そのほかにも、集中力・注意力の低下、自信の低下、自責感が目立ち、将来を悲観して、自殺を考えるようになったりする。
神経症性障害
神経症性障害は、ドイツ語では「ノイローゼ」。一般の人が使う「ノイローゼ気味」には、神経症以外に、統合失調症やうつ病などが含まれることもあるようだ。 神経症の症状は多彩で、様々なタイプがあるが、その大部分が心理的原因と関連してしていると考えられている。身体的な原因やはっきりとした理由がみつからないにもかかわらず、機能的な障害をもたらすので、周囲が感じるよりも患者の苦しみが強いという特徴がある。現在は、その症状のタイプによって、パニック障害、全般性不安障害、恐怖症性不安障害、強迫性障害、重度ストレス反応および適応障害、解離性障害、身体表現性障害、離人・現実感喪失症候群などに分類されている。
パニック障害
急激に非常に強い不安 (パニック)発作を繰り返す病気。症状は、ほとんど突然に始まり、動悸、胸痛、窒息感、めまいなどとともに、「現実ではない」「気が遠くなりそうな」感じや「 死ぬかもしれない」という恐怖、あるいは「気が狂ってしまいそうになる」恐怖を伴う。発作は、通常数分間しか続かず、生命に危険はないが、これがバスや雑踏などの特定の状況で起こると、その後患者は、そのような状況を避けるようになりがち。
全般性不安障害
パニック障害とは異なり、慢性的な不安を特徴とするもので、不安や心配の材料が次々と移り、何もかもが気がかりになってしまう病気。たえず、いらいらしている。ふるえ、緊張、発汗、頭のふらつき、動悸、めまいと胸苦しさなどの訴えがよく認められる。思者は、家族がすぐにでも病気になるのではないか、事故にあうのではないか、と常に気にしており、心配事が絶えない。
強迫性障害 [強迫神経症]
患者は、不合理と感じながらも意に反して不快な考えが繰り返し浮かんだり (強迫思考)、確認や儀式的な動作を繰り返す病気。具体的には、戸締まりや火の始末が気になって何度でも確認する、不潔が気になって手洗いを繰り返すなどの症状がみられる。患者は、こうした考えや行為をばかばかしいと感じ、かつ不愉快で、なんとか止めたいと努力するが、うまくいかない。そのために、動作に時間がかかり、日常生活が著しく制限される場合もある。
その他
精神疾患とは違うようだが、発達性障害も気になる。発達性障害の一部として「多動性障害」や「注意欠陥多動障害」があげられる。いつも落ち着きなく動き回っている症状だ。
8 ストレス以外の原因
1で表した症状は、ストレスが関係しているし、最初の原因である場合もある。また、何らかの体の不調が原因でストレスが発生し、悪化する場合もあると思う。色んなことが絡み合っていることも忘れてはいけません。生物のバランス体系の中で人間も生きているからです。
ストレス以外でこのバランスを崩している合成化学物質のことを忘れてはいけません。内分泌かく乱化学物質がストレスホルモンに与える影響や遺伝子異常の体への影響の解明が急がれます。
9 できる対策
① 力まず筋肉を緩める・体温を温める
呼吸の仕方を工夫しながら軽い体操をする。⇒最後に紹介してます。
② 避けないで、行動パターンを変えてみる
気晴らしに自分の興味のあることをする。体に悪いことはダメ。旅行に行くことが不可能なら旅行の雑誌を見るとか、いくつかできそうな気晴らしをメモして一覧表にしておく。ストレスから解放されたときに役に立つようなことがベスト。現在の自分の状況・気持ちを素直に伝える。同時に相手の気持ちを考えてみる。代替案を考えてみる。
③ 妄想せずに心を今に向ける
心を今に集中させる。瞑想や集中。⇒最後に紹介しています。
④ 森林浴⇒当ブログの「森林浴=リラックス の理由」に掲載

10 簡単なリラックス法(すべて鼻から息を吸って口から息を吐く)
①目を強くつむりながら息を吸う⇒ゆるめながら息を吐く
②息を吸いながら両肩を上げていく⇒両肩を一気におろして息を吐く
③息を吸いながら目を上に上げる⇒息を吐きながら力を抜いて目を閉じる
④椅子の背に軽く寄りかかる⇒目を軽く閉じて手を足に置く⇒首から下に向かって力を抜いていく⇒太ももの温かさが手のひらに伝わるのを感じる⇒手のひらから両肘、両肩へ温かさが伝えわるのを感じる(感覚的に)
⑤④の状態のままで息を吸いながら手を握る⇒息を吐きながら手を広げる⇒息を吸いながら両手を組んで上に大きく上げる(伸びをする)⇒息を吐きながら両手を下ろし目を開ける。
集中と瞑想(瞑想によって脳の島の部分を活性化させる。)
①背筋を伸ばして椅子に座る⇒軽く目をうすく閉じて、斜め前を見る。呼吸は自然体でコントロールしない。⇒息を吸っている時、「ふくらみ・ふくらみ・・・」と心の中で実況する。⇒息を吐いている時、「縮み・縮み・・・」と心の中で実況する。
②①の状態で、周囲の物音を4つか5つ聞き取る。その中で何か一つの音に集中する。⇒次の音に集中⇒同じく順番に続けていく⇒全部の音すべてに集中する。
参考
大阪府こころの健康総合センターサイト
厚生労働省サイト
NHKサイト