午前中は餅つき
【金ごま】入りの餅がおいしかったので今日も入れた。
前回( 2017/09/10 【金ごま】の「かきもち」を食べたい、と )は
【金ごま】を入れすぎたようで、もったいないと言われた。
今回はスプーン3杯に減らした。
搗き上がるのが待ち遠しい。
これくらいが
適量か。
冷凍【よもぎ】はあらかじめ細かく切り、「フードプロセッサー」にかけていた。
レンジで2分間チンし、
もち米が跳ね上がったころに、
入れた。
だんだんと緑になってくる。
今回もいい色に仕上がった。
午後、開演は1時半だが早めに出かけた。
開場に到着すると
太鼓がはじまったところ。
本日は能楽のプレイベント「なるほど、納得!初めての能楽」。
初心者に能楽のおもしろさを解説してくれる。
明日(10月9日)は二十六世観世宗家 観世清和さんの「翁」と和泉流狂言師
野村萬斎さんの「三番叟」の公演がある。
能舞台。
開演中は撮影禁止。
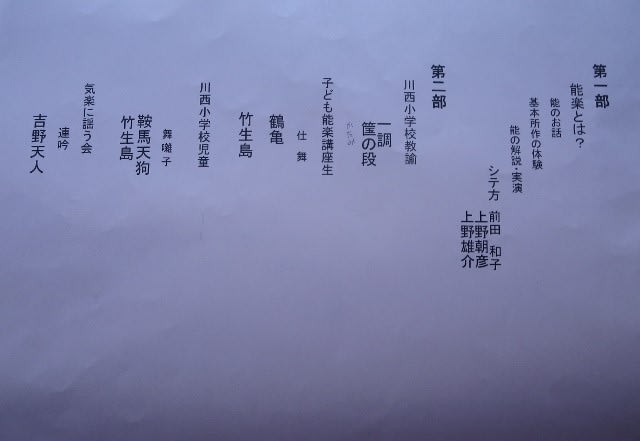

本日のプログラム。
能楽師の前田和子さんが分かりやすく説明してくれた。
「テレビではなく実物の公演を見た人」がほとんどで、「テレビだけで見た人」は
わずかだった。
当地は「能楽・観世流発祥の地」で
( 2008/03/29 天がにわかに曇り、「面とねぎ」が降ってきた )
能楽に対する意識が高いのだろう。
(1)歩き方
音を立てない。すり足で小股に歩く。
能面をかぶると視野が狭くなり、自分の位置を見失わないためでもある。
・ 背筋を伸ばして、爪先を揃えて立つ
・ 扇子は右手、左手は「グー」
・ 視線は遠くに
・ お腹をへこめて、お尻を少し持ち上げる
・ 膝を少し緩めて立つ
・ 歩いて上体がふらふらしないこと
客席から希望者が舞台にあがり、実演があった。
(2)楽器について
舞台での並びは図の通り。
話はそれるが、お雛さんの「五人囃子」と同じ並び。
順番の覚え方がある。右から「謡い(口)」、「笛(下唇)」、「小鼓(肩)」、
「大鼓(ひざ)」、「太鼓(床の上)」。上から順番と覚えればいい。
これも希望者に実演指導があった。他の観客は「エアー鼓」で声を出して練習。
大きな声で「いや~あ」「よ~を」と叫ぶだけで気分が良くなる。
4つの楽器を使うだけ。
楽器の調律はしないという。
(3)「高砂」を謡う
観客は「地謡い」に座ったつもりで「高砂」を謡う。コツは「大きな声を出す」、
「遠くの人に呼びかけるつもり」で謡う。
最初は一小節づつ練習し、次に通しで謡った。
笛、小鼓、大鼓、太鼓の演奏で、腹の底から大きな声を出し、間合いのいい
「いや~あ」「よ~を」の掛け声が入り、気分は爽快。
晴















