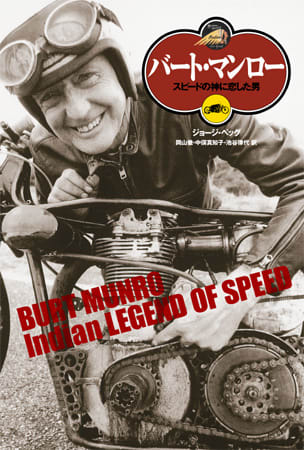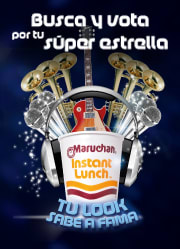
先日、シンガポールで日本のラーメンが大人気とNHKニュースで
取り上げたのですってね。
私はその番組見なかったのですが、香港では「出前一丁」が大人気というのは
この夏、自分の目で確かめたばかり。
そういえば、メキシコではマルちゃんが国民食となっているという話を
以前新聞で読んだ気がして検索してみたら…
色々出てきました。
”(ロサンゼルス・タイムスの)原文記事によれば
「The product is so pervasive that a national newspaper recently dubbed Mexico "Maruchan Nation."
(人気のあまり全国紙では最近メキシコ自国のことを「マルちゃんの国」と呼びました)」という事例があるくらいだ。
さらに「メキシコの新聞が審議を早々と打ち切った議会を『議会がマルちゃんした』と記事にした。
いまや動詞として使われるようだ」という例もある。
メキシコにおいて「マルちゃん」イコール「簡単にできる」「すぐできる」という意味で通じるくらいだという。(中略)
メキシコでの「マルちゃん」の消費量は8年間で10倍に伸び、その量は約10億食。”
http://blog.goo.ne.jp/neo_japan21/e/e6be3114290a8337bcb9d23a3bf53a5d
これは2005年の記事ですので
今は一体どういう数字になっているのかわかりませんが。
こちらがメキシコの「マルちゃん」のHP。
なんだか妙に明るく、ラテン系のノリになっている…w
http://www.maruchan.com.mx/
それにしても何故、日清の「カップヌードル」ではなく
サンヨー食品の「サッポロ一番」でもなく
東洋水産の「マルちゃん」なのでしょう?
不思議です。