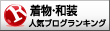28日の朝、発熱。
すぐに近所の発熱外来に電話、中々繋がらなかったものの、その日の午後に予約が取れました。
結果は陽性。
抗生物質と解熱剤が処方されました。
最近、私の周りで続々とコロナ感染者が出ていたので、遂に来たかという感じ。
初日は38℃出て、平熱が5℃台である私には、これでも十分辛い。
全身が痛く、そして喉が痛い。
しかし翌日にはもう微熱に下がり、全身のだるさと喉痛はまだあるものの、これくらいで済めばありがたい限りです。
ただ…
私の味覚と嗅覚は何処へ行っちゃったの?
お昼に夫が買ってきてくれたコンビニのキツネうどんを食べたのですが、出汁の味が全く分からず、甘味だけ僅かに分かるという感じ。
蒲鉾なんて、ゴムを食べているみたい。
匂いもまったく分からず。
味覚嗅覚を失くしたら私の人生、どんなに味気ないものになることか。
周りの友人の話によると、数日で戻った人あり、一ヶ月、二ヶ月かかったと色々なようです。
様子を見るしかないようです。
隔離期間が7日間に短縮されたのはありがたいのですが、年末年始は自宅静養となりました。
夫にうつす訳にいかないので、私は一日中ベッドルームに籠ってなきゃいけないのが面倒です。
すぐに近所の発熱外来に電話、中々繋がらなかったものの、その日の午後に予約が取れました。
結果は陽性。
抗生物質と解熱剤が処方されました。
最近、私の周りで続々とコロナ感染者が出ていたので、遂に来たかという感じ。
初日は38℃出て、平熱が5℃台である私には、これでも十分辛い。
全身が痛く、そして喉が痛い。
しかし翌日にはもう微熱に下がり、全身のだるさと喉痛はまだあるものの、これくらいで済めばありがたい限りです。
ただ…
私の味覚と嗅覚は何処へ行っちゃったの?
お昼に夫が買ってきてくれたコンビニのキツネうどんを食べたのですが、出汁の味が全く分からず、甘味だけ僅かに分かるという感じ。
蒲鉾なんて、ゴムを食べているみたい。
匂いもまったく分からず。
味覚嗅覚を失くしたら私の人生、どんなに味気ないものになることか。
周りの友人の話によると、数日で戻った人あり、一ヶ月、二ヶ月かかったと色々なようです。
様子を見るしかないようです。
隔離期間が7日間に短縮されたのはありがたいのですが、年末年始は自宅静養となりました。
夫にうつす訳にいかないので、私は一日中ベッドルームに籠ってなきゃいけないのが面倒です。