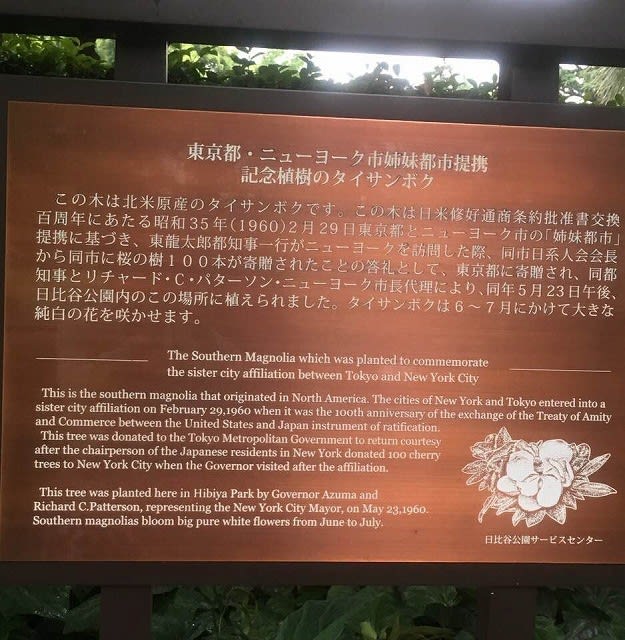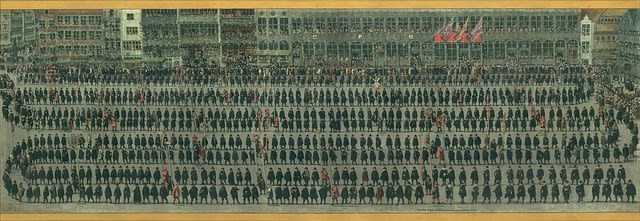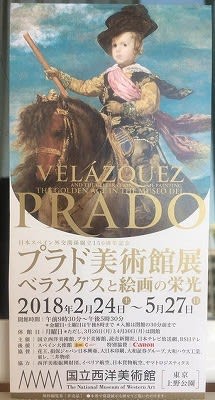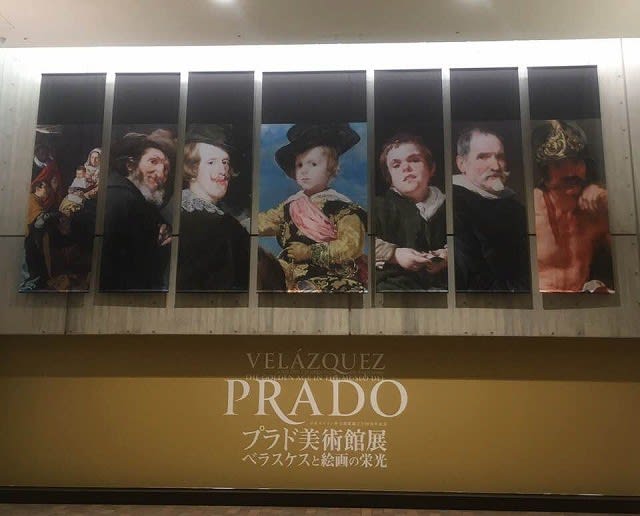椿山荘の向かいにあるこの教会は、日本のカソリックの総本山であるらしい。
椿山荘でお茶やランチをしても、普段この教会は通り過ぎるばかりなのです。
昨日、目白を散歩したついでに中を覗いてみました。
田中角栄邸(門だけ残っている)、和敬塾(「ノルウェイの森」に出てくる、春樹が入っていたという寮のモデル)の前を通り、Otonoha Cafeでランチをして
午後3時頃、聖カテドラル教会の中に入ると…

いきなりパイプオルガンの「主よ人の望みの喜びよ」が高らかに鳴り響いて
度肝を抜かれました。
その後も「トッカータとフーガ ニ短調」など、荘厳なミサ曲の演奏が続きます。
こちらのパイプオルガン、教会用としては日本最大級のものなのだそうです。
そんな立派なパイプオルガンの素晴らしい生演奏が聴けるというのに
その時、聖堂の中にいたのは、私と友人を含めてほんの数人。
なんて勿体ない。
それもその筈、教会のHPにもパンフレットにも
午後3時にパイプオルガンの生演奏が聴けるなんて、何処にも書いてない。
おまけに構内には大きく「撮影禁止」と表示してある。

1964年、丹下健三の設計で建設されたというこの教会、
外観も斬新なのですが、内部はそれよりもっと凄いのです。
祭壇の背後に掲げられた十字架は高さ16メートルあるといい、
その後ろの梯子状の嵌め込み窓から差し込む光が、なんとも柔らかく美しい。
トップライトは下から見上げると、大きな十字架の形をしています。
そこに荘厳なパイプオルガンの演奏が鳴り響くと、私の表現力では上手く言い表せないのですが
クリスチャンでなくとも思わず跪きたくなるような気分になります。
南欧、中欧、北欧、或いはイギリスやアメリカなどの、かなりの数の教会を観て来ましたが
こちらの教会の素晴らしさは、歴史は浅いにしても中々のものです。
「撮影可」にすれば、インスタ映えがもてはやされる昨今、
あっという間に人が押しかけるでしょうに。
余計なお世話かしらん…
写真は下のサイトから頂きました。
東京カテドラル聖マリア大聖堂
https://www.stroll-tips.com/st_marrys_cathedral_tokyo/
#welovegoo