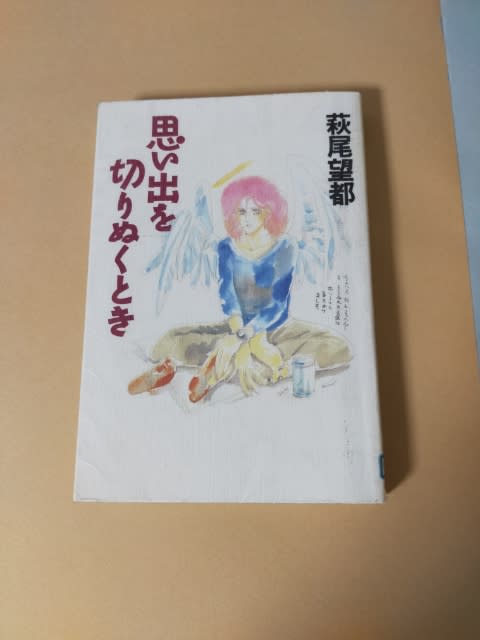書架の探偵(ジーン・ウルフ/ハヤカワ文庫SF)
ジーン・ウルフといえば、20世紀最高のSFファンタジーとも呼ばれる「新しい太陽の書」シリーズの作者だったはず。その評判に魅かれてシリーズ4冊と完結編1冊をいっきに読んだのも、かなり昔のこと。読んでいる間は独特の物語に魅了されるのだけれど、振り返れば全体としてどのような話だったか、さっぱり分からない、という不思議な作品だった。再読すれば見通しがよくなるのかもしれないが、正直、そんな意欲はわかなかった。
で、ともかく最後まで読もうと覚悟して読み始めたが、意外にもすらすらと読めた。
主人公は、過去の作家を複製したクローン人間で、図書館に所属し、貸し出されるのを待っている、という設定。(一定期間、閲覧も貸出もなければ、焼却処分にされる!)ある日、金持ちの若い女性がやってきて、彼を10日間、借りたいという。
そのようにして始まる物語は、テンポよく、ときどき思いがけない方向に展開しながら、最終的に、当初の謎の解明と、殺人事件(題名に探偵とあるのだから、当然でしょう。)の解決にいたる。
本をテーマにした異色のSFだが、本格推理としてもきちんと成立している(ように見える)。読むべき1冊に加えたい。
なお、解説者は、詰将棋作家としても有名な方。
ジーン・ウルフといえば、20世紀最高のSFファンタジーとも呼ばれる「新しい太陽の書」シリーズの作者だったはず。その評判に魅かれてシリーズ4冊と完結編1冊をいっきに読んだのも、かなり昔のこと。読んでいる間は独特の物語に魅了されるのだけれど、振り返れば全体としてどのような話だったか、さっぱり分からない、という不思議な作品だった。再読すれば見通しがよくなるのかもしれないが、正直、そんな意欲はわかなかった。
で、ともかく最後まで読もうと覚悟して読み始めたが、意外にもすらすらと読めた。
主人公は、過去の作家を複製したクローン人間で、図書館に所属し、貸し出されるのを待っている、という設定。(一定期間、閲覧も貸出もなければ、焼却処分にされる!)ある日、金持ちの若い女性がやってきて、彼を10日間、借りたいという。
そのようにして始まる物語は、テンポよく、ときどき思いがけない方向に展開しながら、最終的に、当初の謎の解明と、殺人事件(題名に探偵とあるのだから、当然でしょう。)の解決にいたる。
本をテーマにした異色のSFだが、本格推理としてもきちんと成立している(ように見える)。読むべき1冊に加えたい。
なお、解説者は、詰将棋作家としても有名な方。