(1971/リチャード・C・サラフィアン監督/バリー・ニューマン、クリーヴォン・リトル、ディーン・ジャガー/106分)
 アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。
アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。
一方、この町に向かって一台の乗用車が猛スピードで走っている。運転する男は道路をふさいだショベルカーを見つけて舗装道路を外れる。しばらく行った所で車を止めた男は、車を出て何事かを考える。一体その眼は何を見ているのか・・・。
アメリカン・ニューシネマ真っ盛りの1971年。一台の車が15時間でデンバーからサンフランシスコまで行き着くことが出来るか? そんな賭けをした男が警察の停止命令を振り切って車を暴走させるという話。
そんな話が面白いんかいなと思ったが、評論家筋には好評な点数が多かったので観に行った映画だ。カー・アクションだけの映画ではないかという当初の予想は外れて、ニューシネマらしい結末に向かって上手に構成された面白い作品だった。
吹き替え版をTVで一回くらい観たと思うが、今回数十年ぶりにレンタルDVDにて見直してみた。
「イージー・ライダー」と「栄光のル・マン」を足したようなものと言えばいいんでしょうか。
のんびりとはしてないけどロード・ムービーであり、西海岸からニュー・オーリンズへ向かった「イージー・ライダー」とは反対に、この車はデンバーから西海岸へ向かう。車種は70年型ダッジ・チャレンジャー、色は白、ナンバーはコロラドOA5599。宗教団体のような連中が出てくるのも「イージー・ライダー」に似ている。
「栄光のル・マン」を連想したのは地面スレスレのカメラで撮った車の疾走シーンがあったからで、全体の雰囲気は全然違う。ただ、あのエンジン音は車好きの人にはたまらんでしょうな。
主人公はいわゆる車の陸送屋。金曜日にデンバーに車を届けた折りに、サンフランシスコへ月曜までに着ければいいという車を預かる。その時にクスリを賭けて15時間で西海岸に届けると言い出すのだ。相当なスピードで走らないと着かない計算で、しかも男は車を届けたばかりで休んでもいないのにだ。
ドイツのアウトバーンでもないので暴走すれば当然パトカーや白バイが追跡する。このカーチェイスが見所の一つだ。
最初は白バイが追跡する。次はパトカー。男はどれも振りきる。段々と警察もムキになってきているのが分かる。
何故この男はこんな無謀なことをするのか?
オープニング・シーンの後、話は前々日の暴走の振り出しから再スタートし、徐々に男の正体も分かってくる。
名前はコワルスキー、KOWALSKI。元海兵隊員、元警察官、そして・・・元レーサー。
コワルスキーの話と平行して出てくるのが、西部のラジオ局KOW。
警察無線も傍受しているKOWの進行役はファンキーな盲目の黒人DJ、その名もスーパー・ソウル。コワルスキーの正体が分かってくるにつれて、DJは彼を応援するような放送を始める。やがてコワルスキーの暴走は、マスコミや大衆の関心を集めるようになるのだった・・・。
▼(ネタバレ注意)
過去のシーンや警察情報で分かってくるコワルスキーの過去とは。
海兵隊員としてベトナム戦争に従事したこと。その時に背中に傷を負ったこと。
マリファナをやっていた少女を逮捕した時に、彼女をレイプしようとした先輩警官に暴力を振るって辞めたこと。
その時の少女と恋人同士になったこと。冬の海でサーフィンをして彼女が目の前で亡くなったこと・・・。
やり場のない怒りが溜まっていただろうことが想像できるエピソードが断続的に語られる。
スーパー・ソウルの放送も熱が入ったものになり、それは警官達の反感も買う。
そして、コワルスキーの暴走はついに最終局面を迎えることになる。
リドリー・スコットの「テルマ&ルイーズ(1991)」のラストを観た時にこの映画を思い出した人も多いのではないでしょうか。コワルスキーは薄ら笑いを浮かべていましたが、さてテルマとルイーズはどうだったっけ?
▲(解除)
砂漠で音楽をかき鳴らしている宗教団体みたいなの以外に出てくるのは、ゲイのカップルのヒッチハイカー、毒蛇を獲ってるおじいちゃん、ほっ立て小屋のような家で暮らしているヒッピーのカップル等々。映画の構成上は彼等がいいアクセントになっておりました。
尚、ヒッチハイカーの片割れは「夜の大捜査線(1967)」で軽食堂の店長をやってた男優でした。そして、宗教団体のリーダーは、「インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク(1981)」でナチスの親玉役だった俳優ではないでしょうか?
「イージー・ライダー」と同じく、その頃はやったロックが沢山流れるのも魅力。エンドクレジットで流れていたのは、キム・カーンズ、♪Nobody Knows でした。
リチャード・C・サラフィアン監督がこの映画の前に作ったのは、マーク・レスターが難病を克服する少年に扮した「野にかける白い馬のように(1969)」(=未見)で、全然違う趣の作品のようなので、そういう意味でもサラフィアンの名前は記憶に残るものでした。
VP【原題:VANISHING POINT 】の後は、ジョン・ヒューストン、リチャード・ハリス共演の西部劇「荒野に生きる(1971)」、ロッド・スタイガー主演の「ロリ・マドンナ戦争(1973)」など大御所が顔を出す作品が続きましたが、VP程の話題作にはなりませんでした。
「ロリ・マドンナ戦争」はシーズン・ヒューブリーという可愛い新人が出ていたのと、サラフィアンの新作ということで観に行きました。ヒューブリーの顔も映画の内容も、何年も前に忘却の彼方へ行ってしまいましたがネ。
 アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。
アメリカ西部の田舎町(実はサンフランシスコ近郊という設定)。住宅街を2台のショベルカーがゆっくりと進んでいる。町の住人は何事かと窓の外を覗く。ショベルカーは、町への侵入道路をふさぐように並んで、重いショベルを道路に降ろす。まるでバリケードのように。一方、この町に向かって一台の乗用車が猛スピードで走っている。運転する男は道路をふさいだショベルカーを見つけて舗装道路を外れる。しばらく行った所で車を止めた男は、車を出て何事かを考える。一体その眼は何を見ているのか・・・。
アメリカン・ニューシネマ真っ盛りの1971年。一台の車が15時間でデンバーからサンフランシスコまで行き着くことが出来るか? そんな賭けをした男が警察の停止命令を振り切って車を暴走させるという話。
そんな話が面白いんかいなと思ったが、評論家筋には好評な点数が多かったので観に行った映画だ。カー・アクションだけの映画ではないかという当初の予想は外れて、ニューシネマらしい結末に向かって上手に構成された面白い作品だった。
吹き替え版をTVで一回くらい観たと思うが、今回数十年ぶりにレンタルDVDにて見直してみた。
「イージー・ライダー」と「栄光のル・マン」を足したようなものと言えばいいんでしょうか。
のんびりとはしてないけどロード・ムービーであり、西海岸からニュー・オーリンズへ向かった「イージー・ライダー」とは反対に、この車はデンバーから西海岸へ向かう。車種は70年型ダッジ・チャレンジャー、色は白、ナンバーはコロラドOA5599。宗教団体のような連中が出てくるのも「イージー・ライダー」に似ている。
「栄光のル・マン」を連想したのは地面スレスレのカメラで撮った車の疾走シーンがあったからで、全体の雰囲気は全然違う。ただ、あのエンジン音は車好きの人にはたまらんでしょうな。
主人公はいわゆる車の陸送屋。金曜日にデンバーに車を届けた折りに、サンフランシスコへ月曜までに着ければいいという車を預かる。その時にクスリを賭けて15時間で西海岸に届けると言い出すのだ。相当なスピードで走らないと着かない計算で、しかも男は車を届けたばかりで休んでもいないのにだ。
ドイツのアウトバーンでもないので暴走すれば当然パトカーや白バイが追跡する。このカーチェイスが見所の一つだ。
最初は白バイが追跡する。次はパトカー。男はどれも振りきる。段々と警察もムキになってきているのが分かる。
何故この男はこんな無謀なことをするのか?
オープニング・シーンの後、話は前々日の暴走の振り出しから再スタートし、徐々に男の正体も分かってくる。
名前はコワルスキー、KOWALSKI。元海兵隊員、元警察官、そして・・・元レーサー。
コワルスキーの話と平行して出てくるのが、西部のラジオ局KOW。
警察無線も傍受しているKOWの進行役はファンキーな盲目の黒人DJ、その名もスーパー・ソウル。コワルスキーの正体が分かってくるにつれて、DJは彼を応援するような放送を始める。やがてコワルスキーの暴走は、マスコミや大衆の関心を集めるようになるのだった・・・。
▼(ネタバレ注意)
過去のシーンや警察情報で分かってくるコワルスキーの過去とは。
海兵隊員としてベトナム戦争に従事したこと。その時に背中に傷を負ったこと。
マリファナをやっていた少女を逮捕した時に、彼女をレイプしようとした先輩警官に暴力を振るって辞めたこと。
その時の少女と恋人同士になったこと。冬の海でサーフィンをして彼女が目の前で亡くなったこと・・・。
やり場のない怒りが溜まっていただろうことが想像できるエピソードが断続的に語られる。
スーパー・ソウルの放送も熱が入ったものになり、それは警官達の反感も買う。
そして、コワルスキーの暴走はついに最終局面を迎えることになる。
リドリー・スコットの「テルマ&ルイーズ(1991)」のラストを観た時にこの映画を思い出した人も多いのではないでしょうか。コワルスキーは薄ら笑いを浮かべていましたが、さてテルマとルイーズはどうだったっけ?
▲(解除)
砂漠で音楽をかき鳴らしている宗教団体みたいなの以外に出てくるのは、ゲイのカップルのヒッチハイカー、毒蛇を獲ってるおじいちゃん、ほっ立て小屋のような家で暮らしているヒッピーのカップル等々。映画の構成上は彼等がいいアクセントになっておりました。
尚、ヒッチハイカーの片割れは「夜の大捜査線(1967)」で軽食堂の店長をやってた男優でした。そして、宗教団体のリーダーは、「インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク(1981)」でナチスの親玉役だった俳優ではないでしょうか?
「イージー・ライダー」と同じく、その頃はやったロックが沢山流れるのも魅力。エンドクレジットで流れていたのは、キム・カーンズ、♪Nobody Knows でした。
リチャード・C・サラフィアン監督がこの映画の前に作ったのは、マーク・レスターが難病を克服する少年に扮した「野にかける白い馬のように(1969)」(=未見)で、全然違う趣の作品のようなので、そういう意味でもサラフィアンの名前は記憶に残るものでした。
VP【原題:VANISHING POINT 】の後は、ジョン・ヒューストン、リチャード・ハリス共演の西部劇「荒野に生きる(1971)」、ロッド・スタイガー主演の「ロリ・マドンナ戦争(1973)」など大御所が顔を出す作品が続きましたが、VP程の話題作にはなりませんでした。
「ロリ・マドンナ戦争」はシーズン・ヒューブリーという可愛い新人が出ていたのと、サラフィアンの新作ということで観に行きました。ヒューブリーの顔も映画の内容も、何年も前に忘却の彼方へ行ってしまいましたがネ。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 


















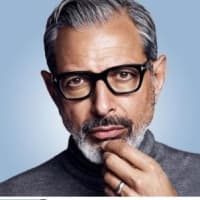




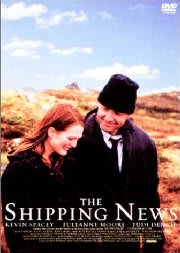
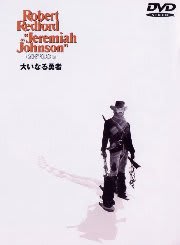
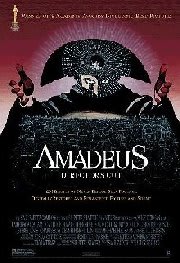
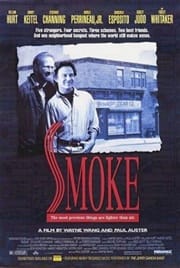







この作品を観た当時は、アメリカの広さが実感できなかったので15時間で横断することがどれくらい大変なことかがよく理解できませんでしたが、観ているうちにどんどん引き込まれた作品ではありました♪
バリー・ニューマン、これ以降ほとんどお姿を見かけないのはやっぱりこの映画のタイトルのせいなんでしょうか(^^;)。
子供の時にはショッキングな結末でした。亜流の作品も沢山生んだような気がしますが。
「明日に向って撃て!」にも通ずるラスト。生きて(逃げて)負けるよりは、死んで勝つといった心境でしょうか?
いずれにしても、アメリカン・ニューシネマに多い、反権力の作品でしたね。
バリー・ニューマンの作品では、「ザルツブルク・コネクション」は凡作でしたが、「爆走!」は結構面白かったですよ。
チャンスがあればまた観たいくらい。
>砂漠で音楽をかき鳴らしている宗教団体
デラニー&ボニーというグループが演じていまして、リタ・クーリッジが一番左の方で歌っていました。
一時期エリック・クラプトンと一緒に活動をしていたこともあります。
>シーズン・ヒューブリー
懐かしいですねえ。
「スクリーン」の表紙裏の広告で初めて見て「うわっ、可愛い女優さんだあ」と興味をそそられました。
実際に本編を見るのは数年後でしたが。
なんかいましたねぇ、そんな夫婦ディオ。クラプトン絡みの記憶がぼんやりと・・・。
>リタ・クーリッジが一番左の方で歌っていました
そうですか。
その情報は持ってなかったなぁ。
いつかレンタルでもう一度見てみます。