(2006/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督/ブラッド・ピット、ケイト・ブランシェット、ガエル・ガルシア・ベルナル、役所広司、菊地凛子、二階堂智、アドリアナ・バラーザ、エル・ファニング、ネイサン・ギャンブル/143分)
1年ぶりに劇場で映画を見ました。
2006年のアカデミー賞で作品賞他にノミネートされ、カンヌ国際映画祭で監督賞、ゴールデン・グローブ賞でドラマ部門の作品賞を獲得した話題の映画です。
原題は【BABEL】。公開時コピーは「神は、人を、分けた。」
旧約聖書の伝説に則り、神により、言葉によって分けられた人間の混乱ぶりを描いた作品です。
 映画は3つのエピソードを平行に描いています。
映画は3つのエピソードを平行に描いています。
一つは、モロッコに観光旅行に来ていたアメリカ人夫婦(ピット&ブランシェット)の奥さんが、バスに乗っている時に何者かに狙撃されて重傷を負う話。
二つ目は、その夫婦のアメリカに残してきた幼い子供たちとメキシコ人のベビー・シッターの話。翌日には故郷で息子の結婚式があるというベビー・シッターは、子供たちの親がモロッコから帰れなくなった為に、仕方なく彼らをメキシコまで連れて行くことにします。日帰りの旅。おめでたい、幸せな日のはずだったのですが・・・。
三つ目は、東京の父親(役所)とその娘で聾唖の女子高生の話。少し前に母親は自殺で亡くなり、二人暮らしとなっているが、娘は母親の居なくなった寂しさからか、訳もなく父親に苛立ち、衝動的になっている。
「トラフィック」の様に断続的にストーリーを語りながら、実は時間軸はバラバラで、それぞれの物語の起承転結の流れが合うように編集されています。観る方にとっては感情の流れがスムースで、個別の話も難しくありませんが、三つ目の日本の親子の話が繋がりとして弱い印象が残りました。
「バベル」=“バベルの塔”のことですね。
あるサイトでは、聖書のこの塔の話を次のように説明していました。
<全地が一つの言語、一式の言葉だった頃に、バビロニアの人々が「さぁ、我々のために都市を、そして塔を建て、その頂を天に届かせよう。そして、大いに我々の名を揚げて、地の全面に散らされることのないようにしよう。」と言った。
神への崇拝の為ではなく、建築者たちの名を上げるために塔を建設する人々。
それを見た神は怒り、人々の言語を混乱させ、彼らが互いの言葉を理解できないようにさせた。こうしてバベルの塔の建設を途中で終わらせた。>
菊池凛子扮する女子高生チエコが聾唖者であることは、何か象徴的な意味合いを持っているのでしょうが、ドラマとしては彼女の心情が分かりにくいし、異様な行動、あまりの激情に置いていかれた気分でした。どことなく思わせぶりなエピソードと感じましたネ。
心も体も裸にならなければ、人間って分かり合えないんだということなんでしょうか?
カンヌ映画祭でこの映画について聞かれ、イニャリトゥ監督はこう答えたそうです。
『言葉は障害じゃない。言葉の壁は簡単に乗り越えられるものだ。だが、偏見から生まれる溝は、なかなか埋まらない。その問題を取り上げたんだ。』
エーッ! じゃあ、「バベル」ってタイトルの意味は何なんだ~っ!
初めて観るイニャリトゥ作品で、個々の描写のセンスはよろしいです。ただ、独りよがりに陥りそうなところが要注意、でしょうか。
それにしても、日本だけ異様な国に見えましたな。今頃の東京の若者って、あんな感じなの?
▼(ネタバレ注意)
モロッコでアメリカ人女性を撃ったのは、現地で山羊を飼育している家族の10代前半の次男坊。ジャッカルが山羊を襲うのを防ぐために父親が銃を買い、兄と一緒に試し撃ちをやっている間に、バスに命中してしまったという話だ。
「テロリストか!?」
このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカとモロッコ両国の国際問題に発展しそうになり、被害者の救済に影を落とす。
同じバスに乗った観光客の間にも対応による混乱が生じ、人間の弱さが露呈する。
人の良いベビー・シッターは、他に預ける人が見つけられずに、何とかなるだろうと幼い兄妹を結婚式に連れてきてしまう。ところが、車に乗せてくれた甥っ子(ベルナル)が前科者で、帰り道でつまらないことから検問に引っかかり、不法に国境を越えることに・・。
灼熱の炎天下、老女と子供たちはニュー・メキシコの砂漠に置き去りにされる。
結局、愚かな人々が発端となった事件ばかりで、ご都合主義がほの見えるのがマイナスです。
三人目の子供が死産だったというアメリカ人夫婦の心の溝も、なんとなく思わせぶりで、個別の登場人物描写もムードに頼っている印象も受けました。作品賞に値するかは疑問ですね。「クラッシュ」もこんな感じなのかなぁ。
三つ目の日本人との接点を書いていませんでした。
父親の趣味がアフリカでのハンティングで、以前モロッコに行った時に、優秀なガイドにお礼としてあげた銃が、モロッコの少年を犯罪者にしたモノなのでした。
女子高生の母親は銃による自殺だったようですが、少女は刑事に『母親は飛び降りて死んだ。』と言います。このウソもよく意味が分かりませんでした。
刑事に渡したメモの中身が分かれば、意図も分かるのかな?
▲(解除)
聾唖の女子高生を演じた菊池凛子は、ベビー・シッターを演じたアドリアナ・バラーザと共にアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされました。私には、バザーラの方が強い印象が残りました。
そして、シタールのような弦楽器の音色が切ないグスターボ・サンタオラヤのスコアは、作曲賞を受賞したそうです。
最も、印象に残ったワン・ショット。
それは、崖の上に立ち、風に向かって大きく両腕を拡げていた、モロッコの兄弟の笑顔でした。事件の前にはあんなに幸せそうだったのに・・・。
1年ぶりに劇場で映画を見ました。
2006年のアカデミー賞で作品賞他にノミネートされ、カンヌ国際映画祭で監督賞、ゴールデン・グローブ賞でドラマ部門の作品賞を獲得した話題の映画です。
原題は【BABEL】。公開時コピーは「神は、人を、分けた。」
旧約聖書の伝説に則り、神により、言葉によって分けられた人間の混乱ぶりを描いた作品です。
 映画は3つのエピソードを平行に描いています。
映画は3つのエピソードを平行に描いています。一つは、モロッコに観光旅行に来ていたアメリカ人夫婦(ピット&ブランシェット)の奥さんが、バスに乗っている時に何者かに狙撃されて重傷を負う話。
二つ目は、その夫婦のアメリカに残してきた幼い子供たちとメキシコ人のベビー・シッターの話。翌日には故郷で息子の結婚式があるというベビー・シッターは、子供たちの親がモロッコから帰れなくなった為に、仕方なく彼らをメキシコまで連れて行くことにします。日帰りの旅。おめでたい、幸せな日のはずだったのですが・・・。
三つ目は、東京の父親(役所)とその娘で聾唖の女子高生の話。少し前に母親は自殺で亡くなり、二人暮らしとなっているが、娘は母親の居なくなった寂しさからか、訳もなく父親に苛立ち、衝動的になっている。
「トラフィック」の様に断続的にストーリーを語りながら、実は時間軸はバラバラで、それぞれの物語の起承転結の流れが合うように編集されています。観る方にとっては感情の流れがスムースで、個別の話も難しくありませんが、三つ目の日本の親子の話が繋がりとして弱い印象が残りました。
「バベル」=“バベルの塔”のことですね。
あるサイトでは、聖書のこの塔の話を次のように説明していました。
<全地が一つの言語、一式の言葉だった頃に、バビロニアの人々が「さぁ、我々のために都市を、そして塔を建て、その頂を天に届かせよう。そして、大いに我々の名を揚げて、地の全面に散らされることのないようにしよう。」と言った。
神への崇拝の為ではなく、建築者たちの名を上げるために塔を建設する人々。
それを見た神は怒り、人々の言語を混乱させ、彼らが互いの言葉を理解できないようにさせた。こうしてバベルの塔の建設を途中で終わらせた。>
菊池凛子扮する女子高生チエコが聾唖者であることは、何か象徴的な意味合いを持っているのでしょうが、ドラマとしては彼女の心情が分かりにくいし、異様な行動、あまりの激情に置いていかれた気分でした。どことなく思わせぶりなエピソードと感じましたネ。
心も体も裸にならなければ、人間って分かり合えないんだということなんでしょうか?
カンヌ映画祭でこの映画について聞かれ、イニャリトゥ監督はこう答えたそうです。
『言葉は障害じゃない。言葉の壁は簡単に乗り越えられるものだ。だが、偏見から生まれる溝は、なかなか埋まらない。その問題を取り上げたんだ。』
エーッ! じゃあ、「バベル」ってタイトルの意味は何なんだ~っ!
初めて観るイニャリトゥ作品で、個々の描写のセンスはよろしいです。ただ、独りよがりに陥りそうなところが要注意、でしょうか。
それにしても、日本だけ異様な国に見えましたな。今頃の東京の若者って、あんな感じなの?
▼(ネタバレ注意)
モロッコでアメリカ人女性を撃ったのは、現地で山羊を飼育している家族の10代前半の次男坊。ジャッカルが山羊を襲うのを防ぐために父親が銃を買い、兄と一緒に試し撃ちをやっている間に、バスに命中してしまったという話だ。
「テロリストか!?」
このニュースは世界中を駆け巡り、アメリカとモロッコ両国の国際問題に発展しそうになり、被害者の救済に影を落とす。
同じバスに乗った観光客の間にも対応による混乱が生じ、人間の弱さが露呈する。
人の良いベビー・シッターは、他に預ける人が見つけられずに、何とかなるだろうと幼い兄妹を結婚式に連れてきてしまう。ところが、車に乗せてくれた甥っ子(ベルナル)が前科者で、帰り道でつまらないことから検問に引っかかり、不法に国境を越えることに・・。
灼熱の炎天下、老女と子供たちはニュー・メキシコの砂漠に置き去りにされる。
結局、愚かな人々が発端となった事件ばかりで、ご都合主義がほの見えるのがマイナスです。
三人目の子供が死産だったというアメリカ人夫婦の心の溝も、なんとなく思わせぶりで、個別の登場人物描写もムードに頼っている印象も受けました。作品賞に値するかは疑問ですね。「クラッシュ」もこんな感じなのかなぁ。
三つ目の日本人との接点を書いていませんでした。
父親の趣味がアフリカでのハンティングで、以前モロッコに行った時に、優秀なガイドにお礼としてあげた銃が、モロッコの少年を犯罪者にしたモノなのでした。
女子高生の母親は銃による自殺だったようですが、少女は刑事に『母親は飛び降りて死んだ。』と言います。このウソもよく意味が分かりませんでした。
刑事に渡したメモの中身が分かれば、意図も分かるのかな?
▲(解除)
聾唖の女子高生を演じた菊池凛子は、ベビー・シッターを演じたアドリアナ・バラーザと共にアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされました。私には、バザーラの方が強い印象が残りました。
そして、シタールのような弦楽器の音色が切ないグスターボ・サンタオラヤのスコアは、作曲賞を受賞したそうです。
最も、印象に残ったワン・ショット。
それは、崖の上に立ち、風に向かって大きく両腕を拡げていた、モロッコの兄弟の笑顔でした。事件の前にはあんなに幸せそうだったのに・・・。
・お薦め度【★★★=一度は見ましょう】 


















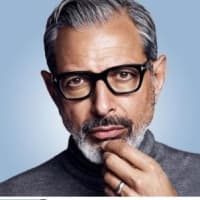



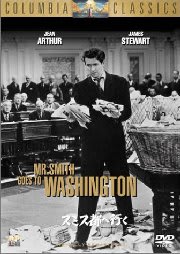



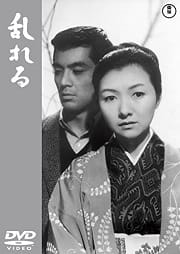







ピット夫婦を最後まで助けてくれた異国の青年の善意が嬉しかったくらいかなぁ。
確かに人間って愚かな動物だけどね。
おまいら、馬鹿だなぁと言われても、返す言葉もない
優れているかそうでないかで言えば、たぶん優れているのだろうけど、好き嫌いで選別するなら、あまり好きではありません。
十瑠さんの書いているように個々のエピソードのセンスはいけてるのですが・・
生理的に
「こんな風にしなくたっていいじゃね~か、ひでえじゃね~か」
という気持ちになってね~
ケイト・ブランシェットの透きとおるような白い肌と看病してくれた現地のばあちゃんのすごい奥目が印象に残りました。
>基本的には面白い作品と言って良いと思います。
★三つは「一見の価値有り」ということですから、同じですね。★★★★に近い★★★です。
「全くつまらない」とか「難解」とかいう意見については、似たような事を考えました。
重々しい雰囲気があった割には、ドラマ描写にはそれ程の深みが無かったという印象です。
作り方は予想された通りですが、前の「21グラム」よりはぐっと整理されているので、好感度は大分アップ。基本的には面白い作品と言って良いと思います。細かな点は是非本文でご確認ください(相変わらずの論文調で恐縮です。長いと余計目立ちます)。
意外と多い「全くつまらない」という人の見識はちょっと理解できない。頭が悪いか、余程の天邪鬼のどっちか。
実際話が理解できない人も多いようですね。子供の頃から200%説明するTVドラマばかり観てたらそりゃ映画を理解する力などつきませんよねえ。
>菊地凛子が聾唖者
なのは、コミュニケーション不全の象徴ですね。彼女の苦悩はモロッコやメキシコといった開発途上国のいらだちでもありましょう。
>彼女が嘘を付く理由
ちょっと思案中。ある程度まで解るような気がしますが、言い得ない感じがあります。宿題です。
こういう辺りは優一郎さんが抜群の読解力を示しそうですね。
作者の一番言いたかったことは何か?
そっちの方が気になります。
同じシーンが、グッときたようですね。
タイミングがあざとい感じもしましたけど・・・(笑)
>崖の上に立ち、風に向かって大きく両腕を拡げていた、モロッコの兄弟の笑顔でした。事件の前にはあんなに幸せそうだったのに・・・。
ここがねえ・・・。ちょっとやられましたね。勿論私のブログに書いたのもこのシーンのことで、映画史に残る素晴らしさではないかと思います。
自分のブログには書き忘れたんですが、サンタオラヤの音楽も素晴らしかったですね。見る前は2年連続作曲賞?と不審に思ってたんですが、みたら納得でした。