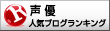イタリアの車で最も販売台数が多いベストセラーは?というクイズがあったら、どう答えますか?
あまり知らない方は、フェラーリ?としか思わないかもしれません。
少しイタリア車に詳しい方なら、フィアット500と答えるのではないかと思います。
でも、残念ながら「ブブー!」です。
正解は「フィアット・ドゥカート」(Fiat Ducato)という車。

乗用車ではなく、いわゆる「商用車」。つまりはたらく車、仕事で使う車です。
イタリア国内で、フィアットのバッジをつけて生産された車だけで、累計約600万台に上ります。
日本の商用バンのベストセラー、ハイエースと同じぐらいの累計生産台数だと言えば、イメージが湧くのでは。
でもハイエースが誕生から約50年経っているのに対して、ドゥカートの歴史は、まだ30年ぐらいですから…
その売れ行きのすごさを想像していただけるのではないかと。
ちなみにトルコやブラジルなどの工場でノックダウン生産されているもの…
また、プジョーなどのバッジを付けて、別の車名で売られているものもあります。
ドゥカートだけでも、台数から言うと、トレーラーや大型トラックを除いたヨーロッパのすべての商用車の…
なんと70%以上ものシェアを誇っているのだそうです。

まさに、商用車の大傑作と言って良いでしょう。
欧州では、こんなふうに荷台の屋根がない、オープントラックタイプのものもあり…

もちろん、EVのバージョンもあります。

救急車としても欧州域内では非常に多く使われているほか…
警察車両に転用されているものもあります。

一般的には、商品を納入する車、宅配用の車、あるいは建築工事現場に資材を搬入する車などに使われますが…
ヨーロッパ各国では青空市場で買い物をすることが盛んなので、そういう場所にお店の資材やテントを運ぶほか…
飲み物やアイスクリーム、食品を売るキッチンカーとして使われることも多いです。
(日本でも移動ケバブ屋さんとかクレープ屋さんとかありますが、ああいう感じです)
また、小型のスクールバスとして使われることもあります。
日本のハイエースは、普通の家庭で自家用車として利用されることも多いですが…
ドゥカートには、積載量が最小2.8トンから、最大4.25トンのバージョンまであって…
外寸も長さが最小で4.96mから最大は6.36mもあり、幅も2mを超えるので、ミニバンの仲間ではなく…
むしろ小さめのトラックの仲間であり、普通の家庭用自家用車には向かないものです。
ここでおさえておくべき重要な点は、イタリア車というと日本では「趣味の車」として見られがちですが…
この車は、あくまでも「実用車」であるということ。
それが、全ヨーロッパで商用車の70%ものシェアを誇るほど、ユーザーに選ばれている理由は…
使い勝手の良さ、車両価格、燃費を含めた経済性、そしてなにより信頼性の高さだと思います。
毎日の仕事でガシガシ使う車がすぐ壊れて動かなくなるとか、修理に費用や手間がかかるとなれば…
あっという間にユーザーから見限られてしまうのは、当たり前のことです。
それが30年間、商用車、実用車としてトップセールスを続けているのですから、それだけ良い商品だということ。
ヨーロッパの人は私たちが思うより倹約家で、そういう部分は非常にシビアなのです。
つまりこの車は「イタリア車は壊れる」「イタ車にはカネがかかる」という神話が…
現実には間違っている。少なくとも「?マーク」がいくつも付く神話である、という証拠です。

ただ、日本人が考える「不具合」と、欧州の人の基準でいう「不具合」は、少し違うというところもありますが。
日本人は、ちょっとダッシュボードからカタカタ振動音が聞こえるとか…
それほど重要でない計器類が、正確に作動していないとか…
どうかすると、ドアやハッチにきしみ音がするとか…
内装のパーツの「チリ」が正確に合ってないというのまで「不具合だ」と言って不満を持ちます。
欧州の人は、確実に走る、曲がる、止まる、各部が開く閉じる…
ライトが点く、ワイパーが動く、エアコンが効いてる…
この程度の基本的なことに問題が無ければ「仕事をする上で別に支障がない」として、トラブルとは考えません。
どうかすると、気に留めない、あるいは気が付かないことでしょう。
ところが日本人は、細かいところまで気になって、オーバースペックを求めます。
というのはありますが…
フィアット・ドゥカートがヨーロッパで圧倒的な支持を受けているというのは…
少なくともドイツ車と比べても、そん色ない、使いやすさ、経済性、信頼性があるからなのは間違いないです。
私が思うに、イタリア車に関する「すぐに壊れる」という良くない偏見は…
1970年代から80年代にかけて、アルファロメオが国営企業だった時代、しかも不景気の時代に…
労使闘争などもあって、労働者のモチベーションが低く、本当に品質レベルが下がってしまったことがひとつ。
(かつてイタリアは、西欧で有数の「赤い国」でした)
あとは、イタリア車と言えば日本でイメージするのはフェラーリやランボルギーニなどのスーパーカーで…
そういったものは、工業製品というよりは手工業品、なんなら工芸品に近い物であるため…
その手の特殊なスポーツカーの品質にばらつきがあるのは仕方ない、という事情があると思います。
あとは、日本のイタリア車のディーラーや、それを扱うメカニックに…
「イタリア車だから仕方ないんですよ」で納得してくれる客に対する「甘え」があって…
良心的でない整備の仕方をしていたり、きちんと「欧州車の使い方」を説明して来なかったからだと思います。
ここで説明した通り、フィアット・ドゥカートというイタリア車が…
欧州の市場で、はたらく車として圧倒的な支持を受けている事実。
また我が家で使って来たアルファロメオたち、歴代3台のうち…
少なくとも2台は、外国車という範疇で見なくても、普通に信頼の置ける車であったという事実。

これが、偏見を覆す証拠になるのではないでしょうか。
買ってまもなくからトラブル続きだった「ロロ」も…

今考えてみると、購入の時点で15年の車歴があったのに、走行距離が3万キロちょっとしかなく…
ほとんどの消耗部品が交換されていない個体で…
そういうものが老朽化して、いろいろ交換が必要なころだったというところに、問題があったのだと思います。
安い値段とはいえ、そういう物を売ってきたS君の親父さんに、ちょっと文句を言って良いのかも。
現にその時の「売り文句」としては、今まで故障で入庫した履歴がない、ということだったんですから。
そう考えると、いちばん心配のないイタリア車選びというのは…
ある程度走って来た中古で、その結果「はずれ玉」でないということがわかっている個体を買うこと。
しかも、必要な交換部品は一通り交換を終え、出る可能性のあるトラブルは全て解決済みで…
良心的で腕の良いメカニックがついているものを選ぶ、ということになるかもしれません。
うちのペッピーノみたいに。

私の義妹夫婦は一貫してドイツ車を乗り継いできていますけれど…
アルフィスタの我が家よりもずっと多くの、しかも呆れたトラブルを、いっぱい経験していますよ。
日本車と全く同じというわけにいかないのは、ドイツ車だろうがイタリア車だろうが、実はほぼ同じこと。
だから、ドイツ車だけが信頼できる外国車、という先入観は捨てて、イタリア車も選択肢に入れてほしいですね。
ちなみに、フィアット・ドゥカートは、もうじきステランティスグループ、つまり…
フィアット、アルファロメオ、プジョー、シトロエン、ジープなどの代理店で、正規輸入するらしいです。
いまでもドゥカートは、キャンピングカーのベース車両として、既に日本にもぽつぽつ並行輸入されています。
それを、正規代理店でも近々扱う…予定、ということですね。
実物はかなりデカい、あくまでも中型商用車なので、普通の車庫に入れるのはきついと思いますから…
キャンピングカーとか、キッチンカーとして改造するか…
それか、ちょっとお洒落さを演出したい都会の業者さんが、商用大型バンとして使うか、ですね。
個人的には、一般のユーザーにはドゥカートより小さい「フィアット・ドブロ」の方が関心を引くと思いますが。

ステランティス・ジャパンは、ドゥカートを日本に正規輸入する際の呼称を…
「デュカト」とするようです。
その方が、日本人が発音しやすいから、と考えてのことだと思いますけれど…
こう表記すると、日本人はアクセントを前に持って来て「デュカト」(太字にアクセント)と呼ぶでしょうね。
実際は、イタリアやその他の欧州諸国では、後ろにアクセントが付いて「ドゥカート」と称していて…
英語を含む欧州系の言語って、アクセントの付く場所が重要で、違うと通じないことが多いんですけど…
まあ、ヨーロッパに行ってこの車を使う日本人は、ほとんどいないから構わない、ということでしょう。
BMWを、日本人しか使わない「ビーエム」という名前で呼んでも別に生活上支障ないし…
イタリア車のMaseratiを「マセラッティー」(セとラにアクセント)と呼んでもイタリア人には分からないですが…
(実際、北イタリアの人は「セ」を濁音にして「マゼラーティ」というのに近い発音をします)
別にそれで問題は起きないですからね。
いずれにしても、イタリア車を含む、ドイツ車以外の欧州車も…
もっと日本での需要が増えるといいな、と個人的に思います。
いま円安の上に、国民生活がこの先もどんどん貧しくなりそうな日本では、難しいでしょうかね……