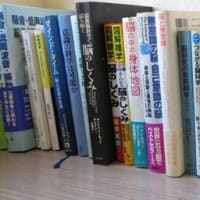保育施設での子供の声をめぐる近隣住民とのトラブルは全国で後を絶たず、訴訟に発展したり事件化したりするケースもある。
平成19年に開園した東京都練馬区の住宅街にある認可保育園では、窓を二重サッシにし、園庭の住宅地側に高さ3メートルの防音壁を設置するなど騒音対策を実施。外遊びの時間も1クラスずつ交代で計1時間45分に制限する徹底ぶりだ。それでも周辺住民らは24年、園側に騒音差し止めと慰謝料を求めて東京地裁へ提訴し、現在も係争中だ。
事件に発展する事例も。国分寺市では26年、保育所近くに住む40代男が、園児を迎えに来た保護者におのを見せ脅迫、暴力行為処罰法違反容疑で逮捕された。男は犯行前日、「声がうるさい」などと同市役所へ電話をかけていたという。
政府が掲げる「待機児童ゼロ」の方針で、保育施設はこの数年、全国で増えている。厚生労働省によると全国の保育定員は昨年4月時点で前年より13万9千人増えた。一方でトラブルも増加。東京都が26年、都内62区市町村を調べたところ、20年度以降、住民から苦情を受けたことがある自治体は約7割の計42団体に上った。
騒音問題を研究する八戸工業大学の橋本典久教授(音環境工学)の相談窓口には全国から相談が寄せられる。橋本教授は「保育園の騒音問題は、首都圏だけでなく全国へ広がりつつある。園側の対策も当然だが、地域側も一定程度の我慢も含めて歩み寄る姿勢が必要だ」と話した。
http://www.sankei.com/life/news/160413/lif1604130007-n1.html
http://news.livedoor.com/article/detail/9377804/
http://www.asahi.com/articles/ASJ4H4VTRJ4HOBJB00H.html?iref=comtop_6_04
子どもの声が騒音かどうかは、「科学的に判定」すべく測定し、環境基準に対応しているかどうかで判定すべきでしょう。ただし、こどもの園庭の遊び声ですから、それは間無しと言う訳ではないのでしょうから、環境省が風車に適応している「移動発生源」と言う意味の解らない定義とか、飛行場の離発着の騒音計算時の”W値、うるささ指数”とかを適用するのがいいのでしょうが、まー、別問題で、受忍限度が登場してくるのでしょうから、難しいというより、普通の人では理解できないでしょうね。では、人間の声はいくらうるさくても、特に子どもに限ってはOKと言う訳にはいかないでしょう。
などとアホなことを敢えて言うのは低周波音被害について国が言う言葉を借りればですの話ですが。。
こどもが何人も集まって遊び回る時の「騒音」は実際には何デシベルでしょうか。かなりでかいでしょうね。それでなければ既に測定し、「環境基準内だ」としているはずです。と思っていたのですが、上記の記事では70dBの時もあるようです。豊田市に於ける裁判も70dBだそうで、やはりこれを目安に問題化するのでしょうね。
この原因は、今時の子どもは家庭での躾のできていない子どもが多く、団地でも道路で数人集まれば自宅の前の道路部分は自分の土地と思っているのか、そこを遊び場として、嬌声を張り上げています。保育園はそれが何十人かですから堪らないでしょう。
全ての責任は「放し飼い的状況では嬌声を上げても良し」として、躾けなかった親にあると私は思います。幼児施設は動物園ではありません。
しかし、しばしば言いますが、それがはっきりと現れているのが、犬の躾。自分の敷地内ならいくら吠えても良いと思っている「親」の多いことか。声=音は敷地内を出ていく。当然、他人に迷惑がかかる、と言う認識が全く無い。
それが自宅から風車までなのが日本国の認識なのでしょう。