
昔、よく透明水彩で西洋古典絵画(油絵)の模写をしていました。理由は模写をしたいけれど、油彩でやると置き場がないし、張りキャンを買うお金もない。やむを得ず、とりあえずやってみようというわけでした。油彩ではできないけれど、水彩でもやらないよりはやった方がいいし、それに実際やったら何が起こるのか、という意味もありました。
で、やってみたらどうなったか。これが意外にも似るのです。正直、びっくりしました。私の場合、色彩を合わせられるのかに興味があったので、デッサンはだいたい合わせる程度でした。使用する紙のサイズはいつもB3で、原画の比率に合わせて水彩紙を切ることはしませんでした。ですから、原画とのサイズが違うので、原画の背景の一部が切れていたり、逆に空が広すぎたり、あるいは背景の一部を引き延ばしたりもします。場合によっては人物の顔が太ったりもします。人物の顔が似ていないこともしばしばです。なぜなら私の興味はデッサンにないからです。
仕上げた模写作品は、A4のトレーシングペーパーを何枚かメンディングテープで留めたもので覆い、それをポートフォリオという紙ばさみに入れて保存しています。トレーシングペーパーと紙とは本来ドラフティングテープで留めるのが紙には良いのですが、面倒なのでメンディングテープで留めちゃってました。もし同じことをする人がいたら、必ずドラフティングテープで留めてください。
本来、模写とは原画をそっくりそのまま写すことではありません。巨匠との対話であり、過去の作品から学ぶために行うのです。何を学ぶかは本人に任されています。もし構図を学びたいなら、原画との縦横の比率を合わせ、原画が油彩であっても、紙に鉛筆で構いません。構図、つまり画面における事物の配置を学びたいわけですから、何も油彩でやる必要はありません。例えば、バルテュスはピエロ・デラ・フランチェスカの厳格な構図に衝撃を受けて画家になった人なので、彼の行ったピエロ・デラ・フランチェスカの模写は、人物の顔がのっぺらぼうです。彼は構図だけ学びたかったわけで、これは正しい模写です。モローは、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵を学びたいだけだっただけなので、ダ・ヴィンチが師匠と共作した絵画の、ダ・ヴィンチが描いた部分だけを模写しました。これも正しい模写です。またマティスがシャルダンの模写をしたときは、面として捉えるという課題を自分に課して行ったので、ごく大雑把なもので終わりにしています。
私の場合、油彩の絵具層の重なり具合、つまり透明層や半透明層をどう重ねれば原画に近づけるのか、に興味がありました。そこにしか興味がなかったので、水彩絵具でやっても勉強になると考えました。ですから古典絵画中心の模写でした。古典絵画は薄い絵具層を幾層も重ねて描かれています。ですから水彩絵具でも再現可能だったわけでした。はっきり言って油彩でやるよりもやりやすいです。一度やってみればわかります。のちに油彩でも模写をしましたので間違いありません。この、透明水彩による西洋古典絵画の模写が、私の油彩技法追究の原点になりました。偶然始めたものでしたがとても貴重な体験でした。
はっきりいって模写は楽しいです。似ても似なくてもどうでもいいのです。何せ勉強ですから。他人に見せる必要など全くない。ただしこの模写、自分で自覚的に始めたときにのみ効果があります。美術教室や学校の授業でやっても何の効果もありません(それはただ無目的にやらされているだけです)。自分でその必要性を感じ、名画から何かを学ぼうとして始めれば、最高の勉強になります。
そして人間には模写する能力があり、名画といえども意外と似せられることを知るでしょう。だからこそ作品にはオリジナリティが最も大切だということ、実はこれが模写から学ぶ最大の成果だと思うのですが、どうでしょうか。
最後に、もし私と同じように、透明水彩で古典絵画の模写をしていてうまく行かない人がいたら、一番安い水彩紙にホルべインの透明水彩絵具で試してみてください。たぶんやりやすいはずです。
で、やってみたらどうなったか。これが意外にも似るのです。正直、びっくりしました。私の場合、色彩を合わせられるのかに興味があったので、デッサンはだいたい合わせる程度でした。使用する紙のサイズはいつもB3で、原画の比率に合わせて水彩紙を切ることはしませんでした。ですから、原画とのサイズが違うので、原画の背景の一部が切れていたり、逆に空が広すぎたり、あるいは背景の一部を引き延ばしたりもします。場合によっては人物の顔が太ったりもします。人物の顔が似ていないこともしばしばです。なぜなら私の興味はデッサンにないからです。
仕上げた模写作品は、A4のトレーシングペーパーを何枚かメンディングテープで留めたもので覆い、それをポートフォリオという紙ばさみに入れて保存しています。トレーシングペーパーと紙とは本来ドラフティングテープで留めるのが紙には良いのですが、面倒なのでメンディングテープで留めちゃってました。もし同じことをする人がいたら、必ずドラフティングテープで留めてください。
本来、模写とは原画をそっくりそのまま写すことではありません。巨匠との対話であり、過去の作品から学ぶために行うのです。何を学ぶかは本人に任されています。もし構図を学びたいなら、原画との縦横の比率を合わせ、原画が油彩であっても、紙に鉛筆で構いません。構図、つまり画面における事物の配置を学びたいわけですから、何も油彩でやる必要はありません。例えば、バルテュスはピエロ・デラ・フランチェスカの厳格な構図に衝撃を受けて画家になった人なので、彼の行ったピエロ・デラ・フランチェスカの模写は、人物の顔がのっぺらぼうです。彼は構図だけ学びたかったわけで、これは正しい模写です。モローは、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵を学びたいだけだっただけなので、ダ・ヴィンチが師匠と共作した絵画の、ダ・ヴィンチが描いた部分だけを模写しました。これも正しい模写です。またマティスがシャルダンの模写をしたときは、面として捉えるという課題を自分に課して行ったので、ごく大雑把なもので終わりにしています。
私の場合、油彩の絵具層の重なり具合、つまり透明層や半透明層をどう重ねれば原画に近づけるのか、に興味がありました。そこにしか興味がなかったので、水彩絵具でやっても勉強になると考えました。ですから古典絵画中心の模写でした。古典絵画は薄い絵具層を幾層も重ねて描かれています。ですから水彩絵具でも再現可能だったわけでした。はっきり言って油彩でやるよりもやりやすいです。一度やってみればわかります。のちに油彩でも模写をしましたので間違いありません。この、透明水彩による西洋古典絵画の模写が、私の油彩技法追究の原点になりました。偶然始めたものでしたがとても貴重な体験でした。
はっきりいって模写は楽しいです。似ても似なくてもどうでもいいのです。何せ勉強ですから。他人に見せる必要など全くない。ただしこの模写、自分で自覚的に始めたときにのみ効果があります。美術教室や学校の授業でやっても何の効果もありません(それはただ無目的にやらされているだけです)。自分でその必要性を感じ、名画から何かを学ぼうとして始めれば、最高の勉強になります。
そして人間には模写する能力があり、名画といえども意外と似せられることを知るでしょう。だからこそ作品にはオリジナリティが最も大切だということ、実はこれが模写から学ぶ最大の成果だと思うのですが、どうでしょうか。
最後に、もし私と同じように、透明水彩で古典絵画の模写をしていてうまく行かない人がいたら、一番安い水彩紙にホルべインの透明水彩絵具で試してみてください。たぶんやりやすいはずです。











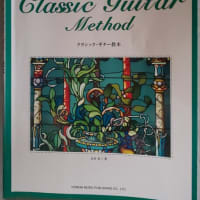





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます