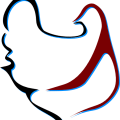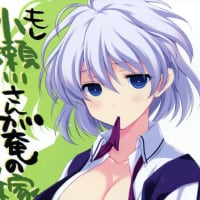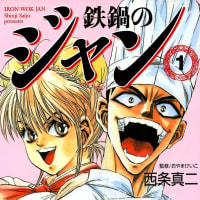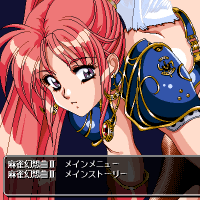タワーリングインフェルノが出る前までの最高傑作映画と言えば恐らくここで紹介するポセイドンアドベンチャーだろう。
と言うか、正確にはこれはタワーリングインフェルノの前哨戦だ。
ここでノウハウを得た特撮をタワーリングインフェルノに応用している。
そういう意味で言うと、技術的にはこの映画がブレイクスルーだったわけだ。
タワーリングインフェルノは大作であるけれども、ポセイドンアドベンチャーはそうではない。っつーか割に小粒な作品かな、とか言うカンジ。この映画は全体で2時間もないのだ。
ストーリーは知ってる人は知ってるだろうが、豪華客船ポセイドン号は海底地震による津波により転覆する。その転覆したポセイドン号から脱出しようとする10名の話である。
いずれにせよ、「転覆した豪華客船から何とかして脱出しようとする話」である。こうやってコンセプトがたった1行で説明出来る映画ってのは良い映画が多い気がする。気がするだけだが(笑)。


ところで、「転覆した豪華客船から何とかして脱出しようとする話」と一行で説明が終わる以上、あらすじに関してはさして解説する事が無い。
ただ、この「脱出に挑む10名」と言うのが仲々濃い面々なのだ。その辺がこの映画を特徴付けてるトコロだろう。
フランク・スコット: カソリックの牧師だが、「力こそ全て」的な異端の思想の持ち主。
マイク・ロゴ: 警察官。だが元娼婦で逮捕した相手が文字通り女房になっている。
ジェームズ・マーティン: 雑貨屋の店主だが、自ら経営してる雑貨屋自体がブラック化してて、暇なしで女に縁なし。
ノニー・パリー: ブラコンの女性。と言うか兄への依存体質。兄が死んだ為精神的支柱が無くなる。
エイカーズ: ポセイドン号の客室乗務員。ケガを負ってるし、特に特徴がないので、脱出トライ組で最初に死亡する事になる(ヲイ
リンダ・ロゴ: マイク・ロゴの嫁で元娼婦の犯罪者。
ベル・ローゼン: 元水泳選手なのに現在デブのオバハン。
マニー・ローゼン: 前述のデブオバハンの旦那。この人も特に特徴がなく、美味しいトコは全部嫁に持っていかれた。
スーザン・シェルビー: スコット神父に恋心を抱く女子高生。設定的にはエロいし美味しい。
ロビン・シェルビー: 前述スーザンの弟で船舶オタク。
濃いだろ?そう、濃い面々で、同じく群像劇の一面があるタワーリング・インフェルノの面々より濃いのは間違いないのだ。
これらの面々がどう動いていくのか、と言うのは実際に映画を観てもらいたいとして。
今回何故にこれを取り上げたのか、と言うと。
知ってる限り、この映画が初めて「キリスト教的な価値観」に疑問を投げかけた映画だと思うから、だ。
映画評によっては、キリスト教的な価値観に異論を初めて突き付けた映画として「ダ・ヴィンチ・コード」を挙げたりしているが、個人的にはそんな事はないと思っている。いや、「初めて」ってのは違うんだよ。
1988年にも「最後の誘惑」って映画があったこともあり、昔から散発的に、洋画で「キリスト教的価値観に疑問を投げかける映画」ってのはあるこたぁあったの。ただ、その時々で無垢なキリスト教徒に反感を買ってただけでな。逆に、「ダ・ヴィンチ・コード」がさして問題視されなかった方が不思議で、これは西欧社会が無垢なキリスト教社会からかなり進歩してきた、って事なのね。良く日本はシャーマニズムの国、とか揶揄されるけど、じゃあキリスト教が「宗教として進んでて原始的じゃないのか」と言われるとそれは違うんだよ。素朴、って事はプリミティヴだ、って事で、実態は文明化されてない、って事なんだ。アメリカも「悪の枢軸」なんつー単純な二元論持ち出して国民が色々と納得してた、って事は素朴な原始人とあまり変わんない、って事なんだよな。んで、ここで言う「素朴」ってのはぶっちゃけ「バカ」の同義語である。
嘘だと思う?例えば90年代、日本がFC/SFCでRPGブームだった時に。米国版ドラクエの教会のデザインが変わってた、って話聞いた事ない?


キリスト教的ナニカは許されないし、キリスト教には色々と配慮せんとならんかった、って事だよな。
んで、当時、どんなに面白くても、女神転生的なゲームはアメリカではリリース出来ない、と言うカンジだったのだ。
いや、かなり最近になって、アメリカ人とかで「女神転生が好き」とか言うヤツが現れるようになってビックリしてるくらいなのだ。曰く「最近だと宗教は宗教、創作物は創作物として分けて考えるようになってきてるよ」と。でもそうなるまで長い時間が必要だったのはヨーロッパ史鑑みても分かるんじゃないか。
それくらい、キリスト教とキリスト教にまつわるモノは色々とややこしかったのだ。ハッキリ言うと「かなりメンド臭い」。そしてその面倒くささは現代でも完全に消えてるわけでもないのだ。
話を戻す。そういう意味で言うと、このポセイドンアドベンチャーはかなり野心的な作品である。
まず主人公的な人物、フランク・スコットが牧師である事。なおかつ、いわゆるキリスト教的な思想を持ってない異端思想者である、と言う辺り。こういう設定は非常に挑戦的だと思うんだ。

キリスト教は「神は全能であり、貴方をずーっと見ている」と言う。しかし、スコット牧師は違う事を言う。「神は忙しい。よって個人を慮る時間がない。」と(笑)。
彼はポセイドン号で日曜学校みたいな事をしてるが、「強くなれ。強くならないと神には認められない」と言うキリスト教的観点で言うととんでもない説法をする。冒頭がこれなんで、彼が強烈なキャラクターなのだ、と言う事を印象づけるのに成功してる。
そしてそれだからこそ、ポセイドン号が転覆事故にあって、「助けが来るまで待ってる」と言う人たちに対して「助かるには力づくで行動せねばいけないのだ」と力説し、その通り行動していくのだ。彼はマゾヒスティックなキリスト教的行動、つまりパッシヴでなく、あくまでアクティヴでいようとする。

そしてその脱出行程。彼を含めて10人が脱出しようと行動するのだが、結局脱出できるのはたった6人。4人は行程で帰らぬ人となる。
3人が失われた時、スコット神父は神に、ハッキリ言うと呪いの言葉を投げかける。
「誰が助けてくれ、と頼んだんだ。一体何人、人身御供があれば貴方は満足するのか。」
と。
そう。実際問題、キリスト教に限らないが、神に祈って物事が解決する、なんて事はあり得ない。
そういう当たり前の「現実」に対して、知ってる限り初めてセリフにしたのがこの映画、である。
そういう意味では、初めて西欧社会の「現代化」を告げたのがこの映画だと思っているのだ。
そしてその現代化の灯火から来年で丁度50年になる。要するに「脱キリスト教」の狼煙から半世紀がやっと経つのである。