
その日彼らは死ぬために回天に乗った。
愛する人を人たちを守れると信じて・・・。
■監督 佐々部清
■原作 横山秀夫(「出口のない海」講談社刊)
■脚本 山田洋次・冨川元文
■キャスト 市川海老蔵、伊勢谷友介、上野樹里、塩谷瞬、香川照之、古手川祐子、三浦友和
□オフィシャルサイト 『出口のない海』
1945年、極秘任務で潜水艦に乗艦した甲子園投手の並木(市川海老蔵)をはじめとする4人の若者。 大事な家族や想いを寄せる女性との未来を諦めた彼らは、死を覚悟して上官の指令を待つ。 脱出装置の無い爆弾兵器、“回天”を操るために。
おススメ度 ⇒★★★ (5★満点、☆は0.5)
cyazの満足度⇒★★★☆
『半落ち』コンビと来れば期待しないわけにはいかない。
まして佐々部監督はぼくの好きな監督さんだ。 山田洋次の脚本でどのように戦争において死を覚悟の戻れない選択を選んだ若者の姿を描き出すのか。
お国のために自らの死を持って敵艦に体当たりを食らわす回天。 この使命に携わる人間たちは、現代に置き換えると高校生や大学生のような若い世代である。 現代に生きる若者が「お国のために死んで来い」と言われれば、それこそ全員が逃げてしまうようなものだろうけど、選択肢がない戦争という舞台にでは、生きることより、死んでいくことが肯定され、ある意味美化されてしまう。
死を覚悟して打ち放たれる回転がうまく作動せず使命を果たせず生き残る儚さをカメラはクローズアップしていく。 実際には、死んで当たり前、生きて戻れば卑怯者。 そんな時代に生きることは今では全く想像を絶することなのかもしれない。 ただそればかりを強調されても、「ただ泣けと言われてに過ぎない」ような感じは否めない。
爽やかなイメージの中で強いメッセージはないものの、死んでゆけるもの、そうでないものが、それぞれの“想い”と恐怖を、互いを慰めあい、奮い立たせることでその恐怖を払拭しようとする。 死にゆく者に、複雑な回転の操縦はかなりのプレッシャーであったと想像できる。 2度と戻れない決心をして回天が何かのトラブルで動かないときの表情は恐らくこんなものではなかったろう。
派手さはないものの、人間重視の視点と、友情・家族愛を優しく描いた作品だが、今ひとつ心を動かすものが足りなかった感じだ。
佐々部監督をもってしてもなかなか難しい表現だったのかもしれない。 そして監督の地元で映画を撮ることも今まで同様だ(ま、これは史実に基づいているので)。 今回も山口県を中心に描かれている。
海老蔵はやはり今の青年とは違い、この時代の骨太な青年を演じる方が合っているような気がする。 現代を描く映画より、はるかに時代劇の方にベクトルを向けたほうが正解であろう。
伊勢谷友介も幅の広い役者に成長してきたと思える。 特に最近の作品では力がついてきた。 そして力が出てきたから、彼の得意なサイズの役柄に自然にベクトルがむき出した感がある。
この映画だけではなく、最近昭和の時代を描いた作品が多いのだが、古手川祐子の髪の色があまりに茶色いのには興醒めした。 せめて映画のためだけに、黒髪に染め直すことぐらい監督に言われなくても、十分キャリアのある女優としては必要なことではなかったのだろうか・・・。
何気ない家族のシーンには、先日観た『紙屋悦子の青春』の卓袱台的シーンもあったが、常に冷静を装っていた父親(三浦友和)が、「おまえは敵の顔を見たことがあるのか?」 という言葉があった。 これが意味することは本当に大きかったように思う。 つまり戦争のあまりに悲惨な側面がこれであろう。
主人公が肩を潰したピッチャーという設定は、人間同士のキャッチボール必要性を作り手側が密かに訴えていたのではないだろうか。
人が人として命を奪うということ。 そんな悲しい現実は過去のものではなく、今も形を変え存在している。
昨年から続く戦争映画に今の若者たちは何を感じるのであろうか。 自分を含めてもう一度考えてみる必要があるのかもしれない。
こんな自堕落な未来のために、俺たちは命を掛けて戦ったのか?
荻原浩の「僕たちの戦争」のなかの言葉が繰り返し脳裏を掠めていた・・・。




















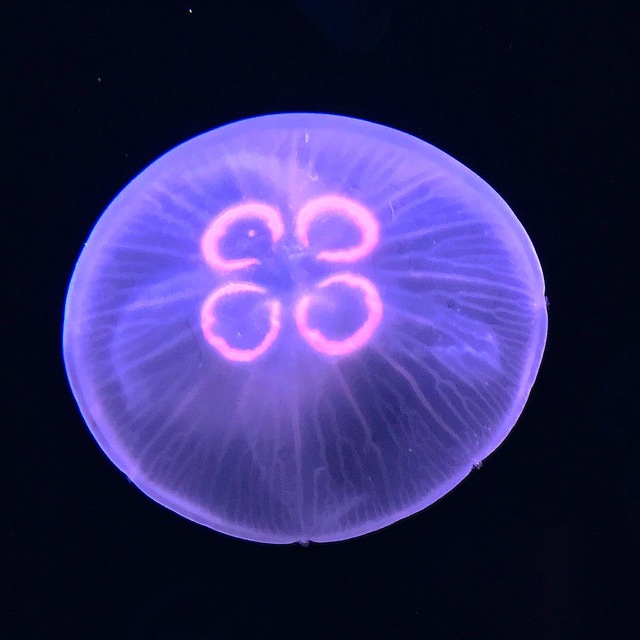





期待した一人です。
映画の出来はいま一つだったけれど
キライじゃありません。
とても静かな「反戦映画」だったと思いました。
TBさせていただきます。宜しくお願いします。m(__)m
昨年の「男たちの~」に比べると派手さはありませんでしたが、それなりに良かったと思います。
いろんな感想を読ませていただくと、「回天」を初めて知ったという方も多くて、それだけでも意味があったのかなと思います。
海老様はこういう時代がかった役が似合うのかもしれませんね。
たまたま「回天」がらみで時を同じくして「出口~」と「僕たち~」をみました。
>こんな自堕落な未来のために、俺たちは命を掛けて戦ったのか?
私も、「出口~」を観ながらずっと脳裏を掠めていたのがこのことでした。
また「軍神」などとよくもまぁそんな言葉で純粋な若者を操ったものだと思うと切ないです。
靖国問題もわかる気が・・・。
確かに 訴えかけるものが 描写不足だったと思いますね~~^^ 結局 言いたい事は
わかるんですが・・・(わかってるつもりだけかもしれませんが^^;)
勝手な解釈ですが きっとこんな事を 伝えたかったんだろう、ならば もっとこう描けば・・・というような もどかしさはありました。それでも ズジーンときたのは、主人公の最後の笑顔(野球の球を投げる)・・・。 あれに参りました^^
この手の映画に物申したら罰が当たりますね。
台詞にあったごとく「回天」を世に知らしめるため、たくさんの人に観てほしいと思いましたが。
原案・脚本が山田洋次、で納得です。(いえ、決して嫌いな監督さんではないのですよ。)
「主人公が肩を潰したピッチャーという設定は、人間同士のキャッチボールの必要性を作り手側が密かに訴えていたのではないだろうか。」というところにとても共感できました。この映画では、やはり、キャッチボールというのはとても重要なファクターなのですね。
>映画の出来はいま一つだったけれどキライじゃありません。とても静かな「反戦映画」だったと思いました。
そうですね! 佐々部監督に派手な「反戦映画」はそもそも無理ですからね^^
>いろんな感想を読ませていただくと、「回天」を初めて知ったという方も多くて、それだけでも意味があったのかなと思います。
そうですね! 僕らの年代を含め若い人たちが知ってくれることは意味があると思います。
靖国神社にレプリカがあるそうなので、いつか見に行きたいと思っています^^
>海老様はこういう時代がかった役が似合うのかもしれませんね
丹精な顔立ちですからね! 僕みたいに(笑)
>たまたま「回天」がらみで時を同じくして「出口~」と「僕たち~」をみました。
なるほど、集中でしたね(笑)?
>また「軍神」などとよくもまぁそんな言葉で純粋な若者を操ったものだと思うと切ないです。
靖国問題もわかる気が・・・。
難しい問題ですが、蚊帳の外ではない重要なことですよね?
>結局 言いたい事はわかるんですが・・・(わかってるつもりだけかもしれませんが^^;)
そうでしたんね(笑)
>それでも ズジーンときたのは、主人公の最後の笑顔(野球の球を投げる)・・・。 あれに参りました^^
そこがキャッチボールのいいところであり、実にイイ比喩でした!